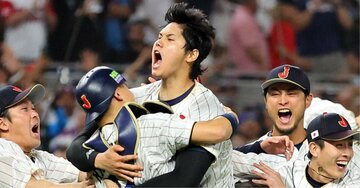PR専門家ジョーダン・グリーナウェイの分析によれば、この戦略が成功した理由は「製品の品質の核心を突かない」スキャンダルだったこと。彼らは「製品の品質をからかっているのではなく、すでに辞任したCEOをからかっている」のだ。例えば2013年に起きた馬肉スキャンダル(編注:「牛肉100%」と表示された製品に馬肉が混入。アイルランドから始まり、ヨーロッパ全体に広がった)のような製品品質問題ではユーモアは不適切だが、今回は違う。結果として、ウェブサイト訪問数が1万5000%急増という、どんなマーケティングキャンペーンでも達成不可能な効果を生んだという。
デジタル時代をサバイバルするコツは「炎上の種を作らない」こと
しかし、この「教科書に載せたいほど見事なPR戦略」の成功も、ある意味では結果論に過ぎない。グリーナウェイ自身が「彼らがやっていることをする勇気が私にあったかどうかはわかりませんが、あったことを願います」と述べているように、理論上はアリでも実行には相当な度胸が必要だったし、もし動画が逆炎上していたら「最悪の判断」と酷評されていたかもしれない。アメリカのこの不倫カップルを我々日本人すらSNSで笑っていたほどのグローバルな注目度では、ほんの小さなきっかけで逆炎上も大いにありえたのだから。
現代のウェブ社会はあまりに巨大で、深く、参加者も不確定要素も多すぎる。セオリー通りに世界が動くかどうかは、もはや誰にも予測できない。バタフライ効果の嵐のような環境で、小さな判断ミスが予想もしない大災害を招いたり、逆に絶体絶命のピンチが思わぬ大成功に転じたりする。それはもう、結果論だ。
「集合知」や「群衆の心理」は、従来のマーケティング理論では捉えきれない複雑さを持っている。「何がヒットするかもう全然読めない」という意味で「人類は企画に向かない」なんて企画担当者界隈からのあきらめに似た自虐も聞こえる。今回のアストロノマーのケースは成功例として語り継がれるだろうが、同じ手法が次回も通用するとは限らない。現代のPR担当者たちは、確実な方程式のない世界で、手探りでハラハラしながら仕事をしているのが実情ではないだろうか。
デジタル時代のサバイバル術として、我々が学べることがあるとすれば、それは「愛は盲目だが、カメラは見ている」という戦慄の現実を忘れないこと。そして何より、最高のリスク管理は「最初から炎上の種を作らない」ことなのである。そんなこと言われても、PR担当者たちからすれば「まさかウチの元CEOが人事部長と公然とバックハグするなんて、誰が予想できる?」だとは思うけど。