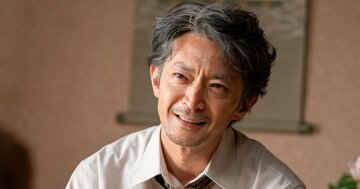第一話の冒頭が再び。「あんぱんまん」誕生
体調が悪いにもかかわらず東海林が東京に来て、ふたりのやってきたことを認めてくれたことを重く受け止めたのか、嵩は意を決してアンパンマンを描き直す。
そのときの嵩の目元のどアップ。キラーン。
一晩かけて描き上げていく。時計の秒針が進む音が効果的に使われている。
朝、「嵩さん、おはよう、朝だよ」とのぶが窓を開けた。
これは第1話の冒頭と同じだ。あのときのシーンは長い間、嵩が悩みに悩んだ末にたどりついたものだった。ただし、第1話の使いまわしではなく再撮影されている。
北村匠海が本日公開されたインタビューで語ったことが印象的だ。
「僕はこの半年、やなせたかしとして生きたのではなく、柳井嵩として生きたからだというのを強く感じました」
第1話を撮ったときと第120話では違う人物になっていた。やなせたかしと柳井崇は違う人物だという自覚は興味深い(詳細はインタビュー記事を参照ください)。
「こんなヒーローはじめて見た」とのぶ。
今度は頭がアンパンで、その顔を飢えた人に食べてもらうキャラになった。
「命を削って会いに来てくれた」東海林のように命を削るキャラになったのだ。
命を削るが、あんぱんまんの命は終わらない。頭が半分欠けて飛びたっていった先に、待っているのはジャムおじさん。彼があんぱんまんの頭を修復してくれる。
「パン作りのおんちゃんが新しい顔を」と嬉しそうに笑うのぶ。このおんちゃんは、どこかヤムおんちゃん(阿部サダヲ)に似ている。
こうして子ども向けの絵本『あんぱんまん』が昭和48年(1973年)10月に出版された。
「アンパンマン」から「あんぱんまん」になったのは子ども向けだからと嵩のモデル・やなせたかしは言っている。
やなせたかしは「チリンのすず」「チリンの鈴」もそうで、平仮名、片仮名、漢字と表記をたびたび変えていて、ややこしい。
「エヴァンゲリオン」なのか「ヱヴァンゲリヲン」なのか。「リーガルハイ」なのか「リーガル・ハイ」なのか、ややこしい作品は時々ある。試行錯誤や工夫があるのだとは思うが、のちに混乱するからできれば控えてほしい(冗談です念のため)。
タイトル表記が揺れているのは、やなせたかしが常に思考が定まらない人であったと想像できる。ひとつの仕事に絞れず、あれこれ手を出していたのもそのせいであろう。
のぶは性懲りもなく(言い方)、子どもたちに読み聞かせをする。のぶはいつの間にか、お茶の教室をはじめていて、お茶のお稽古のあと、来ている子どもに『あんぱんまん』を読み聞かせているのだ(便乗商法?)。
今回は、正真正銘、子ども向けではある。だが子どもたちは、見た目はかわいいが、顔を食べるという行為を気持ち悪がっていたりもする。それでものぶは諦めない。
八木(妻夫木聡)関連の子どもたちの施設にも『あんぱんまん』が納入された。
この流れで気になるのは、お茶教室の生徒として、何の説明もなくエキストラのお茶の生徒たちと並んで、しれっと古川琴音が座っていることだ。彼女は次週予告にも出ているので、終盤を彩る役割を担っているようなのだが……。