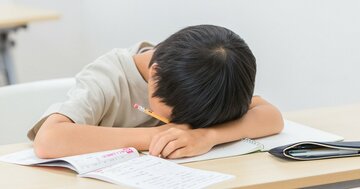写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
1980年代に放送された学園ドラマ『3年B組金八先生』は、学校教育が抱える問題を真正面から描いた作品として語り継がれている。そこには、教師と生徒の関係性や、学校で行われる“線引き”に対する問いかけが込められていた。漫画『ドラゴン桜2』の編集を担当した西岡壱誠氏は、そんなドラマが映し出した教育観を読み解きながら、生徒の“分け方”がもたらす影響について考察していく。※本稿は、西岡壱誠『学園ドラマは日本の教育をどう変えたか “熱血先生”から“官僚先生”へ』(笠間書院)の一部を抜粋・編集したものです。
伝説として語られる学園ドラマ
「金八先生」が描いた80年代
「できる生徒とできない生徒の二極化」の対立軸がはっきり描かれたのが、「3年B組金八先生」だった。このドラマはスペシャル版も合わせて長寿番組となるわけだが、どのシリーズでも「その当時の生徒の抱える問題」について触れられていく。
最初の第1シリーズでは「中学生の出産」と「受験戦争を苦にする自殺」が描かれ、第2シリーズでは「教育困難校」がテーマに、第3シリーズでは「生徒の無気力」が描かれることとなった。その中でも、「金八先生と言えば」と言われるのが「第2シリーズ」であった。
これが「伝説」と言われるようになったのは、やはり当時の時代背景を反映し、そこに真っ向から大人がぶつかって解決していくというストーリーがお茶の間に受けたからだと言えるだろう。第2シリーズを象徴する言葉として、「腐ったミカン」というキーワードがある。これは、作中に登場する加藤という不良生徒のことを指す言葉であった。