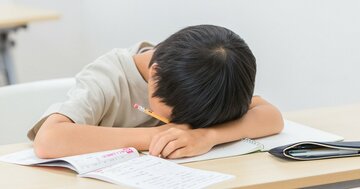そんなハッピーエンドに終わったにも拘らず、この3分程度の短い映像のインパクトは、強烈だった。本当に多くの人の心に、この時代の大人の暴力性が刻まれたワンシーンだったと言っていいだろう。
中島みゆきの歌声が重なる名場面
金八は学園ドラマのテンプレに
金八先生の奮闘も、生徒1人ひとりの純粋な想いも、公権力という圧倒的に大きな力の前には無力になってしまう、ということを表すかのようなシーン。中島みゆきの滔々としているにも拘らず心強い歌声と、それを後押しするようなコーラス合唱。そしてその裏で展開される、無情にして圧倒的な抑圧…。
この当時、体罰も校内暴力も、ある意味では「普通の」ことだった。荒れている学校があるのも「当たり前」として受け入れられ、卒業式のとき、学校に警察が配備されている光景も珍しくなかったという。
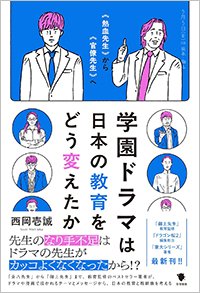 『学園ドラマは日本の教育をどう変えたか “熱血先生”から“官僚先生”へ』(西岡壱誠、笠間書院)
『学園ドラマは日本の教育をどう変えたか “熱血先生”から“官僚先生”へ』(西岡壱誠、笠間書院)
そんな中で、このドラマは「社会が、不良を作り出しているのではないか」というメッセージを、我々に突き付けた。我々が無関心のうちに肯定している「腐ったミカンの方程式」の持つ暴力性が、このシーンによって浮き彫りになり、当時の世相に一石を投じたと言えるのではないだろうか。
後にも先にも、ここまで社会問題の核心に切り込んだドラマは他にはないだろう。「3年B組金八先生」が32年も続く超長寿ドラマになったのは、このワンシーンのインパクトがあったからだと考えられる。
そしてこの時期から、「熱血で、不良のことを見捨てない先生」という存在が、かっこいい存在として憧れられるようになって、コンテンツの中での1つのテンプレートとして描かれるようになる。
後に続く「ごくせん」「ROOKIES」 などの数多くの学園ドラマが、「金八先生的なテンプレート」で作られるようになっていった。