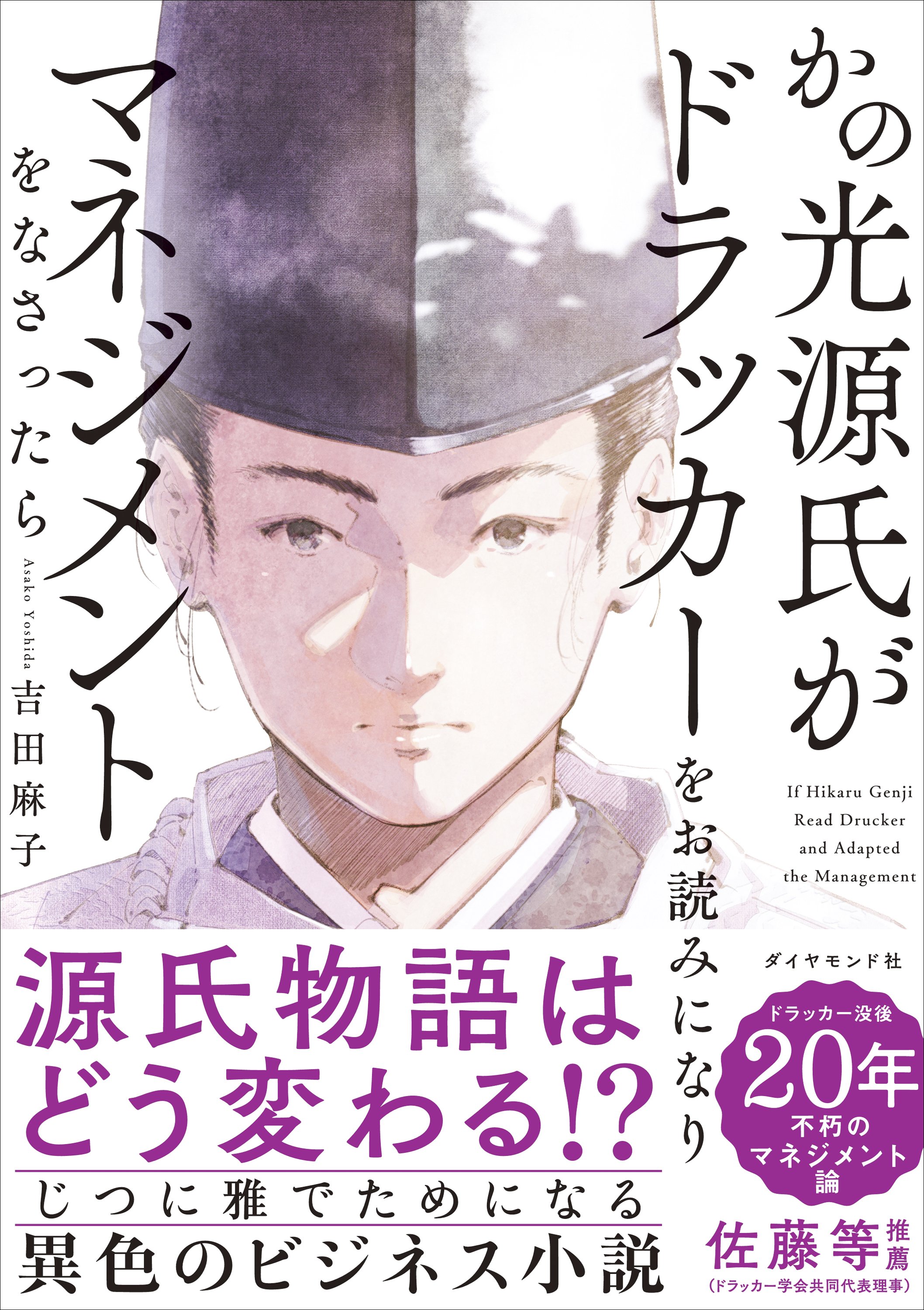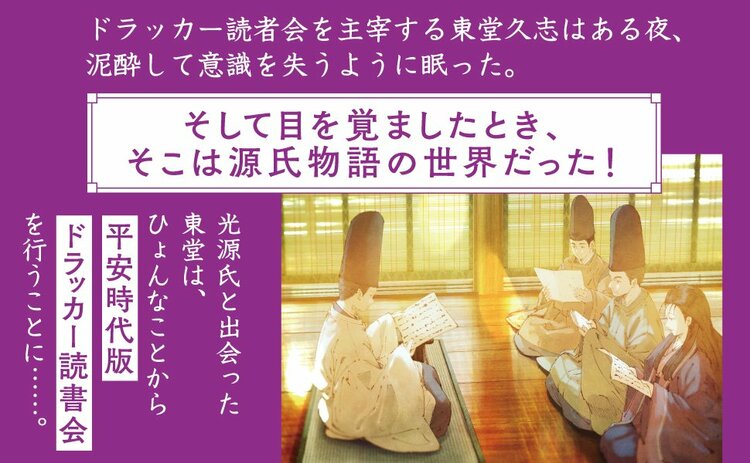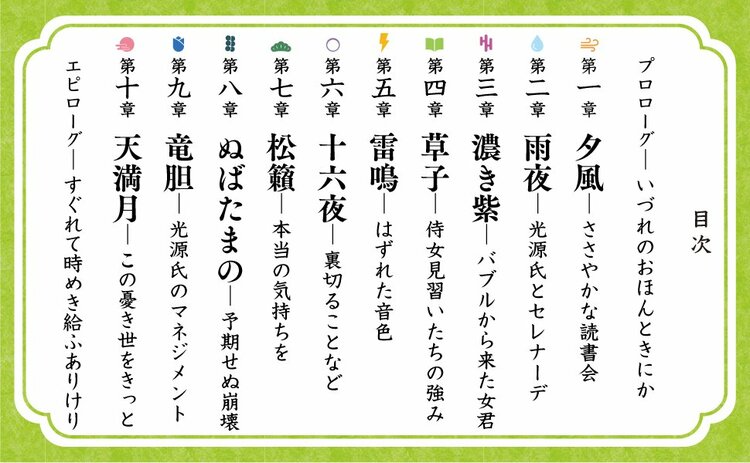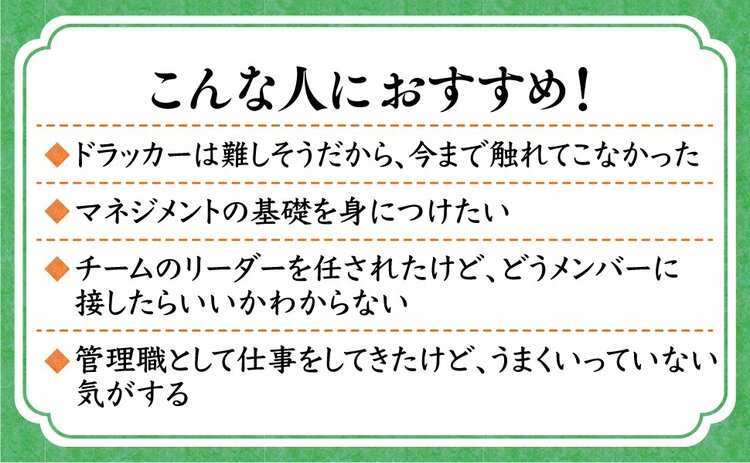「自分で考える部下がほしい」=放任ではない
「自分で考える部下がほしい」という願いは、現代の知識社会において必然的な要求です。
ただしそれは放任を意味するのではなく、マネジャーが「成果と貢献」という基準を常に示すこととセットで成り立ちます。
言い換えれば――
・マネジャーは「指示を出す人」ではなく「方向を示す人」
・部下は「従う人」ではなく「自ら考え、成果を生み出す知識労働者」
この両輪がそろってこそ、組織は成果をあげることができるのではないでしょうか。
採用すべき人を見極める質問
――そのような自ら考え、成果を生み出せる人、そして誠実な人を見極めるための質問はありますか。
ドラッカーは『現代の経営』の中で、こう述べています。
「手だけを雇うことはできない。手の所有者たる人がついてくる」
つまり、人は能力だけを切り離して雇用できるものではなく、全人格的な存在として仕事に関わるのだ、と指摘しています。だからこそ、人の強みをどう生かし、動機づけるかがマネジメントの本質になるのです。
ドラッカーは、企業と働く人の間にはお互いの要求があると整理しています。
・企業の目標に進んで貢献すること
・変化を進んで受け入れること
・仕事ぶりについての高い水準
・仕事の組織とマネジメントに関わる能力の高さ
・優れた仕事に対する明確な関心
この両方が共有されてこそ、健全な雇用関係が成立します。
したがって面接では、学歴やスキルの確認だけでは不十分です。
企業側からも「私たちは何を求め、どんな基準を大切にするのか」を明確に伝えること、そして候補者がその期待にどう応えるかを問う対話が大切です。
例えばこんな質問が考えられます。
「私たちの目標やビジョンに、あなたはどう貢献できますか?」
「これまでに経験した大きな変化に、どう対応しましたか?」
「あなたが仕事において最も高い基準を求めた経験は何ですか?」
「優れた仕事に心から関心を持った瞬間を教えてください」
これらは「誠実さ」や「強みに基づく貢献」を引き出すための問いです。
ドラッカー的にいえば、採用で最も大事なのはスキルの多寡だけではなく 真摯さと貢献意欲 です。
組織の成果に進んで力を尽くす人をどう見出すか。
そしてそのための面接は、企業側からも期待と基準を明確に伝える「対話の場」として設計されるべきであると思われます。
――面接は一方的なものではなく、双方の「対話の場」であるべきなのですね。ありがとうございました。