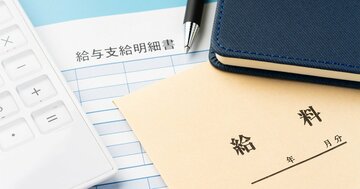写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「ほめて伸ばそう」という文化に、弊害はないのでしょうか?ハラスメントを恐れて、部下に好かれたいからと安直にほめてはいないでしょうか?ミスをした部下とうまくコミュニケーションするには?「ほめる」の功罪を分析することで、人を育ててチームの業績を上げるコツを解説します。(ブレインマークス代表取締役 安東邦彦)
「ほめるだけ」では人は育たない!
本当に部下を伸ばすコミュニケーションとは?
「部下は、ほめて伸ばすべきだ」――こんな風潮が広まってもう何年経ったでしょうか。心理的安全性やハラスメント回避といった観点から、「上意下達の命令型マネジメントは時代遅れ」という認識が浸透し、代わって「ほめることで部下との関係性を良くしよう」という発想が日本社会を埋め尽くそうとしています。
また、ゆとり教育を経験した世代が30代半ばとなり、指導的立場に就くケースが増えているのも、その理由の一つとして考えられます。その世代の人たちは学校で先生に叱られることがあまりなかったため、大人になって人を叱ることを嫌気し、その結果「ほめて指導する」しかなくなっているのではないでしょうか。
確かに、ほめることには一定の効果があります。人は誰しも認められたいという欲求を持っていますし、ポジティブなフィードバックがモチベーションにつながる場面も少なくありません。しかし一方で、「ほめすぎ」による弊害も見逃せないものです。成果がそれほどでもないのに「すごいですね」「よくできました」を連発すると、言葉の重みがなくなるばかりか、相手の自己認識を歪ませてしまう恐れがあります。
特に注意すべきは、相手がその言葉を「本気で」受け取ってしまうことです。上司の側は単なる気遣いやクッション言葉のつもりでも、部下は「自分は評価されている」「十分にやれている」と思い込み、結果として成長意欲が鈍ってしまうケースもあります。自己評価が甘くなり、「もっと頑張ろう」という内発的なモチベーションが生まれにくくなるのです。
上司からほめられることが当たり前になってしまうと、部下の仕事に対する動機が「ほめられるため」に変質してしまいます。「あの上司にほめられるから頑張る」「評価してもらえるからついていく」。こうした他者軸の働き方は、本人の主体性や責任感を育てることにはつながりません。
本来、マネジメントの目的は目標の達成や組織の成長であって、「部下に好かれること」ではありません。では、本当に部下を伸ばし、チームの業績を上げるコミュニケーションとは何でしょうか?