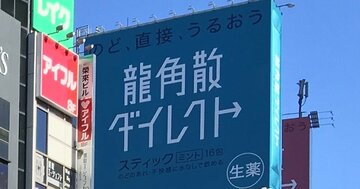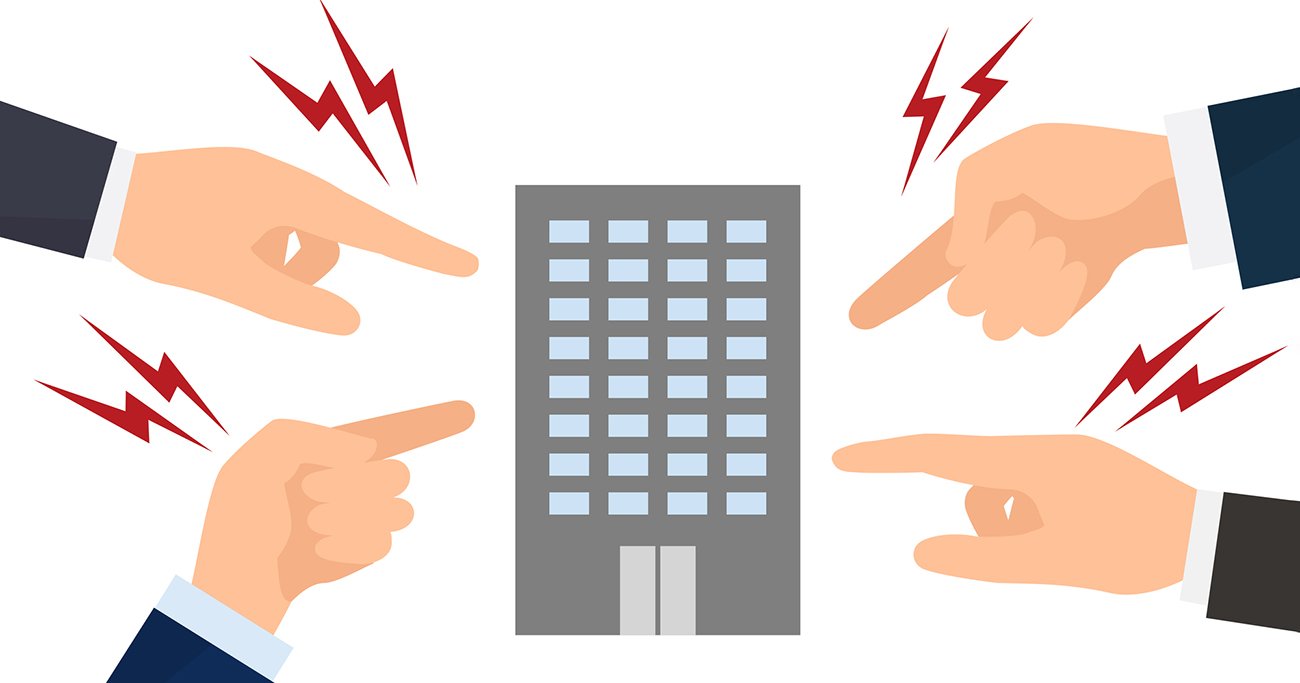 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本取引所グループが7月にまとめた24年度株式分布状況調査によると、日本株における外国法人等の株式保有比率は25年3月末で32.4%と、前年同月末と比べて0.6ポイント増加し、過去最高を記録した。一方で、外国法人等の株式保有金額は前年度末より13兆7045億円減って306兆7705億円となった。海外投資家の投資部門別売買状況では、24年度は4兆8736億円の売越しとなり、売越しは2年ぶりのことだそうだ。一般に、強気で鳴らす外国人投資家の間にも日本株の将来に対する弱気の見方が広がっている兆候かも知れない。
こうしたなかで、引き続き「元気」なのがモノ言う株主の異名で語られるアクティビストの連中である。長年、ボーっと生きてきた日本の上場企業をターゲットに大株主の立場から経営改革を迫る人たち、というのが大方の日本人が抱くイメージだろう。米国政府がかつて日本政府に突き付けていた「年次改革要望書」のように、上から目線でお小言を並べる姿勢に違和感を覚える向きも少なくない。だが、指摘を受けるJTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)のほうも褒められる経営に徹しているわけではないため、判官贔屓の対象とはなりにくい。この間隙をうまく利用して大暴れしているという構図だ。
自ら株式を公開しながら、上場企業の株主対策などを手がけるアイ・アールジャパンホールディングス(HD)によると、日本で活動するアクティビストの数は今年5月時点で74社。10年前に比べて7倍強に増えた。20年前後からは欧米系だけでなくアジア系アクティビストも存在感を増している。こうしたアクティビストによる日本株の投資総額は約9.5兆円に上り、プライム市場の時価総額の約1%に達しているという。
変化は量だけにとどまらない。これまで主流であった株主還元の拡大要求はやや鳴りを潜め、事業ポートフォリオの集中と選択、MBO(経営陣による買収)、スピンオフといった改革や再編にまで口を出しながらさまざまな「出口」を探る方向にチェンジしつつある。