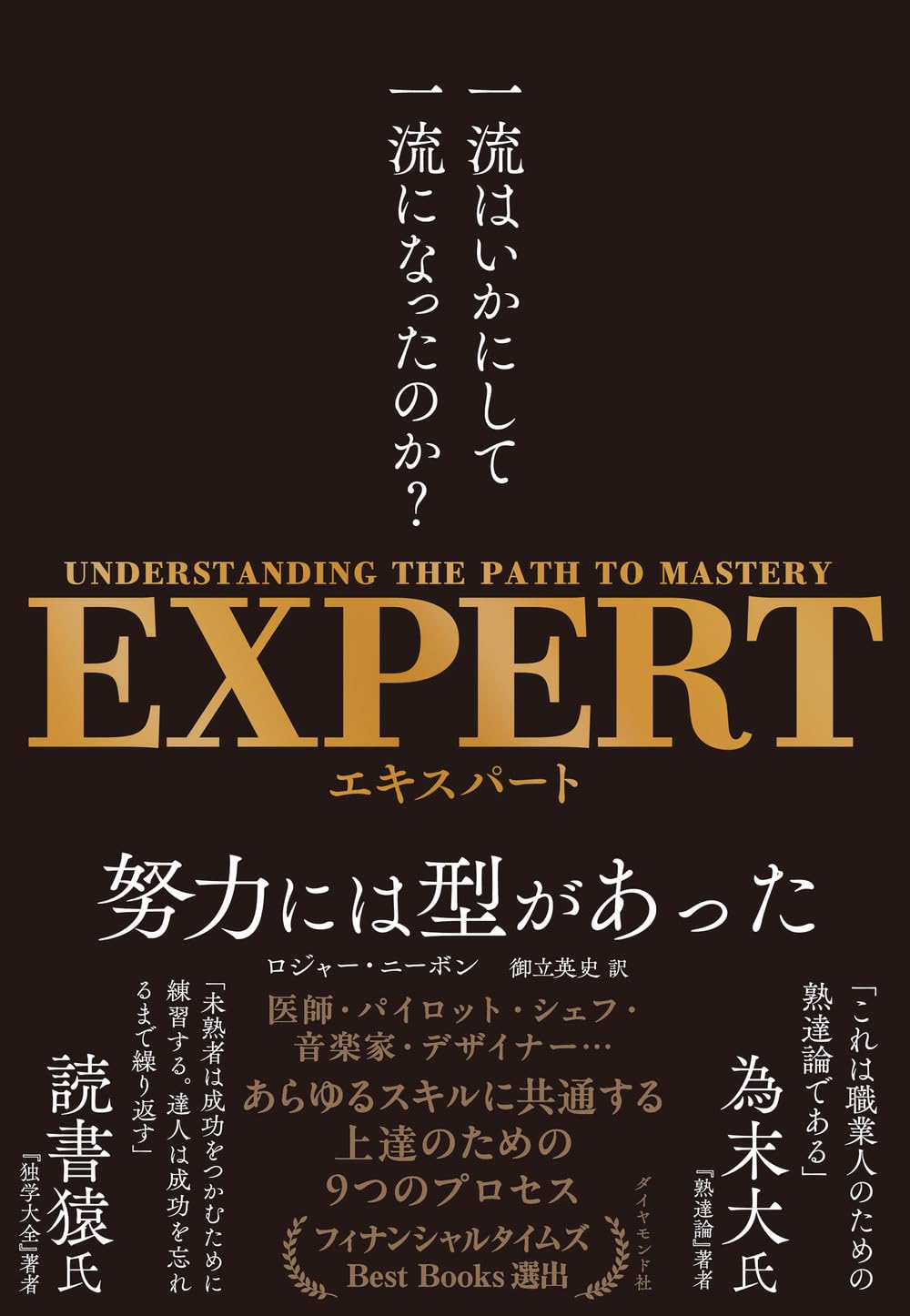見えない過程
達人が行っていることの多くは、じつは当人も自覚していない。達人か達人でないかは、その人が物事をどう見るか、どう解釈するかによって決まる。その人をその人たらしめている内なるプロセスであって、何を作ったか、何を生み出したかで決まるのではない。
達人がどのようにしてその域に到達したのか─私たちはそれを見ることはほとんどない。彼らが作ったものや達成した結果に触れることはあっても、そこに至る過程を見ることはない。コンサートホールでトランペットのソロを聴くことはあっても、完璧な演奏の背後にある何年もの練習を見ることはできない。美術館で名画を見るとき、その絵に至るまでの数え切れない習作の努力を目にすることはない。しかし、達人になりたければ、その長い過程を経なければならない。この本はその過程について述べる。
“技を感じさせないほどの技”
私は達人を達人たらしめるものを解明しようと取り組んできた。彼らがいとも簡単にやってのけること、取り扱う対象に対する深い理解、直感的な判断、物事を知り行動するときの方法、そして予期せぬ事態に対処する能力を言語化しようとしてきた。達人が自身を超える何かに対して示す献身を捉えようとしてきた。
だが、それは容易なことではない。達人であることの真髄は行為によって伝わることであって、言葉で説明できるものではないからだ。その大部分は言葉による説明を受け付けない。達人がやっていることを自分で実際にやってみて、はじめて達人の高みも深みもわかる。「技の存在を感じさせないほどの技」を身につけた存在が達人なのだ。
それについては、よくできた小話がある。暖房システムが故障したため、年季の入ったボイラー技士が修理にやってきた。現場に着いた技士は、依頼人にいくつか質問し、運転音を聴くと、おもむろに作業着のポケットからハンマーを取り出して、配管の一箇所を叩いた。するとシステムは復旧し、技士は帰って行った。要した時間はわずか数分。後日、五〇〇ポンドの請求書が送られてきた。ハンマーで一発叩いただけなのに何という高額請求かと依頼人は怒り、内訳を示せと要求した。配管工はこう答えた。「ハンマー使用料:五ポンド。叩く場所の特定:四九五ポンド」
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)