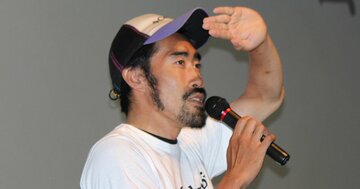告別式で永末さんは、声を振り絞って弔辞を読み上げた。「もっと勉強して君と同じ病気を持つ子供や大人を1人でも多く助けることを誓います。助けてあげられなかったことを許してください」
すべてを背負う一例目があるから
その後の医学が発展する
日本初の手術は何をもたらしたのか。
生命の危機にあった患者を救う緊急の手術だったとはいえ、倫理委の承認を得ていないことが問題視された。健康な人の体にメスを入れていいのか、子供への臓器提供を強要することにつながらないか。学内外で批判や反発が巻き起こった。
「功を焦った」「早く教授になりたかっただけだろう」。心ない声も耳にした。
1995年に島根医科大の教授となり、2003年の島根大との合併後は医学部長にも就いたが、生体肝移植を執刀する機会は2度と訪れなかった。
「倫理委を通さなかったことへの反発が思ったよりも強かった。裕弥ちゃんとの約束を果たせず、悔いが残る」と唇をかむ。
寿美子さんは、裕弥ちゃんの弟に「直弥」と名付けた。木村さんと永末さんの名前の「直」と、裕弥ちゃんの「弥」からとった。
「裕弥の命がつながり、成長を少しでも見られてうれしかった。先生たちへの感謝の気持ちは変わらない」
日本移植学会の江川裕人理事長は「うまくいかなかったことも、すべてを背負う気持ちがなければ1例目はできない。準備中だった他の病院の背中を押し、手術を広めるきっかけになった」と評価する。
裕弥ちゃんの手術をきっかけに国内の生体肝移植は急速に広がった。1990年には京都大学と信州大学が相次いで実施した。
移植は本来、倫理的にも技術的にも脳死からの方が望ましいとされる。97年に臓器移植法が成立したが、脳死移植が劇的には増えない一方、生体肝移植は2021年末に累計で1万件を超えた。
島根県の会社員、森脇寛彬さんは1990年6月、3歳で生体肝移植を受けた。京大で実施された国内4例目だった。子供2人に恵まれ、元気に暮らす。