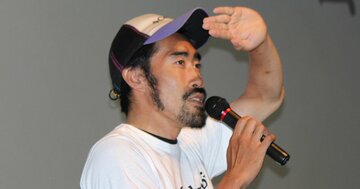九州大学医学部に合格すると、「どんな困難があっても逃げない医師になろう」と決意した。
自分が断れば、裕弥ちゃんの命はない。
「助けてほしいと願う患者と家族に背を向けることはできない」。
超音波検査を施すと、「手術は可能」に思えた。肝移植を決断した。
自信はあった。スウェーデンに2度留学し、肝移植の研究に携わった。広島赤十字病院時代には、肝がん患者から肝臓の一部を切除する手術を約200件執刀した。島根医科大でも動物実験を続けた。
岩国市から島根医科大に戻ると、所属する第二外科の医師らに告げた。
「生体肝移植をやりたい」。
皆が押し黙り、重い空気が流れた。
学内の倫理委員会の承認は得ていなかった。第三者の立場から医療行為の妥当性を審査する倫理委は、一定の時間を要する。
「時間がない。私がすべて責任を取る」と押し切った。
若い医師は言った。「先生は黙っていても教授になれます。失敗すれば、すべてを失いますよ」
決意は揺るがなかった。当時の日本では、68年の札幌医科大学の和田寿郎教授らによる心臓移植以降、腎臓を除き移植医療は途絶えていた。脳死判定への疑義に加え、密室性も批判の対象となり、国民の不信は根強かった。
「誰かが一歩を踏み出さないと、移植医療は進まない」。
そんな思いにも後押しされた。何度も会議を重ね、手術後に最大限の情報を公開すると確認した。
自分の家族には黙っていたが、緊張は伝わっていた。妻の淑子さんは手術当日、子供たちに告げた。
「お父さんは今日、とても難しい手術をします。結果によっては大学を辞めることになります。その時はあなたたちも覚悟を決めなさい」
世紀の手術は成功するも
事態は急展開を迎える
13日午前9時40分、手術が始まった。2回の手術を経た裕弥ちゃんの肝臓は他臓器との癒着が激しく、剥がすのに約4時間を要した。