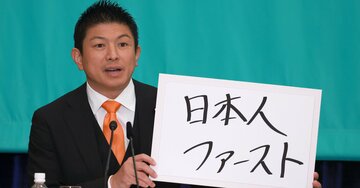ここまで言えばもうおわかりだろう。今後減少していくであろうアジア圏の労働者の代わりに、新しく「安くこき使える外国人労働者」として、アフリカの人々をどしどし迎え入れていこう、というのが日本政府の本当の「狙い」なのだ。
なぜそんなことが断言できるのかというと、「ホームタウン」という名称だ。
あらためて言うまでもなく、これは「故郷」や「生まれ育った街」を意味する。一般的に自治体が国際交流を推進する場合、「フレンドシップタウン」や「パートナーシティ」などになるのが普通だ。政府の釈明では、インターンの受け入れを想定しだからだと言うが、それならば「ホストタウン」が妥当だ。国際交流くらいで「故郷」を連想させるのは明らかに「異常」だ。
では、なぜ「ホームタウン」なんて違和感だらけの言葉を引っ張り出したのか。その答えは歴史を振り返ればわかる。実は日本の政治家や役人が本音を隠して、「移民推進」の旗振りをするときに使うキラーワードこそが「ホームタウン」なのだ。
「満州をホームタウンに」
繰り返される“負の歴史”
今から100年ほど前、日本政府が「移民推進」を国策としてゴリゴリ押ししていた。といっても、外国人を受け入れるのではなく、日本人を移民にしようとしていたのである。
農村での土地不足、失業者の増加を受けて、海外に移り住んで働くように推奨した。厳しい言い方をすれば「口減らし」である。そこで移民先として背中を押していたのが、シンガポール、インドネシアなどのアジア圏、ブラジル、ペルーなどの南米だ。
そして、そんな移民政策の中でも、特に力を入れられたのが「満州」(現在の中国東北地方からロシア沿海地方にかけての地域)だ。
この地は日露戦争によって手に入れた権益だが、現地住民からの激しい抵抗にあって治安もかなり悪化していた。日本政府としては、どんどん日本人を入植させて、現地の“日本勢力”を拡大することによって治安の安定を図り、ソ連に対する防衛体制を築きたかったのである。