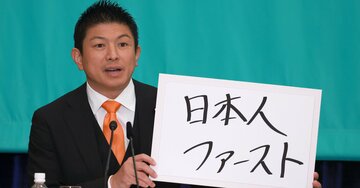そこで1936年、日本国内の農村の中で経済的に苦しい人々を「満蒙開拓団」として満州に入植させて、最終的には100万戸を移住させようという国策が本格的にスタートするのだ。
ただ、いくら貧しくて生活が苦しくても、治安も悪い、敵国とも近い国へと移住しようなどとはなかなか思わない。そういう不安や恐怖をかき消すため、政府が打ち出したのが「ホームタウン」である。
「拓けゆく大陸“第二の故郷”に、沈む村の視察団帰る」(読売新聞1938年11月1日)
このような形で政府はマスコミを用いて「満州=ホームタウン」というイメージを盛んにふれまわったのである。現地の新聞「満洲日日新聞」も1938年3月15日の夕刊で、新潟県が移民奨励計画を推進していることを、「第二の故郷を建設」という見出しで報じている。
日本政府の移民推進プロパガンダは見事成功し、最終的には終戦までに約27万人が満蒙開拓団として満州へ渡っていったのである。(満蒙開拓平和記念館「満蒙開拓のミニ知識」)
もちろん、この「ホームタウン」はイメージ戦略だけにとどまらない。当時の政府は農民以外の移民も呼び込むため、満州に実際に「ホームタウン」をいくつもつくったのである。
その代表が「東京村」だ。
これは満州国の首都・新京特別市の近郊にあった、東京商工会議所が建設した200戸ほどの村だ。そう聞くと「民間事業」のように誤解するだろうが、入植者には政府からは補助金、満州拓殖公司(満州開拓のための国策特別会社)から融資金などの特典があった。つまり、「東京村」というのは、日本政府が満州に多くの移民を呼び込むためにつくった「ホームタウン」なのだ。
ここまで言えば筆者が何を言わんとしていたか、わかっていただけたのではないか。
日本政府は、はるか昔から移民推進をする際には「故郷=ホームタウン」というキラーワードを多用してきた。こういう国家の“癖”というか、役人根性というのは世代を超えて引き継がれるものだ。