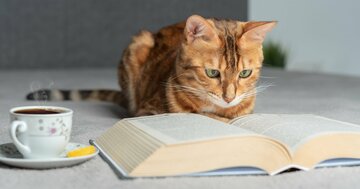ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。本記事では、著者であり、生物学の専門家である更科功氏にインタビューを実施。ダーウィンの進化論を説明するためによく使われるイメージイラストの間違いについて伺った(取材・構成:小川晶子)。
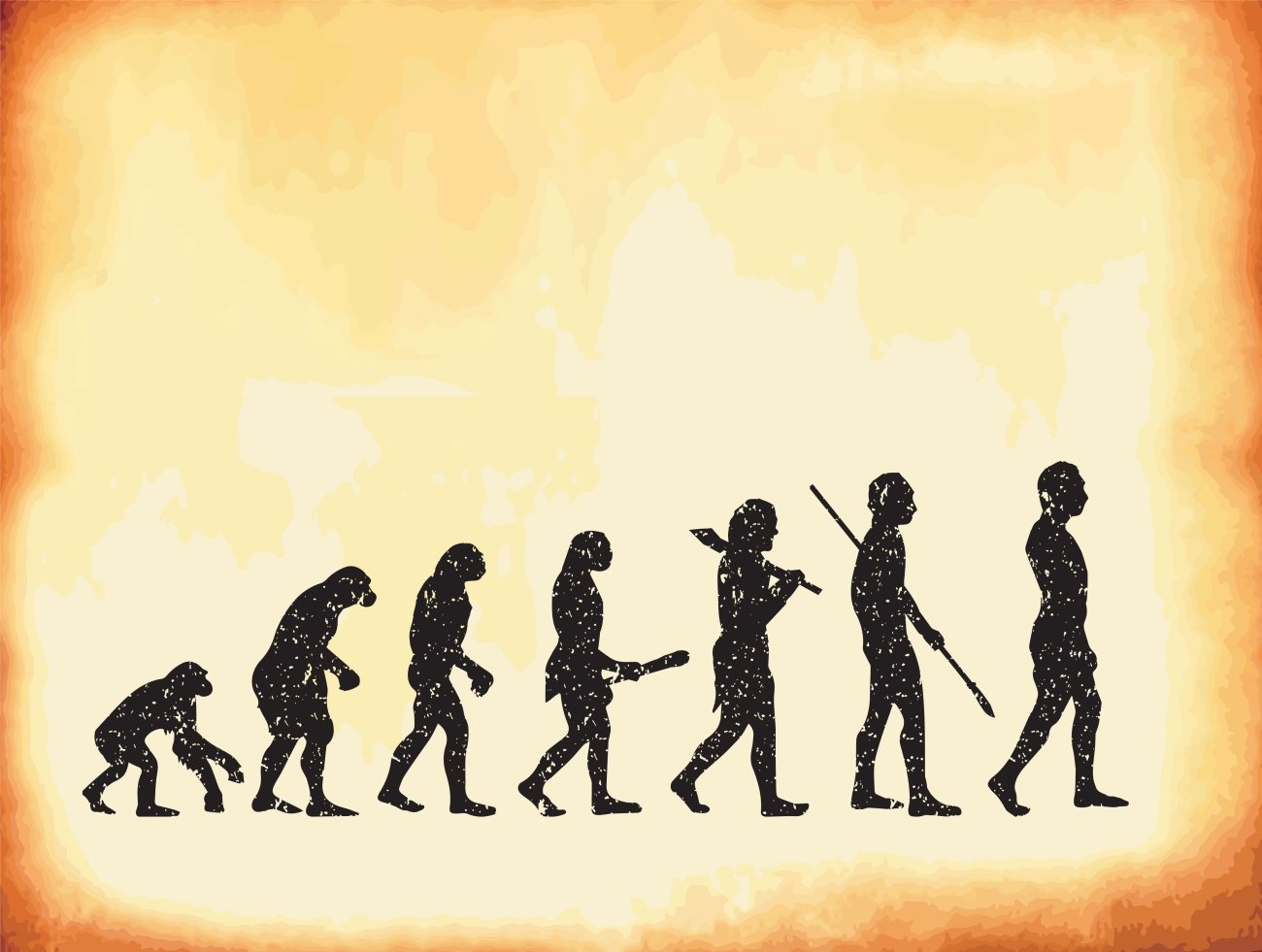 ※記事内で言及されている典型的な進化論のイメージ Photo: Adobe Stock
※記事内で言及されている典型的な進化論のイメージ Photo: Adobe Stock
進化論イラストの間違い
――更科先生は『「種の起源」を読んだふりができる本』の中で、「かなりの数の記事が、『種の起源』についてとんちんかんなことを述べている」とおっしゃっています。実は多くの人が『種の起源』を読まずに、いろいろ言っていると。「進化論」と言えば、四足歩行のサルが徐々にヒトに進化するイメージイラストが思い浮かびますが、あれは誤解に基づいているのでしょうか?
更科功氏(以下、更科):そうですね。進化生物学の研究者からすると大変よろしくないイメージイラストなので、これまで何度も出版社の方に「あのイラストは使わないでください」とお願いしてきました。
――どういう点が間違っているのでしょうか?
更科:2つの側面で間違っています。まず事実として間違っているのは、中腰のサルが描かれていること。腰が曲がってヨタヨタしたサルが生きていけるわけがありませんからね。
四つ足で素早く移動するか、直立二足歩行かどちらかです。2019年に、直立二足歩行をしていた類人猿の化石が見つかりました。直立二足歩行は木の上で始まったと考えられています。
赤ちゃんが立ち上がるときも、最初は何かにつかまって立ちますよね? 類人猿も何もないところで突然立ち上がるはずがなく、木の枝につかまって直立するようになったと思われます。
かつて直立二足歩行の類人猿が何種かいて、その中の一種がヒトになったのでしょう。四足歩行と直立二足歩行の、中間の姿勢の類人猿の化石は見つかっていません。腰の曲がった個体はいたかもしれませんが、種としては存在していなかったのではないでしょうか。
進化は進歩ではない
――もう一つの側面での間違いとは何ですか?
更科:サルがヒトに向かって一方向に進歩していくというイメージを喚起する点です。進化は進歩ではないので、そういう意味でもよろしくない。研究者は使わないイラストです。
でも、大人気なんですよねぇ。あんなにはっきりと間違っているのに、あまりにも有名になってしまったから……。
――進化論のイメージイラストを描くとしたら、ダーウィンが『種の起源』の中に唯一入れたという図のように、種が分岐していくようなものがいいのでしょうか?
更科:そうですね。まぁ、あのイラストでなければ何でもいいです(笑)。
進化論を認めたくなかった理由
――ダーウィンは『種の起源』の中で、ヒトがサルから進化したのだと名言しているわけではないんですよね。当時は神様が人間を創ったと考えられていたので、そんなことを言ったら大変な批判を浴びそうです。
更科:人間も進化の産物だということは述べていますが、具体的に何から進化したのかは明言しませんでした。でも、『種の起源』を読めば当然、人間はサルの仲間から進化したとわかります。
毛むくじゃらのサルの顔がダーウィンになっているという風刺画がありますよね。あれはダーウィンを批判する意図で描かれていますが、むしろ正しい理解を示しています。
19世紀のイギリスでダーウィンの進化論を認めたくなかった人たちは、生物が進化するのが嫌だったわけではなく、人間がサルから進化したことをどうしても受け入れられなかったんでしょう。
いろいろな文献を見ると、表向きはいろいろな理屈をつけて進化論に反対していますが、本音はそこだと思います。サルから進化したという考えが我慢ならなかったのです。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』に関連した書き下ろしです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。