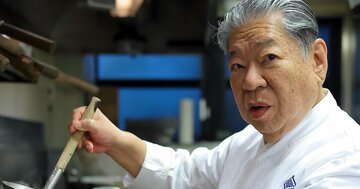タコの産地は各地にありますが「エラがここまでの大きさになるのは、10キロ以上になる北海道のミズダコだけ」と小林社長。
日本海、オホーツク海、宗谷海峡の織りなす環境がタコを育み、魚介の宝庫にしています。
琵琶湖の保存食は
お茶漬けにして
伝統的な乳酸発酵食の琵琶湖名物「鮒鮨」。フナをご飯と塩で発酵させる、古来伝わる保存食「熟鮨」のため、食べなれない人が料理店で注文するのは少々ハードル高めかもしれません。でもじつは、地域のスーパーで少量を気軽に買えるのです。
 同書より転載
同書より転載
1905(明治38)年創業、琵琶湖の魚を扱う専門店の魚三のふなずしは昔ながらの製法にこだわります。2~5月に琵琶湖で捕れる貴重な天然子持ちニゴロブナを地元漁師から生きたまま仕入れ、新鮮なうちに塩漬けします。
夏の土用前には近江産の米を炊き、フナの頭やエラにご飯を詰め込む飯漬け作業に。たるの中の様子を見ながら、半年から1年発酵させたものが、ふなずしです。
そのまま食べたり、お茶漬けにしたり。深いうまみと酸味と塩気は濃厚なチーズを知る現代人の口に意外に合います。
「大パックに入る尾頭は椀に入れ、湯を注いで吸い物にしても美味」と魚三。パック内のご飯は身と一緒につまむのが通で、低価格の卵のないオスを好むそうです。
噛めば噛むほど
おいしい栄養食
グロテスクな姿のためか、食用とする地域が少ない魚、ウツボ。じつは淡泊な味わいで栄養価も高く、昔から四国周辺および南紀(三重・和歌山の南部)で「滋養強壮」に役立つ魚として食べられてきました。
 同書より転載
同書より転載
和歌山県の南紀では、ウツボの干物が郷土食のひとつでしたが、新たな定番が加わったのはおよそ70年前のこと。桝悦商店の「うつぼ揚煮」です。
カリッとした表面ながら、弾力のある身と甘辛い味付けで、スルメのように噛めば噛むほどじんわりと口に広がるうまみは、酒のさかなに最適。あと引く味は「初代が苦労して考案した秘伝の味」と4代目の桝田義治さん。