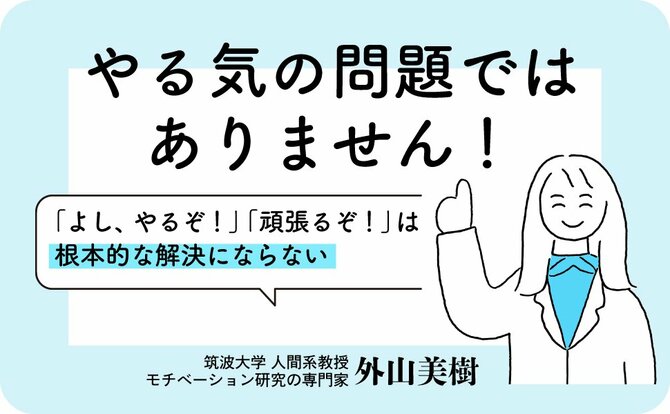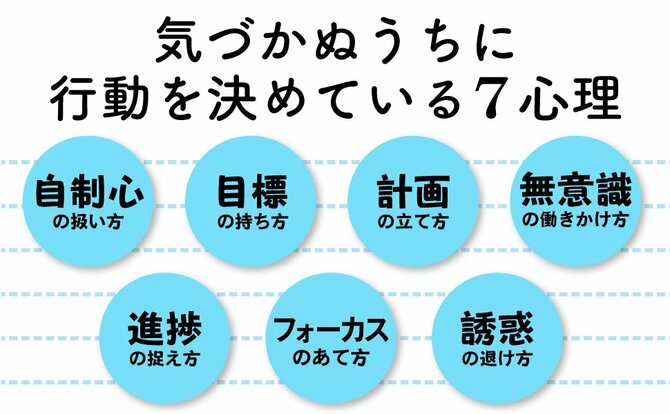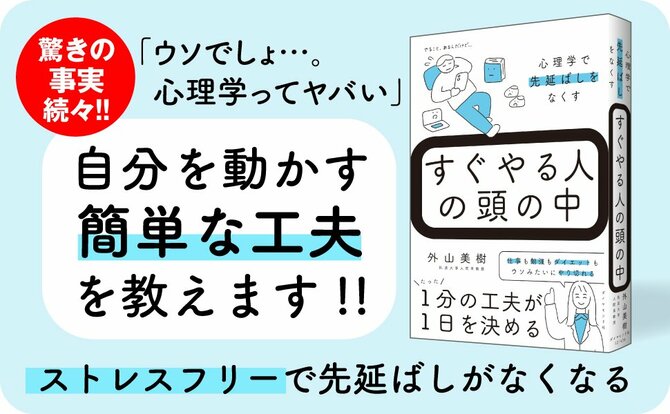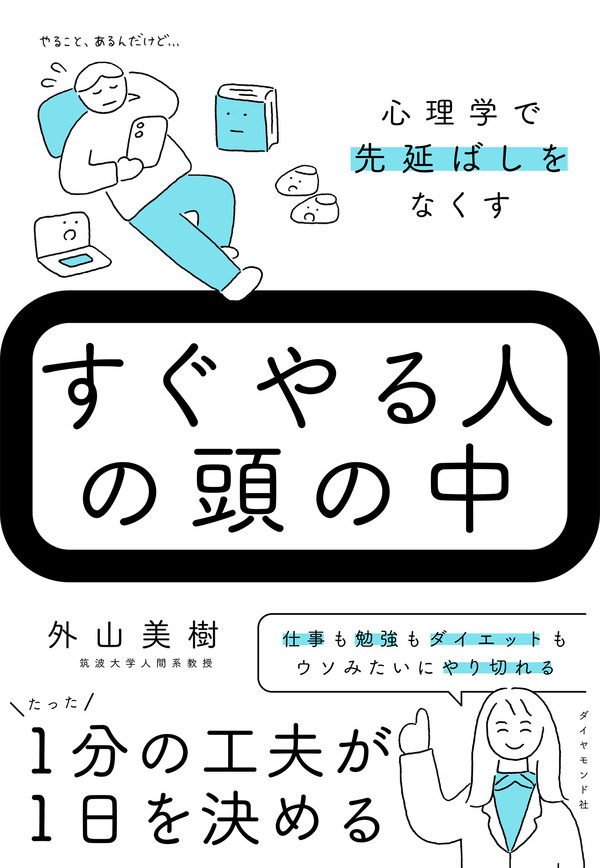試験がある時、「良い成績を取りたい」と思うタイプと、「悪い成績を取りたくない」と思うタイプがいる。どちらも、試験に向けて一生懸命に努力をしているが、そのためのアプローチが異なるという。「たいていはどちらかの思考を好み、それが日々の選択、感情、行動に影響を及ぼす」と語るのは、モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏だ。この思考の傾向をうまく活用すれば、目標達成がしやすくなるのだそうだ。本記事では外山氏の著書『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』をもとに、自分のタイプを見極め、状況に応じた心理的作戦によって物事を達成する方法を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
獲得型と防御型、2つの思考のタイプ
学生時代、あなたは試験勉強をするときに「良い成績を取りたい」と思っていただろうか。それとも「悪い成績を取りたくない」と思って勉強していただろうか。
どちらも「試験に向けて努力する」のは同じだが、アプローチが異なるのだそうだ。
投資家も同様です。利益は高いけれどリスク(損失)も高い運用を好む投資家もいれば、利益は高くはないけれどリスク(損失)も高くない運用を好む投資家もいます。(P.214-215)
心理学者のヒギンズは、これらの違いは「『フォーカス(焦点)』の違いによる」と語っている。
彼は、前者を「獲得型」、後者を「防御型」の思考と呼ぶ。
防御へのフォーカスは、安全と危険に注目します。それは責任や義務を果たすことであり、すでにもっているものを失わないことです。損失を回避することにフォーカスしています。(P.214)
このように、同じ目標を目指しているように見えても、獲得型と防御型のどちらの思考にフォーカスしているかで、大きな違いが生じるのだ。
思考の傾向が行動を左右する
獲得型と防御型、これはどちらが優れているという類のものではない。それぞれ良いところと悪いところがあり、誰しも両方の思考を持っている。
ただ、たいていの場合はどちらかの思考を好み、それが日々の選択、感情、行動に影響を及ぼすという。
外山氏は「自分がどちらのタイプか把握し、自分に合った心理作戦を用いる必要がある」と指摘する。
【獲得型】理想として叶えたいと願っている目標を追求しているので、それが叶うと強い快感情(喜び、意気揚々、幸福感)を覚え、達成できない場合は落胆の感情を覚える。
【防御型】果たさねばならない責任としての目標を追求しているので、それが叶わなかった時には、強い不快感情(不安やパニック、脅威)を覚え、達成できた時には、安堵する。
環境次第で変わる“フォーカス”
人それぞれ、獲得型と防御型どちらかの傾向はあるものの、「人は両方の思考を持っているため、置かれた状況によっては、自分が日頃使っているフォーカスとは異なるほうが顔を出すこともある」と外山氏は語る。
たとえば、「ミスを避けよう」と考える職場の雰囲気であれば、あなたが普段は獲得型であったとしても、防御型にフォーカスしやすくなる。
逆に「失敗を恐れず、アイデアをどんどん出して提案する」ことを要求される職場であれば、普段防御型であっても、獲得型にフォーカスしやすくなるのだ。
つまり、環境に応じて自然とフォーカスを切り替えることで、その場に適した成果を得ることにつながるのだ。
そのため、外山氏は「今、身を置いている環境によって獲得と防御のどちらが優勢になるのかが異なるため、これをうまく使わない手はありません」と提案する。
そこで、たとえばスピードを必要とする課題を行う場合は、意図的に獲得へフォーカスし、正確性を必要とする課題を行う場合は、意図的に防御へフォーカスしたほうが効果的ということになるでしょう。(P.245)
心理的作戦を使い分けて成果につなげる
ある研究では、禁煙と減量という目標に対して、獲得型の人は最初の半年間での成功率が高く、防御型の人は、その後の1年間での維持率が高いことが示されている。
これらのことから、まずは自分がどちらの思考の傾向が強いかを把握し、そして、その局面にあったアプローチはどちらであるかを見極めて、心理的作戦を使い分けると成功率が上がると言える。
「私は失敗するのが嫌だから、着実にできるこの方法でやってみよう」などと考えながら、自分のしたいことや目標に着手すれば、より効果的になるだろう。
自分が獲得型か防御型かを知ることは、目標達成の第一歩だ。
過去の経験を振り返り、自分の傾向を理解したうえで、状況に応じてアプローチを切り替えてみてほしい。そうすれば、あなたの努力はより確かな成果につながるだろう。