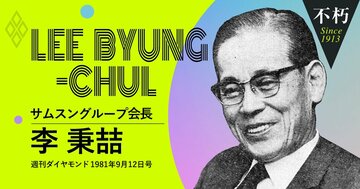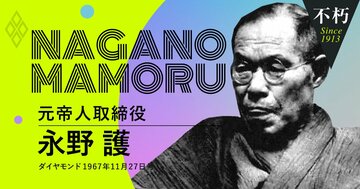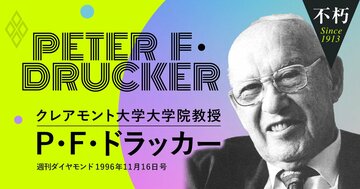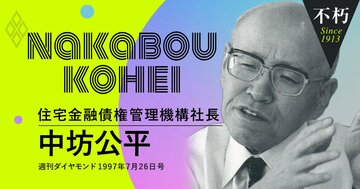住友化学工業の社長・会長を務めた長谷川周重(1907年8月8日~1998年1月3日)。生家は加賀前田藩に勤めた家老の一門で、父は旧制熊本五高(現熊本大学)の教授だ。教育者の家庭に生まれ、府立一中(現東京都立日比谷高校)、旧制一高(現東京大学教養学部など)から東京帝国大学法学部政治学科を卒業して住友合資会社に進んだエリートである。若い頃から西洋文明の二大源泉であるキリスト教とギリシャ哲学に傾倒し、カトリックのキリスト教徒ともなった。
こうした経歴から財界きっての論客として知られ、とりわけ西洋社会の考え方や欧米企業の経営観について多くの発言がある。1985年刊の自著『大いなる摂理』でも、日本企業、経営者、ビジネスマンは国際社会の一員としていかに行動すべきかを大きなテーマに据えている。そもそも石油化学の基幹原料であるナフサは国内ではほとんど産出されないため、中東などから輸入した原油を精製するしかない。いやが応でも国際化の波に翻弄される産業でもあった。
1967年10月ダイヤモンド臨時増刊『これが日本の経営者だ』の「日本の経営者は国際レベルか」という特集の中で、長谷川がインタビューに答えている。60年代半ばから始まった資本自由化・外資参入のうねりの中で、日本企業は国際市場で戦えるかが経済界の大きな関心となっていた頃だ。
記事のタイトルは「“西欧的な”経済社会待望論」。国際競争が激化する中、日本企業や経営者は従来の「甘え」や義理人情の発想を捨て、国際社会のルールにのっとった行動と正しい知識を身に付ける必要があるというのが、長谷川の一貫した持論だった。
インタビューでは「自分本位で、過当競争に負ければ、誰かが助ける。これではいけない」と訴えている。高度経済成長を支えた行政による“護送船団方式”を、甘えであると一刀両断するのである。これに対し欧米では、失敗すれば経営者も失職し社会的に葬られるという厳しい現実があり、「分不相応なことをすれば経済的な罰を受ける」と話す。日本の経済社会はそうした厳しさを受け入れられるかと、資本自由化を前に懸念を表明している。74年に長谷川は経団連副会長に就任するが、一貫して保護主義を批判し、自由化推進を唱え続けた。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
こうした経歴から財界きっての論客として知られ、とりわけ西洋社会の考え方や欧米企業の経営観について多くの発言がある。1985年刊の自著『大いなる摂理』でも、日本企業、経営者、ビジネスマンは国際社会の一員としていかに行動すべきかを大きなテーマに据えている。そもそも石油化学の基幹原料であるナフサは国内ではほとんど産出されないため、中東などから輸入した原油を精製するしかない。いやが応でも国際化の波に翻弄される産業でもあった。
1967年10月ダイヤモンド臨時増刊『これが日本の経営者だ』の「日本の経営者は国際レベルか」という特集の中で、長谷川がインタビューに答えている。60年代半ばから始まった資本自由化・外資参入のうねりの中で、日本企業は国際市場で戦えるかが経済界の大きな関心となっていた頃だ。
記事のタイトルは「“西欧的な”経済社会待望論」。国際競争が激化する中、日本企業や経営者は従来の「甘え」や義理人情の発想を捨て、国際社会のルールにのっとった行動と正しい知識を身に付ける必要があるというのが、長谷川の一貫した持論だった。
インタビューでは「自分本位で、過当競争に負ければ、誰かが助ける。これではいけない」と訴えている。高度経済成長を支えた行政による“護送船団方式”を、甘えであると一刀両断するのである。これに対し欧米では、失敗すれば経営者も失職し社会的に葬られるという厳しい現実があり、「分不相応なことをすれば経済的な罰を受ける」と話す。日本の経済社会はそうした厳しさを受け入れられるかと、資本自由化を前に懸念を表明している。74年に長谷川は経団連副会長に就任するが、一貫して保護主義を批判し、自由化推進を唱え続けた。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
繁栄する外国の化学会社
日本は過当競争でもうかっていない
――今回は、国際化時代に臨み、日頃思っていられることを、お伺いしたい。最近の海外視察は、6~7月の木川田ミッション(編集部注:当時の経済同友会・木川田一隆代表幹事の下で行われた欧州における米国資本の進出状況に関する調査)のときでしたか。
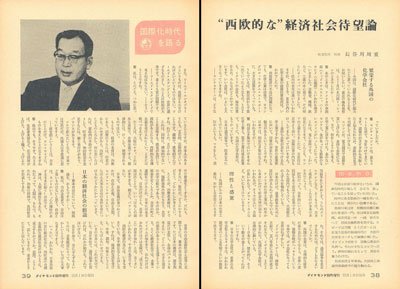 1967年10月1日号より
1967年10月1日号より
あのときは、米国のミッドウエスト(中西部)、ハートランド(心臓部)といわれる地方へ行きました。自動車、機械、鉄など工業の中心地です。その帰りに欧州へ回りました。
――欧州の景気は悪いといわれますが、英ICI(インペリアル・ケミカル・インダストリーズ)や、EEC(European Economic Community:欧州経済共同体)内の化学工業の設備投資状況は、いかがでしたか。
西ドイツ経済の不況が問題になっても、化学工業は活発で、オランダのロッテルダム・ユーロポートに、大きな設備を造っている。
うちでいえば、新居浜(愛媛県)から千葉へ出ていったようなもの。ICIも、イタリアの会社も、海外投資を含め、みんながどこかでやっています。いい会社は、いよいよ大きくなっていきますね。