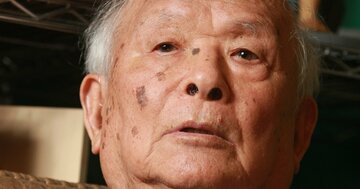(c)楳図かずお 拡大画像表示
(c)楳図かずお 拡大画像表示
「形の怖さ」が一番怖いと僕は思っていますが、そこには問題もあって、出てきた最初は異様だけれど、慣れちゃったら怖くなくなるんです。「心理的な怖さ」の方が難しくて複雑です。見かけは怖くない人が、実はすごく怖いことを考えているかもしれない。「漂流教室」(1972年)の関谷(編集部注/給食のおじさんで、大人で唯一生き残った登場人物)みたいに、最初おとなしかった人が、急に凶暴になると怖いでしょう。ある意味、仕掛けなんですけどね。
主人公は、名前こそおろちですが、へび女的なところはありません。不老不死の美少女で、常に一歩引いて人間社会を観察する傍観者です。よく彼女の正体について聞かれますが、「何も考えていない」というのが正直な答えです。右手首に包帯を巻いたのは、「アキレスのかかと」のような弱点を作った方が面白いかなと思ったからです。あまり深くは考えていません。
楳図ホラーは
怖いだけではない
前々年の1967年に描いた「猫目小僧」の第1話で不死身の男を描きました(「恐怖の再生人間」)。70年に「ビッグコミック」に連載する「イアラ」も歴史の中をずっと生き続ける人間の話です。この頃、「不死身」で何か新しいことができそうだと考えていたようです。
誰かのことを、生まれてから、死ぬまでずっと見続けるためには、自分が不死身でないといけない。そういう話は新しいと思ったんですね。いつも咄嗟に思いつくんですけどね。
――「おろち」は、楳図ホラーが怖いだけではないことを証明する傑作シリーズとなった。第2話「骨」は、愛する夫を事故で失い、嘆き悲しむ妻のため、おろちが自分の「力」を使おうとする。夫は墓場からよみがえるが、妻は喜ぶどころか、なぜか恐れおののく……。過去に描いた短編「愛の奇蹟」を完全に裏返し、ショッキングな結末に仕上げた。さらに新境地と言えるのが、第3話「秀才」だ。