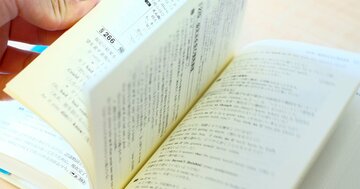国連総会で演説するトランプ米大統領 Photo:picture alliance/gettyimages
国連総会で演説するトランプ米大統領 Photo:picture alliance/gettyimages
トランプ米大統領が国連で前代未聞のスピーチを行い、物議を醸しています。「国連は機能していない」「不法移民をサポートしている」「気候変動は史上最大の詐欺」などと国連への批判を繰り返したのです。その真意は何だったのでしょうか?スピーチに出てくるキーワードをランキング化して分析すると、「米国ファースト」以上にクセの強い思想が浮き彫りになりました。英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。(トライズ 三木雄信)
異例のトランプ演説を「頻出語ランキング」で分析
トランプ米大統領が、ニューヨークの国連総会で行った演説が話題です。その内容を最初にざっくりまとめると、自らの成果で「米国は黄金時代を迎えた」と自画自賛する一方、紛争や移民問題、地球温暖化に関しては国連や欧州を繰り返し批判しました。
「米国が関与したことで7つの戦争を終わらせることができた」「周りの人々は私がノーベル平和賞を7回、受け取るべきだと言っている」などとアピールする一方、「国連の役割は?」などと批判。続けて、「不法移民は国連が住居や食料などをサポートして悪化させている」「地球温暖化はウソだ」「パリ協定もいかさまだ」などと攻撃的な口調を続けました。そして場違いにも、自国内の政治や経済に言及していくのです。
演説の要旨を日本語で知った読者も多いと思いますが、ウェブ上に動画が残っているので、ぜひ視聴してみてほしいです。国連演説で約1時間も1人でしゃべり続けるのも異例でしたが、繰り返された単語と、あえて語らなかった単語を分析すると、トランプ氏の頭の中が「アメリカ・ファースト」を超えて「アメリカ・オンリー」とも言える世界観であることが分かってきます。
そのクセの強い思想は、スピーチ開始直後、worldとpeaceを強調したことから始まっていました。
“Six years have passed since I last stood in this grand hall and addressed a world that was prosperous and at peace.”
(私が最後にこの場に立ち、繁栄し平和な世界に語りかけてから6年がたちました)
この直後に語られたのは、国連という舞台で語るべき世界の変化ではなく、「米国が直面した危機」でした。この点からも、実は最初から「世界」という言葉を、米国の立場を際立たせるための背景として、トランプ氏が利用しているのが分かります。
今回のトランプ演説は、言葉の使い方が本当に特徴的でした。そこで、スピーチに出てくる単語の頻度をランキング化し、さらに「共起語(きょうきご)」も併せて分析しました。
共起語とは、ワンセンテンス内のキーワードに近い位置で繰り返し登場する別の単語を指します。「セット語」「第2ワード」などと考えると分かりやすいでしょう。「どの言葉が結びついて文章を構成しているか」を分析すると、話し手の意図や、聞き手にどのような印象を残そうとしているのかが浮かび上がってくるのです。