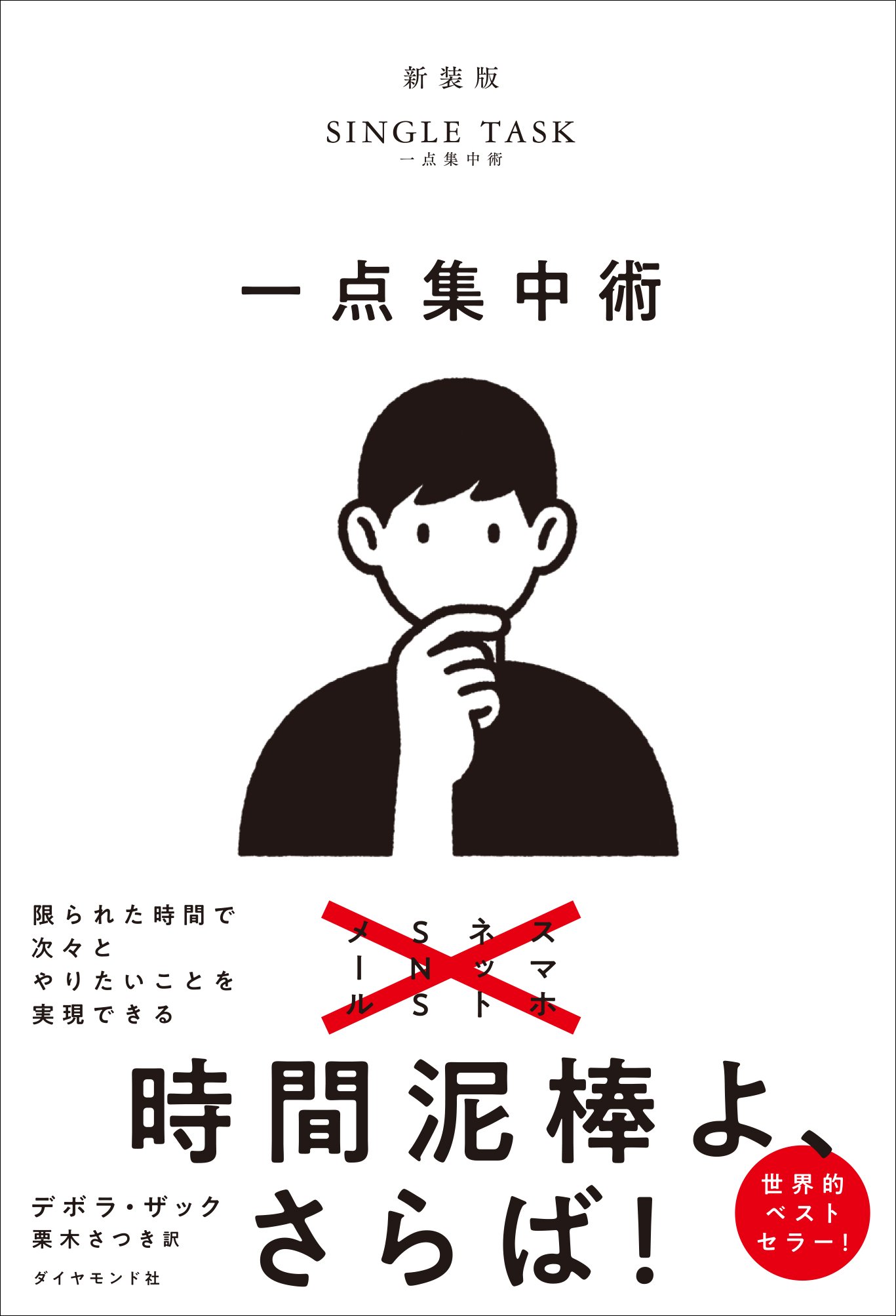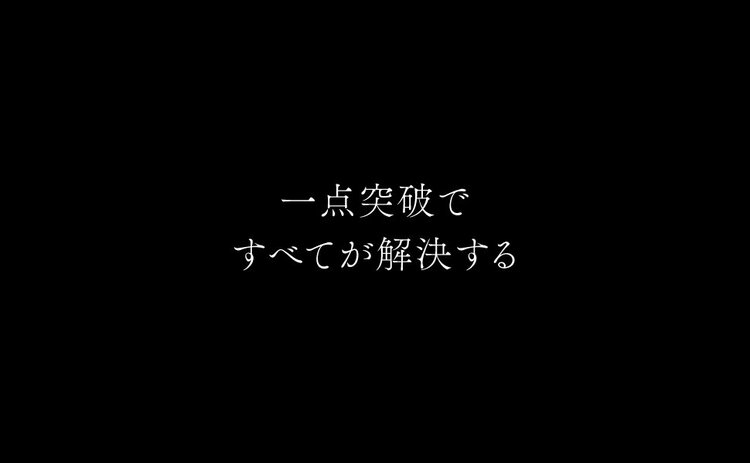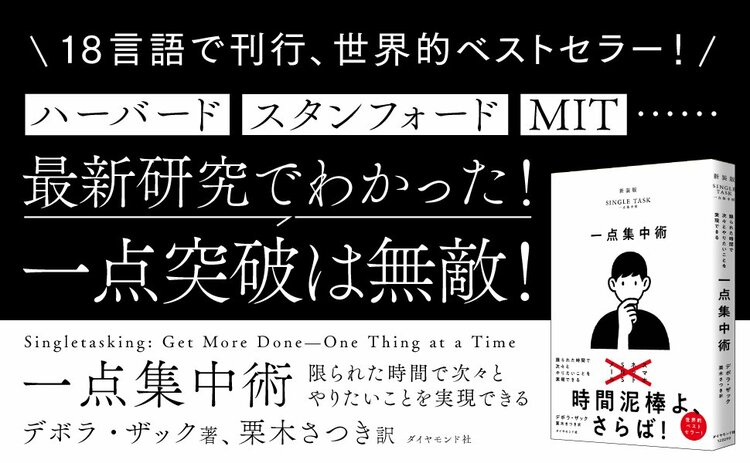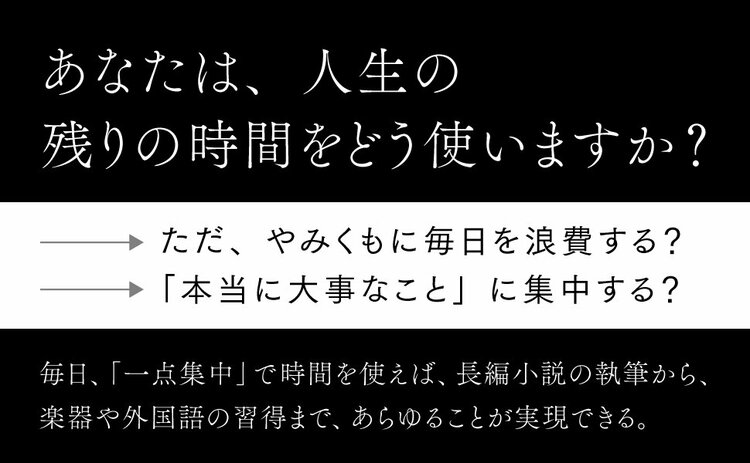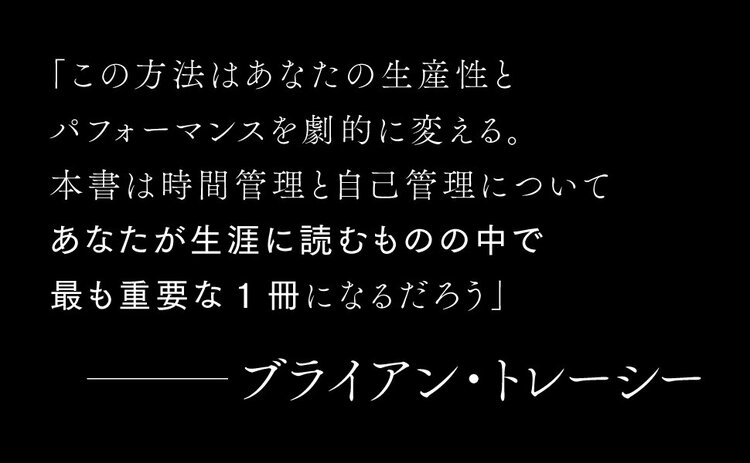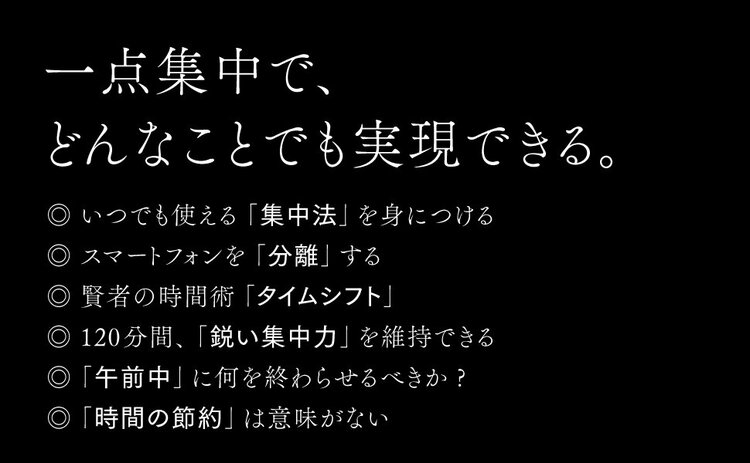スマホ、ネット、SNS……気が散るものだらけの世界で「本当にやりたいこと」を実現するには? タスクからタスクへと次々と飛び回っては結局何もできない毎日をやめて、「一度に1つの作業」を徹底する「一点集中」の世界へ。18言語で話題の世界的ロングセラーの新装版『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』。その刊行を記念して、訳者の栗木さつき氏に話をうかがった。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「マルチタスク」をしてはいけない
――本書では、マルチタスクを避けてシングルタスクに徹することの重要性が繰り返し説かれています。栗木さんはマルチタスカーの自覚はありますか?
栗木さつき氏(以下、栗木):いいえ、自分自身はマルチタスカーだという意識はありません。もちろん、自然と気が散ってしまうこと自体は多いですが、同時に複数のことができるというタイプではないです。
また、この本を訳すことで「一点集中」の重要性を再確認しました。仕事中にラジオや音楽を聴くことはありますが、本書でも、「意識的な努力を必要としないこと」を同時にするのは問題ないと書かれています。
ただし、集中力を要することは、決して同時にしてはいけないと書かれていますね。
その結果、注意散漫な生活に歯止めがきかなくなっている。集中力がなくなり、ストレスがたまり、目の前の作業とは何の関係もないことでヤキモキする。おまけにそうすることで、いま目の前にいる人たち――同僚、顧客、店員、社員、仲間、家族――に無礼をはたらいているのだ。
注意散漫の状態を続けていると、結局のところ、何の成果もあげられないうえ、対人関係まで壊しかねない。――『一点集中術』より
タスクからタスクに切り替えているだけ
――世の中では、複数のことを同時にこなせるマルチタスカーのほうがえらいみたいな風潮がありますよね。
栗木:はい。でも、著者のデボラさんは、そもそもマルチスクというものは存在しないと言っています。
スタンフォード大学の神経科学者エヤル・オフィル博士は「人間はじつのところマルチタスクなどしていない。タスク・スイッチング(タスクの切り替え)をしているだけだ。タスクからタスクへとすばやく切り替えているだけである」と、説明している。
こうした行動を続けているとマルチタスクをしているような気分にはなるものの、現実には、脳は一度に2つ以上のことに集中できない。――『一点集中術』より
脳科学の観点では、人は同時に複数のことに注意を向けることができない。「マルチタスクが得意」と感じるのは錯覚で、実際はタスクを高速で切り替えているだけ。その切り替えのたびに脳が疲弊し、パフォーマンスが落ちてしまうという。
――毎日に「一点集中」を取り入れることで、どんなメリットが得られると思いますか?
栗木:日常の行動一つひとつに意識を向けるようになると、時間の使い方が自然と変わってきます。
たとえば仕事の日でも休みの日でも、「いま何を優先するか」を意識的に選ぶだけで、1日の流れが大きく違ってきます。そうした意識がなければ、気づけばあっという間に時間が溶けてしまい、何も残らなかったということになりかねません。
シングルタスクは、仕事だけでなく、充実した人生を送るために「必需品」なのだと著者は言っています。
目の前のタスクに一つずつ集中すれば、効率が上がって睡眠などリフレッシュの時間が増えるし、リフレッシュの時間が増えると、もっと集中してシングルタスクに励むことができる、と。だらだらマルチタスクを続けるよりも、毎日が充実する好循環になっていくんです。
(本記事は、デボラ・ザック著『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』の翻訳者インタビューです)