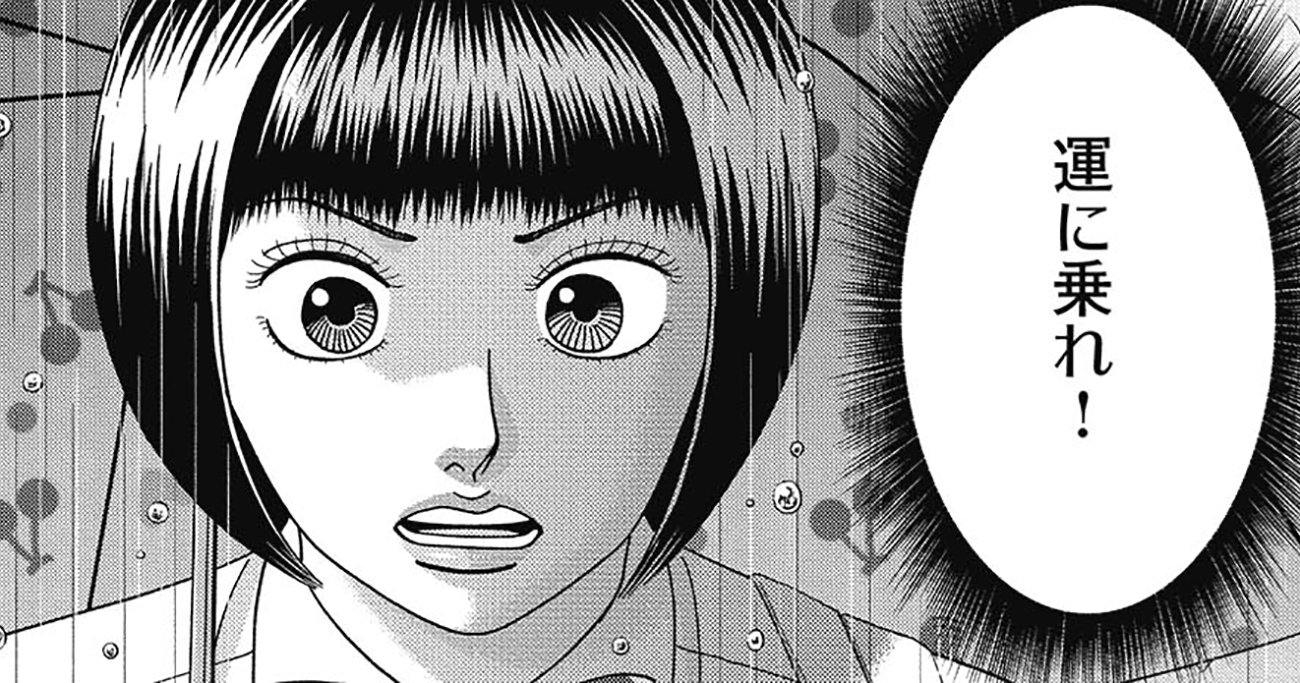 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第89回は、「東京大学駒場キャンパス」について紹介する。
駒場東大前の駅を出ると…
東京大学現役合格を目指す早瀬菜緒と小杉麻里は、高校生でも受けられる「金曜特別講座」を受講するため、東京大学駒場キャンパスを訪れた。
渋谷駅から京王井の頭線で2駅目の駒場東大前駅を降りると、目の前に東京大学駒場キャンパスがある。
東大に合格すると、基本的に2年生までは駒場キャンパスを拠点に学生生活を送ることになる。駒場東大前駅には各駅停車しか止まらないが、例外として駒場祭(毎年11月末)と入試の時には急行が臨時停車する。
これは入学してから知ったことなのだが、いわゆる駒場キャンパスの正式名称は「駒場Iキャンパス」で、10分ほど歩くと「駒場IIキャンパス」がある。これは主に研究施設として利用されており、学部生にはあまりなじみのない場所なのだが、駒場IIキャンパスの食堂で提供されるおにぎりを求めて通う学生もいる。
ちなみに、東大と聞いて思い浮かべるであろう赤門や安田講堂があるのは3・4年生が主に通う本郷キャンパスだ。そのほかにも院生向けの研究施設として千葉県に柏キャンパスがある。
首都圏に住む受験生はふらっと東大のキャンパスを訪れることもできるだろうが、そうでない人にとって実際にキャンパスの地を踏む機会は限られている。
オンラインのオープンキャンパスやGoogleマップのストリートビューなどでキャンパスの様子を見ることもできるが、私がおすすめしたいやり方は別にある。
「幽霊」のように漂う“重厚な雰囲気”
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
東京大学新聞が2019年から2020年にかけて連載していた「サーギル博士と歩く東大キャンパス」だ。
文化地理学者ジェームズ・ サーギル特任准教授と共に、幅広い人文学的知見を用いて東大の見どころを巡るという連載で、現在も公式サイトで読むことができる。哲学の知識が必要な部分もあり、やや難解な内容も含まれるが、東大のアカデミックな雰囲気を感じてもらうにはぴったりだ。
有名な赤門については「赤門に覆い隠され『不在』となっている空間を把握することで、赤門からのぞくことのできる東大構内の風景があくまで全体の一部であることが理解され得る」と述べ、東大の中と外を隔てる境界線としての門の機能を解釈している。
ちなみに赤門は耐震補強などの調査のため現在は閉じられており、入ることができない。
駒場東大前駅をおりて真正面に構える駒場Iキャンパス1号館についての考察も面白い。
この1号館は主に英語や第二外国語の授業に使われるのだが、戦前の旧制第一高等学校時代からの歴史ある建物なだけに、その重厚な雰囲気が時折、異様さをまとうこともある。サーギル博士はこの異様さを、過去の痕跡を現在に残す「幽霊」に例えて考察している。
そのほかにも、本郷キャンパスの総合図書館や駒場キャンパスにある駒場池、さらにはオンライン授業についてもユニークな解釈が加えられ、東大の魅力を味わうことができる。
駒場キャンパスの施設の中で私がおすすめしたいのは、KOMCEE(コムシー)と呼ばれる建物だ。
机とイスが規則的に並ぶのではなく、不規則な形のテーブルとホワイトボードが並ぶ教室がいくつかある。1年生の頃は同じクラスの人が自然とそこに集まり、課題を黙々と進めたり歓談をする場所になっていた。
もし受験生がキャンパスを訪れる機会があれば、その建物の外観だけを見るのではなく、その建物が学生にとってどのような機能を果たしているのかに焦点を当てて見てみると、学生生活をイメージしやすいのではないかと思う。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







