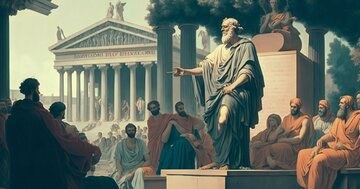シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
哲学は、学びの基礎中の基礎
哲学は、学びの基礎中の基礎の学問だ。
時間と関心があれば、有名な哲学者の著作を読むのもいいが、そうでなければ、以下のようなスキルだと思って、体幹のように日々トレーニングしてほしい。
哲学は、ウエイトトレーニング前の体幹トレーニングと同じ立ち位置にある。
体幹が強くなればそのおかげで、より効果を生む正しい姿勢で、より強度の高いウエイトトレーニングができるのと同じだ。
哲学的思考が身につけられれば、考えることがさらに楽しくなり、その思考を活かしてより深い学びができる。
哲学を学ぶ意義やメリットは、以下の4つである。
1.本質を見抜く力
2.タブーや先入観を排する力
3.あることの本質をメタファー(隠喩)として適用する力
4.自分を内省するスキル
それぞれについて、順番に説明しよう。
1.本質を見抜く力
まず、哲学とは「本質」を見抜く力である。
世の中にあるものはいろいろな側面を持っている。それを間違ってとらえると、時間やお金など、私たちの大事な資源を失ってしまう。
本質とは、そのものの真価であり、一番大きな不変の価値である。
物事に向かうとき、まずはその本質をつかむことが不可欠だ。
これができれば、自分のリソースをかけて、より大きなリターンを得る確率が上がる。
例えば、「人間とは何か?」という“人間の本質”を問うてみる。
これは我々に欠かせない問いである。ビジネスも政治も「人間の本質」を問うところから始まる。
人間の定義は多様だ。影響力を持つ人々によって過去に行われた主な定義としては、以下のようなものがある。
・ホモ・サピエンス(知恵のある人):リンネによる学名で、知的能力を持つ動物として定義されている。
・ホモ・ファーベル(工作する人):ベルクソンによる定義で、道具を作る能力を持つ存在としている。
・ホモ・シンボリクス(象徴的動物):カッシーラーによる定義で、言語などの象徴を介して世界を抽象的に理解する存在とされる。
・ポリス的動物:アリストテレスによる定義で、社会を形成する存在としている。
・間柄(あいだがら)的存在:和辻哲郎による定義で、人間関係の中で生きる存在とされる。
松下幸之助氏による定義では、
・万物の王者:宇宙の動きに順応しつつ万物を支配する力を持つ存在。
・天命を持つ存在:万物それぞれを生かしつつ、人間生活自体の物心一如の向上発展を生み出す権能を持つ。
どれも、それなりの説得力を持つ定義だろう。
さて、ここで本質に迫るために、各々の定義を批判的に見ていこう。
「ホモ・サピエンス(知的能力を持つ存在)」
→タコやイカやイルカや類人猿の中にも、高い知能を持つ存在はいる。
「ホモ・ファーベル(道具を作り使う存在)」
→アリや類人猿や鳥の中には、人間と同じように道具を作って使うものもいる。
「ポリス的動物」
→アリやハチやライオンやニホンザルまで、社会を形成する動物は多数ある。
「万物の王者、天命を持つ存在」
→逆に、そうでない人間もたくさんいる。
取り上げた中では、以下のものが本質に近いだろう。
ホモ・シンボリクス(象徴的動物):カッシーラーによる定義で、言語などの象徴を介して世界を抽象的に理解する存在。
ちなみに私は、ホモ・シンボリクスに近い定義だが、
「ナラティブ(物語)を創り、ナラティブを信じて、そのために危険を冒す存在」
と定義している。
この定義に基づいて、ビジネスを創ったり、評価したりするのだ。
2.タブーや先入観を排する力
哲学とは、タブーや先入観を排する力である。
たとえば、「戦争は悪である」とよく言われる。私も戦争は嫌いで怖い。これも哲学する必要がある。
しかし、本当にそうか? 問うてみる意義がある。
嫌ったり、怖がれば「戦争はなくなる」のか、を知るためにも大事な問いだ。
そこで、その問いを実例にぶつけてみるのだ。
・もし第二次世界大戦で敗戦していなければ、我々は今どんな日本に生きているか?
・人類は常に前進しておらず、前進と後退を繰り返しているのではないか?
3.あることの本質をメタファー(隠喩)として適用する力
哲学とは、あることの本質をメタファーとして適用する力である。
人類史上ほとんどの重要発明は、中国で生まれているが、それが商業利用され、自国の経済発展に使われることはなかった。
なぜ、中国で産業革命が起こらなかったのか?
過去の歴史に潜む本質をメタファーにして、未来を予測する術について、本連載ではそのヒントを提示していく。
4.自分を内省するスキル
自分を掘り下げて観察するスキルとして、哲学は有効だ。
自分の現在位置が把握できなければ、目標が定まらないし、対象を相対視することもできない。デカルトの、
「われ思う、故にわれ在り」
ではないが、あらゆるバイアスを外して、自分を見つめるスキルとして哲学は役立つ。
自分が信じたい自分、自分が見たい自分、誰かの期待に沿いたい自分ではなく、今の自分の本音(何を望んでいるのか? 何が好きなのか?)や、真の実力や適性をファクトとして、あらゆる先入観を排して本質として見抜くのだ。
最高の実力を悔いなく発揮するためには、あなたは「あなた自身である」ことが大事だ。
目標も他者に評価されたいものだと、意味がない。
我々は他人の気持ちをコントロールできないからだ。
そして、他者は、あなたが期待するほど、あなたに長く関心は持ってくれない。他者の評価にゆだねることや、それを期待することほど無意味なことはない。
(本稿は『君はなぜ学ばないのか?』の一部を抜粋・編集したものです)
シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 兼任教授、カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル・リーダーシップ・インスティテュート フェロー、一橋ビジネススクール 客員教授(2022~2026年)。元参議院議員。早稲田大学卒業後、慶應義塾大学大学院(MBA)、デューク大学法律大学院、イェール大学大学院修了。オックスフォード大学AMPおよび東京大学EMP修了。山一證券にてM&A仲介業務に従事。米国留学を経て大阪日日新聞社社長。2002年に初当選し、2010年まで参議院議員。第一次安倍内閣で内閣府大臣政務官(経済・財政、金融、再チャレンジ、地方分権)を務めた。
2010年イェール大学フェロー、2011年ハーバード大学リサーチアソシエイト、世界で最も多くのノーベル賞受賞者(29名)を輩出したシンクタンク「ランド研究所」で当時唯一の日本人研究員となる。2012年、日本人政治家で初めてハーバードビジネススクールのケース(事例)の主人公となる。ミルケン・インスティテュート 前アジアフェロー。
2014年より、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院兼任教授としてビジネスパーソン向け「アジア地政学プログラム」を運営し、25期にわたり600名を超えるビジネスリーダーたちが修了。2022年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校においても「アメリカ地政学プログラム」を主宰。
CNBCコメンテーター、世界最大のインド系インターナショナルスクールGIISのアドバイザリー・ボードメンバー。米国、シンガポール、イスラエル、アフリカのベンチャーキャピタルのリミテッド・パートナーを務める。OpenAI、Scale AI、SpaceX、Neuralink等、70社以上の世界のテクノロジースタートアップに投資する個人投資家でもある。シリーズ累計91万部突破のベストセラー『頭に来てもアホとは戦うな!』など著書多数。