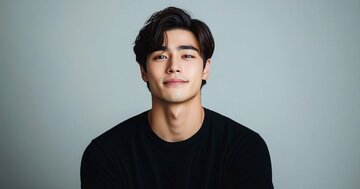AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って「斬新な解決策」を生み出す
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、前提条件や常識をとっぱらった、斬新な解決策を見つけたいときにおすすめなのが、技法その12「制約なき発想」です。
こちらが、そのプロンプトです。
エネルギー、資金、時間、人材、法規制の制約がまったくないとしたら、もっとも理想的な〈アイデアを得たい対象を記入〉する手段は何だと思いますか?
「仮に、制約のない状況であれは何が発想できるか」。
ブレインストーミングが停滞したとき、優れたファシリテーターが投げ込む問いです。
制約や先入観から離れて発想する。「それができれば苦労しない」と思うかもしれませんね。1人きりだとなおさら“囚われて”しまいがちです。いくら制約を外そうと試みても、制約を外そうとすることで、かえって制約を意識してしまったりします。
こういうときに使えるのが、この技法です。AIの特性として、条件を細かく入力しなくても情報(この場合は制約)を推定し、回答を進めてくれます。短いプロンプトですが、大胆なアイデアが出やすくなる仕組みです。
「選挙の投票率」を上げるアイデアを考えてみよう
では、実践してみましょう。
制約がたくさんありそうなお題のひとつとして、「投票率を上げたい」を取り上げて実践してみます。選挙活動には法律など様々な制約がありますから、なかなか有効策が見つからないこの問題、制約がなければどんなアイデアがあり得るのでしょうか?
エネルギー、資金、時間、人材、法規制の制約がまったくないとしたら、もっとも理想的な〈選挙の投票率を上げる〉手段は何だと思いますか?
この手のお題へのアイデアは、「ダメな理由」はいくらでも思いつきますが、「じゃあ、どうすれば?」と考えると、ピタッと止まってしまうことがよくあります。AIに突破口を期待したいところ。