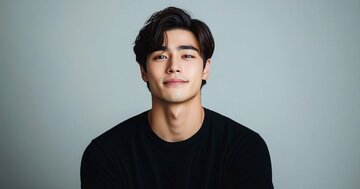エネルギー、資金、時間、人材、法規制の制約がまったくないという仮定のもとで、選挙の投票率を上げるもっとも理想的な手段を考えるとき、いくつかの革新的で包括的なアプローチが考えられます。以下にそのような手段を挙げてみます。
1.全国民への教育と啓発:すべての市民に対して、選挙の重要性、投票の仕組み、候補者の政策と立場についての教育と啓発を行います。これには学校教育はもちろん、メディア、オンラインプラットフォームを利用した包括的なキャンペーンが含まれます。
2.アクセスの容易化:投票所の大幅な増設、移動投票所の導入、24時間投票可能な施設の設置、オンライン投票システムの開発と導入などにより、すべての有権者が容易に投票できるようにします。
3.投票日の祝日化:投票日を国民の祝日に指定し、企業や学校も休業することで、誰もが投票所に行きやすくなります。
4.インセンティブの提供:投票参加者に対する金銭的インセンティブの提供や、投票後に受け取れる特典やサービスの提供など、投票を促進するためのインセンティブ制度を導入します。
5.自動登録システムの導入:国民が生まれた時点で自動的に選挙人名簿に登録され、適齢に達した時点で投票資格を得るシステムを確立します。
6.多言語サポートの拡充:選挙に関する情報提供を多言語で行い、言語の壁が投票参加の妨げにならないようにします。
7.選挙プロセスの透明性と信頼性の向上:選挙の透明性を高めるための技術の開発と導入、不正投票を防ぐための厳格なセキュリティ対策を講じることで、選挙への信頼を高めます。
8.候補者と有権者の直接対話を促進:候補者と有権者が直接対話できるイベントやプラットフォームを多数提供し、有権者が候補者の政策や人物像を深く理解できるようにします。
これらの手段は、理想的な状況下ではありますが、選挙の投票率を大幅に向上させる可能性があります。重要なのは、それぞれの国や地域の具体的な状況に応じて、最も適切な手段を選択し、実施することです。
「24時間投票」「オンライン投票システム」「インセンティブの提供」あたりは、既視感あるアイデアでしょうか。
「祝日案」は可能性がありそう。現在のところ投票日はもっぱら日曜日ですが、平日にした上での「投票日の祝日化」なら、「投票のための休みなんだね」という意識が作れるかもしれない。それは制約の枠を外した感がありそうです。
「それは制約がなければの話で、実際には制約があるんだから無理だろ」なんて考えそうになるとき、それもまた思考が囚われています。その制約を、なくすことはできないのか。日本では制約になっている諸事情を、すでにとっぱらっている国もあるかもしれません。外国の事例も含めて聞いてみましょう。
日本とは法制度や制限が違う国や時代からヒントを得た案も出してみてください。
日本ではそうだけど、他の国ではそもそも存在していない制約もありますよね。時代によっても違うでしょうから。
日本とは異なる法制度や制限を持つ国や時代からのヒントを踏まえて、選挙の投票率を上げるための斬新なアイデアを提案します。これらのアイデアは、文化的、社会的背景が異なるため、そのまま適用するのではなく、参考点として考えることが重要です。
1.オーストラリアの義務投票制度:オーストラリアでは投票が義務付けられており、投票しない場合には罰金が科される場合があります。この制度を参考に、投票を義務化し、参加を促すための法的枠組みを検討することができます。ただし、これを実施するには、選挙へのアクセスを大幅に向上させる必要があります。
2.ブラジルのバイオメトリック投票システム:ブラジルでは、バイオメトリックデータを利用した投票システムを導入しており、選挙の透明性とセキュリティを高めています。この技術を利用して、投票プロセスを簡素化し、より安全にすることが可能です。
3.エストニアのオンライン投票:エストニアは、オンラインでの投票を可能にする世界初の国となりました。オンライン投票システムを導入することで、アクセスの容易さを大幅に向上させ、投票率の向上を図ることができます。
4.南アフリカの移動投票所:選挙時、遠隔地や農村部の住民が投票しやすいように移動投票所を設置することで、投票へのアクセスを向上させることができます。このアプローチは、地理的な障壁が投票率に影響を与える地域でとくに有効です。
5.古代アテナイの抽選による公職選出:古代ギリシャのアテナイでは、公職者を抽選で選出する制度がありました。このような直接民主制の要素を現代の選挙に取り入れることで、政治参加への関心を高めることができます。
6.スウェーデンの長期的な政治教育:スウェーデンでは、学校教育を通じて幼い頃から政治教育が行われています。長期的な教育プログラムを通じて、市民に政治参加の重要性を教え、選挙への関心を育てることができます。
7.ニュージーランドの若年層へのアプローチ:ニュージーランドでは、若者が政治に参加しやすいように、ソーシャルメディアやイベントを通じた啓発活動が行われています。若年層に焦点を当てたアプローチを強化することで、将来的な投票率の向上につながります。
これらのアイデアは、日本の法制度や文化に合わせて適応する必要がありますが、選挙の投票率を高めるための新しい視点を提供することができます。重要なのは、これらのアプローチがすべての市民にとって公平でアクセスしやすいものであることを確保することです。
行政や政治関係の仕事をしていたり、日々ニュースを丹念に読んでいたりしたら、こうした事例も知ることができるのでしょう。ですが、素人としては目からウロコなケーススタディでした。
ここで言う制約なき発想とは、現時点において世界中のどこにもない発想である必要はありません。商品であれば自社の顧客にとって新しい、今回のケースで言えば日本国内で行われる選挙にとって新しければ充分です。こういった他国事例をそのまま取り入れるのもアリだと思います。
なお、すでにお察しの方もいるかもしれませんが、固有名詞を含む回答についてはハルシネーションへの対策は行うべきです。資料的に使う場合は、実際に存在するのかどうかを検索して調べておきましょう。
もちろん、AIの回答をベースにアイデアを膨らませるのはOKです。その場合は、AIが出したこれらの事例が存在していようがいなかろうが関係ありませんよね。古代ギリシャにならった「抽選による公職選出(くじで議員を決める)」、というアイデアは、日本ならどういうふうに使えるだろうか。考えてみると、さらにアイデアが浮かんできます。
なお、何が制約条件になっているかがいまいち把握できていないと感じたなら、AIに「この(自分が抱えている)課題の解決における制約条件を列挙してください」と伝えてみてください。重要だと感じたものを、プロンプトの中で列挙している制約の例に加えて技法を使ってみると、AI回答の精度が上がります。
技法その12「制約なき発想」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています)