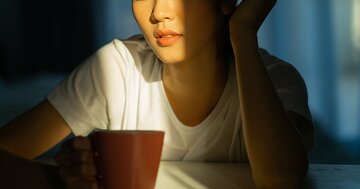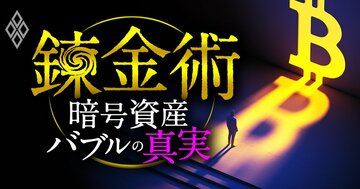チェーン店がセントラルキッチンで調理した料理も「預製菜」?
10日間にわたる丁々発止の激論の末、結果的に西貝レストラン側が謝罪した。だが、この間のやり取りを眺めていた人たちの間からは多くの疑念の声が上がった。
羅さんが言った「預製菜」とは先にご紹介したような「レトルト」ではなく、チェーン展開するレストランが、そのセントラルキッチン、つまり店舗とは別の厨房あるいは工場で店舗に提供するために事前に制作しておいた半加工品だったようだ。だが、手広く店舗を展開するレストランが、手間暇のかかる調理過程を事前に済ませて作っておいた半材料を、預製菜と呼べるのか。
一方で、西貝レストランの経営者、賈国龍さんが「預製菜なぞ使っていない」と言下に否定したことへも反論が渦巻いた。「レストランはレストランのプライドがあるだろう。だからと言って、すべての預製菜をまるで悪徳商品のように切り捨てるのはいかがなものか?」というのが、預製菜「支持派」の主張だった。
お気付きだろうか。羅さんといい、賈さんといい、さらには預製菜「支持派」といい、それぞれが考える「預製菜」が微妙にずれていることに。
これを受けて、論争を眺めていた人たちの間から、「いったい、預製菜ってなんなんだ?」という声も上がり始めた。中国語を文字通りに解釈すれば「事前に(預)」「作った(製)」「料理(菜)」という意味になる預製菜に、セントラルキッチンで大量生産した半加工品も含まれるのか否か。また、預製菜が多くの人々の食卓を飾っているのは、おいしくて便利だからだ。粗製濫造品も氾濫しているとはいえ、体に悪いものばかりではない。それなのに、なぜ預製菜がこれほど悪者にされてしまうのか。騒動の最中には、「日本では預製菜なんかとっくに生活の一部になっている」という日本の即席文化の紹介記事も出現した。
そうするうちに、「当局が預製菜の規格を定めるべきだ」という主張が高まり始め、これを受けて、国務院(内閣に相当)食品安全委員会が政府の各監督部門に対し、「早急に預製菜の国家基準を制定」するよう厳命したという報道も流れてきた。国家基準が制定されれば、粗製濫造製品の取り締まりも拍車がかかるはずだ。そうなれば、預製菜市場ももっと健全になっていくことだろう。