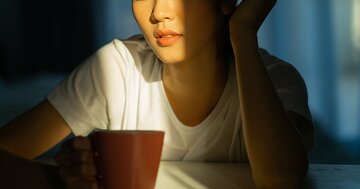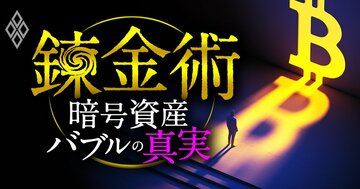厳しい規制下で制約された生活を送った人たちは、次第にウェブサイトやレシピ本と首っぴきで、あるいは家族や友人に教えてもらいながら自分で料理を始め、その面白さ、そして「手軽さ」、さらにはコスパの良さにハマってしまった。また、香港の政治的環境の変化も相まって、親しい人たちを自宅に呼んでプライベートな空間で忌憚(きたん)ないおしゃべりを楽しみつつ、その料理の腕前を披露するのも、「また楽しからずや」となったのだ。
今では筆者の友人たちの多くも、自宅での自炊を中心に暮らしている。朝から昼、アフタヌーンティー、さらには夕食に夜食まで外食していた香港人たちは、すっかり姿を変えてしまった。
中国で「預製菜」が普及
香港よりずっと大規模で、長期にわたる封鎖が行われた中国でも、同じような変化が起きた。コロナウィルス前の外食率は香港ほどではなかったものの、それでも家に帰って自分で作るより外食、あるいは超がつくほど発達したデリバリーで済ませていた人たちの多くが、突然のマンションや都市の封鎖によって「家に食べるものが何もない」、さらには「鍋釜すらない」という事態に直面した。
そんな封鎖が緩んだ時、注目されたのが買ってきて温めるだけの「預製菜」(レトルト食品、調理済み食品)だった。封鎖下では自炊しようにも配給物資は限定的で、満足な一品も作れない。それこそ鍋釜すらない人たちにとっては基本の調味料すらない。そこで、すでに味付け済みでパックされ、食べたい時に温めればよい「預製菜」が歓迎されたのである。なお、ここでいう「菜」とは野菜のことではなく、料理そのものを意味する中国語だ。
十数億人の巨大な人口を持つ中国だが、実はそれまで預製菜のような半加工食品はそれほど重視されず、その種類も多くなかった。最も人気の預製菜は水餃子であろう。筆者も中国在住の頃にはスーパーで売られているさまざまな種類の水餃子を買いまとめし、食べたい時にお湯に放り込んで食べていたものだった。だが、水餃子のほかにはほぼ原材料となる野菜や魚をそのまま凍らせたものがほとんどで、味付けまで済んでいて預製菜と言えるものはほぼなかった。
そんな預製菜が、コロナウィルス封鎖の不便な生活を経て、大人気商品となった。もちろん、デリバリーは復活したし、外食も以前通りに再開された。だが、預製菜には「いつでも食べられる」安心感があるし、コロナウィルス後の経済事情悪化で懐が寂しくなった人たちにとって、「プロが作った」とうたう預製菜は外食の代わりにすることもできた。もちろん、主婦たちも大助かり、というわけである。