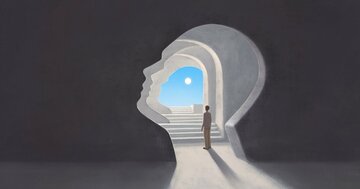シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
企業の事業分析が哲学そのものになる
私のビジネスパートナーの大半は、世界中に散らばっている。
その人たちの国籍は、「何人(なにじん)」とは定義できない。
なぜなら彼らの多くは、「自分が生まれた場所」と「教育を受けた場所」と「今、住んで仕事をやっている場所」が違うからだ。
・インドで生まれ、アメリカで教育を受け、シリコンバレーに在住して働いている
・アメリカで生まれ、英国で教育を受け、ドバイに暮らして仕事をしている
・ロシアで生まれ、シンガポールで教育を受け、キプロスに暮らし欧州をベースに仕事をしている
等である。
「何人」というのは、生まれた場所も教育を受けた場所も、住んで働いている場所も「日本」である人が多い、我々日本人には普通の発想だ。
私も海外で暮らしたり、教育を受けたりするまで、こういう感覚は持てなかった。
しかし、今はこういう人たちが増えている。
こういうメンバーとリアル会議やテレビ会議で集まり、今後進める事業分析をしていると、やっていることが「哲学」そのものになるから面白い。
「死にゆく中小企業リスト」は、
「宝の山」のリストだった
哲学の定義とは、
「目の前にある当たり前だと思っているものを問い直して、新しい価値を見つける作業」
というものだ。
例えば、
・自分とは……
・民主主義とは……
・国家とは……
・資本主義とは……
・リーダーシップとは……
・企業や製品の価値とは……
などなど。
ビジネスパートナーの皆で、ある既存の日本の中小企業の事業を分析していると、私は「先行きが危ぶまれるベタベタ製造業」だと思ってそう言うと、あるパートナーは「いや、これは斬新な次世代テックだ」と叫び、別のパートナーは「どう見ても、これはエンタープライズSaaSになれる」という。
同じ会社の事業分析でも、人によってこんなに違うのだ。
潜在市場が違うのか? 普段、見ているテクノロジーが違うのか?
また、このメンバーで私にとっての「死にゆく某中小企業リスト」を見ていたとき、多くのメンバーは「宝の山」だと狂喜乱舞する。
スタートアップもいいが、既存の「ゆっくり死にゆく中小企業リスト」と思い込んでいるリストを「哲学」してみると、まったく新しい価値がそこに見つかりまくるのだ。
一般的に、中小企業が衰退する理由としては、以下のようなものがある。
・人手不足
・後継者難
・英語の壁
・外国人嫌い
・新市場の開拓ができない
・外部資金を調達していない
「みにくいアヒルの子」をどう見つけるか?
本連載の2回目でも言及したが、外資の巨大プライベート・エクイティ・ファンドが、ベタな日本企業の新たな価値を再発見し、それを買収・再生して価値を膨らませて売りさばいている。
彼らに言わせると日本市場は、「大きな美しい白鳥になれる“みにくいアヒルの子”がいっぱいいる」という。
私たちが見ているリストには、私たちが考えている以上に、さらに多くの「みにくいアヒルの子」がいるようだ。小さくて見つかりにくいが、それらの企業にはかなりのアップサイド(上振れ可能性)が隠されているのだ。
日本企業には社歴の長いものが多く、事業や製品はしっかり作られている。しかし、多くは地元の銀行としか付き合いがなく、かつ日本の中の狭い市場しか見ていない。
日本のスタートアップにも面白いものがあるかもしれないが、日本の中小企業は製品もサービスも何年も世に出していて、十分な実績もある。スタートアップと違い、事業プランがすでに市場で実践できているものばかりだ。
ただ、これ以上、後継者難や人手不足への対策、新市場開拓や外部資金調達ができなければ、ゆっくりと死にゆくだけだろう。
日本にいるいつものメンバーで事業を見て、縮小する国内市場だけを見ていると、絶望はできるが、「哲学」はできない。
日本はアジアにおいて唯一無二なほど、心地よい社会が実現されていて、世界一英語が通じない社会でもあり、世界の課題や自社製品の次なる応用のチャンスが見えにくい。
しかし、それらを日本の外で生まれ育ち、働く人にさらしてみると、まだまだイケてる商品やサービスの売り方や応用方法が発見できる。
その人たちは、お金も販路も経営能力もあるので、ちょっと面白いポテンシャルを見出したりすることができる。
「みにくいアヒルの子」、つまり、やがては美しい大きな白鳥になるが、今はまったくみにくいアヒルの子にしかみえない過小評価された会社たちは、世界に探しにいかなくても、日本の中に、皆さんの足下にたくさんあるのだ。
グローバルにスタートアップをゼロから立ち上げるのも素晴らしいが、出来上がった実績あるビジネスを再構築するほうが、確実性が高い。あとは、それらを束ねること。
そうした企業をロールアップして(束ねて)一定の規模にすること。そして一定の規模に達したら、プロフェッショナルな経営者を迎え入れる。
これが実現できれば、日本は宝の山だらけといえる。
(本稿は『君はなぜ学ばないのか?』の一部を抜粋・編集したものです)
シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 兼任教授、カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル・リーダーシップ・インスティテュート フェロー、一橋ビジネススクール 客員教授(2022~2026年)。元参議院議員。早稲田大学卒業後、慶應義塾大学大学院(MBA)、デューク大学法律大学院、イェール大学大学院修了。オックスフォード大学AMPおよび東京大学EMP修了。山一證券にてM&A仲介業務に従事。米国留学を経て大阪日日新聞社社長。2002年に初当選し、2010年まで参議院議員。第一次安倍内閣で内閣府大臣政務官(経済・財政、金融、再チャレンジ、地方分権)を務めた。
2010年イェール大学フェロー、2011年ハーバード大学リサーチアソシエイト、世界で最も多くのノーベル賞受賞者(29名)を輩出したシンクタンク「ランド研究所」で当時唯一の日本人研究員となる。2012年、日本人政治家で初めてハーバードビジネススクールのケース(事例)の主人公となる。ミルケン・インスティテュート 前アジアフェロー。
2014年より、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院兼任教授としてビジネスパーソン向け「アジア地政学プログラム」を運営し、25期にわたり600名を超えるビジネスリーダーたちが修了。2022年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校においても「アメリカ地政学プログラム」を主宰。
CNBCコメンテーター、世界最大のインド系インターナショナルスクールGIISのアドバイザリー・ボードメンバー。米国、シンガポール、イスラエル、アフリカのベンチャーキャピタルのリミテッド・パートナーを務める。OpenAI、Scale AI、SpaceX、Neuralink等、70社以上の世界のテクノロジースタートアップに投資する個人投資家でもある。シリーズ累計91万部突破のベストセラー『頭に来てもアホとは戦うな!』など著書多数。