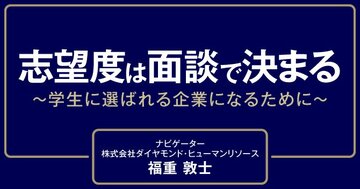これに呼応するように “選考”解禁前の5月末までに学生が面接を受けた企業数は平均8.3社で、全受験企業数(15.4社)の53.9%に相当する。文系学生の56.2%、理系学生の66.0%が“広報”解禁時期の3月までに内定を獲得しており、「早期化」が一層進んでいることが明らかとなった。
「就職先が決まって活動を終了した」学生は64.1%だが、就職活動を継続している学生のうち64.0%が、「内定はしているが、納得いくまで就職活動を継続する」と回答しており、複数内定を獲得した後も妥協せずに活動を継続する「長期化」傾向も見られる。
インターンシップの重要性
生成AIは必須ツールに
企業と学生の初めの接点となるインターンシップ類についても見ておこう。学生がインターンシップ類に参加した理由のトップは「就職活動に有利だと思うから」(82.3%)で、インターンシップ類への参加を就職活動の一環として捉えている。参加率は79.0%と8割に迫り、平均参加回数は調査開始以来最多となった25年卒(8.6回)に次ぐ7.9回となった。「11回以上」参加した学生も26.9%に上る。「インターンシップ類に参加した経験が入社企業の選択に影響した」学生は84.8%、「インターンシップ類に参加した企業に入社を決めた」学生は34.5%に上る。
インターンシップ類は、企業にとっても早期から優秀な学生と接触し、企業・仕事理解を深めてもらうための重要なツールとなっている。実施理由のトップは「採用に向けた母集団形成」(92.1%)で、大手企業の92.2%、中堅・中小企業の71.3%はインターンシップ類参加者からの採用実績が「ある」と回答。学生・企業双方に欠かせない機会となっている。
25年卒からは一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるようになった。26年卒では大手企業の29.9%が「従来のプログラムで基準を満たしており、採用選考に活用する」としている。「改正内容に合わせてプログラムを変更し、採用選考に活用する」(18.7%)を含めると大手企業の半数近くが採用選考に活用する意向を示しており、今後もその重要性はますます高まりそうだ。
最後に、昨今話題の「生成AI」についても触れておこう。「就職活動で生成AIの活用経験がある」と回答した学生は64.3%と25年卒(28.2%)の2倍超に。具体的な利用方法はエントリーシートの作成や推敲、自己分析の言語化、企業へのメールの添削などが挙げられる。さらに面接の練習相手や企業情報の分析、適性検査問題集の解説などもあり、活用方法の多様化が進む。「使用しなかった場面の方が少ない」という声もあり、就職活動の重要なツールとして今後定着する可能性は高い。
Key Visual by Ken Fukasawa