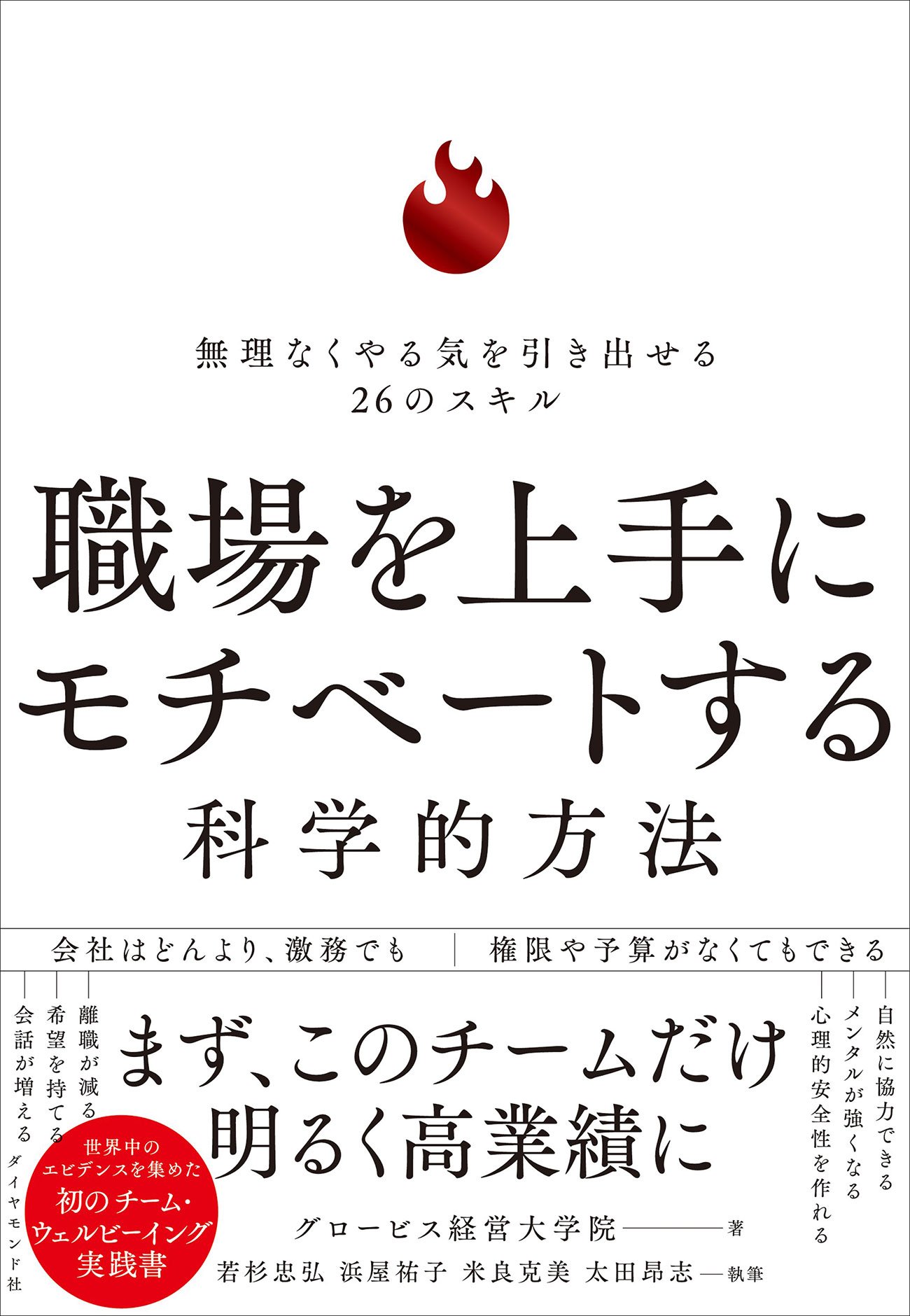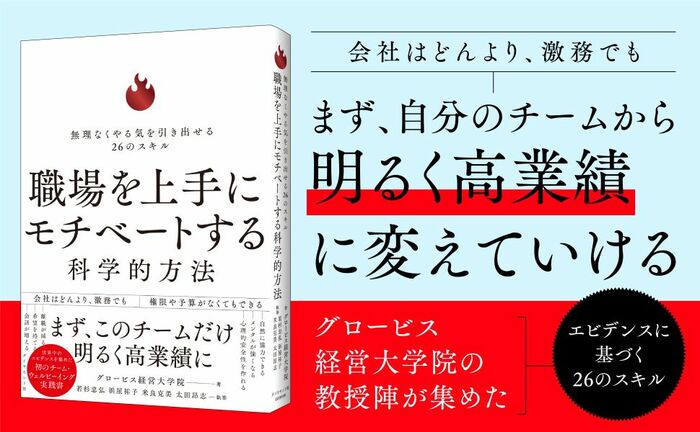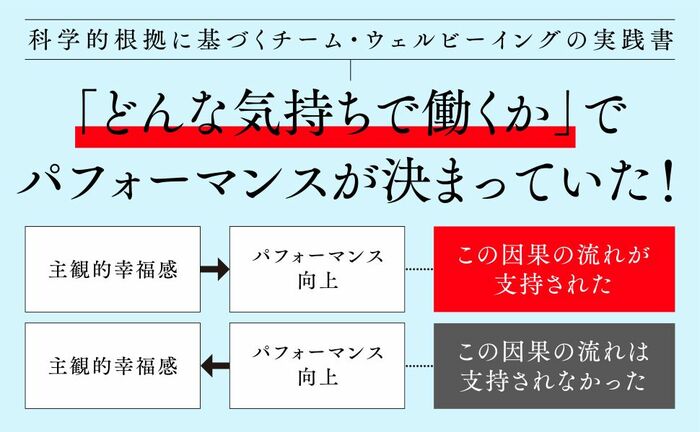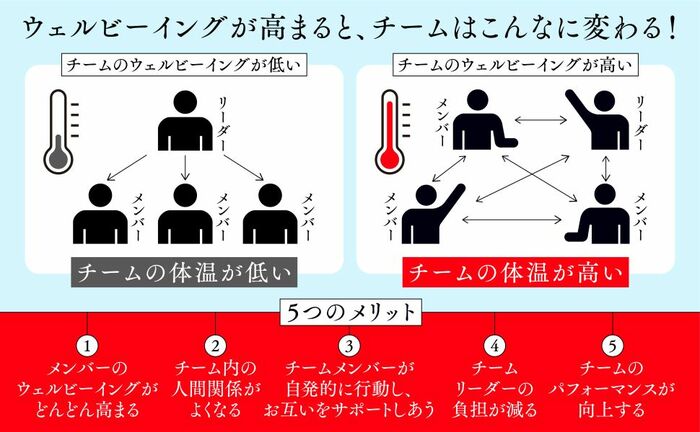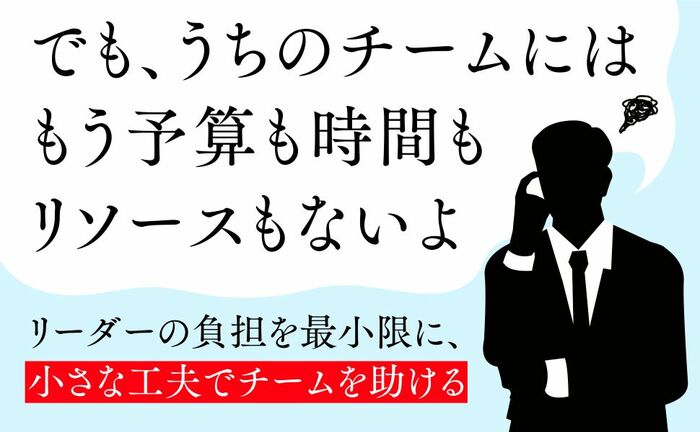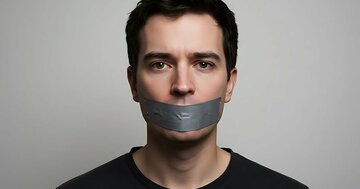直接ほめてもダメなら、カゲホメする
「ほめる」行為には、人のモチベーションを高める効果がある――これは誰もが実感していることでしょう。幼児[1]から小学校低学年[2]、高校生[3]、大学生[4]まで幅広い年齢層を対象とした実験でも、その有効性が証明されています。当然、社会人に対しても有効なはずです。
ではなぜ、原田さんのチームではほめてもメンバーのモチベーションが上がらなかったのでしょうか?
一因として考えられるのは、リーダーの「ほめる」行為に対する信頼性の欠如です。具体的には、リーダーのほめ言葉に対して、メンバーが「本当にほめているのだろうか?」と疑念を抱いていた可能性があります。
もしそうであれば、「カゲホメ」をしてみるとよいでしょう。「カゲホメ」とは、本人に直接言わず、第三者を通じて間接的にその人のことをほめる行為です。
「○○さんがあなたのことをほめていたよ!」と誰かから言われたとき、思わずうれしくなった経験はありませんか? まさにこれが「カゲホメ」の効果です。
カゲホメはなぜ効果的か?
では、なぜ直接ではなく、あえて陰でほめることが効果的なのでしょうか?
その理由は、私たちが第三者を通じて伝わる情報も加味しながら判断する心理にあります。たとえば、商品を選ぶ際は自分の経験や知識だけに頼るわけではありません。むしろ、第三者からの情報を手掛かりにすることのほうが多いでしょう。
身近なところだと家族や友人の意見、レビューサイトの評価、SNSの投稿といった第三者の意見を信頼し、参考にします。人は商品の内容を判断する際、第三者機関の情報に影響されるという研究結果もあります[5]。
この効果が「カゲホメ」にも応用できるというわけです。したがって、リーダーが直接ほめてもその言葉が相手に響かないときは、第三者を通じて伝えるようにすればよいでしょう。そうすることでほめ言葉の信頼性が増し、メンバーに受け入れてもらいやすくなります。
カゲホメの上手なやり方
では、この「カゲホメ」を職場でどのように実践するとよいでしょうか。
もっともシンプルなのは、信頼できるメンバーやほかのリーダーに協力してもらい、ほめたいメンバーの良い点を間接的に伝えてもらうやり方です。ただし、自分がこの方法に慣れるまでは、どこか不自然に感じたり、気まずさを覚えたりすることがあるかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、ミーティングの冒頭の話題として「カゲホメ」を活用する方法です。たとえば、こんなテーマを設定してみます。
「今日このミーティングに出席していない人の行動で、一緒に仕事をしていて学びになったことは?」
このテーマについてメンバー同士で意見を出し合えば、お互いの良い点を認め合う空気が自然に生まれます。そして、ほめられた人も、どこかでその評価を耳にするでしょう。こうした間接的な称賛は、わざとらしく聞こえず、誰でも受け入れやすいかたちで伝わります。
このほめ方をすると、チーム全体にも大きなメリットがあります。それは、「こんな行動が評価される」という基準が明確になることです。称賛される行動が「模範」として定着することで、チーム全体がより良い方向に変わる効果が期待できるのです。
「カゲホメ」は個人のモチベーションを高めるだけでなく、チーム全体の成長にもつながる有効な手法です。ぜひ職場で取り入れて、その効果を実感してみてください。
ほめることのネガティブな側面
ここまで「カゲホメ」の効果を見てきましたが、最後に「ほめる」ことにはネガティブな側面もあるということに触れておきましょう。
「ほめる」行為は基本的にポジティブな効果をもたらしますが、注意すべき点もあります。そのひとつが、本人が自覚していないことをほめすぎることです。
たとえば、プレゼンに苦手意識をもっているメンバーに向かって「プレゼンがとても上手ですね」とほめても、口先だけの社交辞令と受け取られ、さらに自信を失わせることになります。リーダーがメンバーの努力や成果を深く理解せずに安直にほめ続けると、かえってメンバーのモチベーションを下げてしまうおそれがあるのです。
ほめられた内容が本人の認識と食い違うと、自己批判を引き起こすことがあるという研究結果[6]もあります。
また、お互いが認識していることであっても、その「ほめ」が過剰になってもいけません。なぜなら、あまりにほめすぎると、大げさなお世辞に聞こえ、「何か下心があるのでは」と疑われるおそれがあるからです。
それが実際に本人の長所であっても、しつこくほめると、相手を当惑させたり、不自然さを感じさせたりすることもあります[7]。何事もバランスを見極めることが大切です。
ほめ方の注意点
それを踏まえ、リーダーが「ほめる」ときは、次の点を意識するとよいでしょう。
相手が納得できる事実に基づいてほめる
ほめるときは具体的な行動や成果に焦点を当てましょう。たとえば、「あなたのプレゼンでの資料整理や質疑応答がすばらしかった」と具体的な点を挙げてほめると、相手も納得しやすくなります。
過剰なほめ方は避ける
ほめすぎると、相手が不自然さを感じたり、真意を疑われたりすることがあります。ほめられた自分の行動や成果に本人が納得できる範囲で評価しましょう。ほめ言葉についても過剰に飾らず、伝えたいポイントをシンプルに伝えることが大切です。
ほめるタイミングを見極める
ほめるタイミングも重要です。ほめること自体は悪くありませんが、相手が成果を実感しているときにほめることで、より効果を高めることができるでしょう。
*この記事は、『職場を上手にモチベートする科学的方法――無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社刊)を再編集したものです。
[2] Swann, W. B. J. & Pittman, T. S. (1977). Initiating play activity of children: The moderating influence of Verbal cues on intrinsic motivation. Child Development, 48, 1128-1132.
[3] Harackiewicz, J. M. (1979). The effects of reward contingency and performance feedback on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1352-1363.
[4] Deci, E. L., Cascio, W. F., & Krusell, J. (1975). Cognitive evaluation theory and some comments on the Calder and Staw critique. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 81-85.
[5] Dean, Dwane H. and Abhijit Biswas (2001), “Third-Party Organization Endorsement of Products: An Advertising Cue Affecting Consumer Prepurchase Evaluation of Goods and Services,” Journal of Advertising, 30(4), 41-57.
[6] Schlenker, B. R. & Leary, M. R. (1985). Social anxiety and communication about the self. Journal of Language and Social Psychology, 4, 171-192.
[7] Buss, A. H. (1986). Social Behavior and Personality Lawrence Erlbaum Associates. 邦訳書は以下。 (大渕憲一監訳 (1991). 『対人行動とパーソナリティ』 北大路書房.)