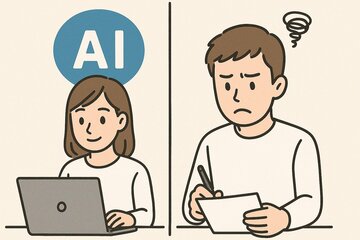(5) 約束や時間の軽視
「明日までに折り返します」と言ったのに音沙汰なし、納期が来ても連絡がない。顧客との約束を守らない対応ほど信用を失うものはない。
特に工事・リフォーム、引っ越し業者、中小のBtoB取引など、現場が流動的な業種ではこのリスクが高い。時間を守ることは顧客にとって「生活や業務の予定を立てる」基本条件であり、そこを軽視されると「この会社は信用できない」というレッテルを即座に貼りたくなる。
(6) 謝罪の仕方が悪い
「ご迷惑をおかけし申し訳ございません」と口先だけの謝罪、あるいは「しかしながら、お客様の……」と責任転嫁する一言。謝罪の瞬間は、顧客が最も敏感になっている瞬間でもある。
形だけの謝罪は、逆に火に油を注ぐことになる。交通インフラの遅延対応、物流・飲食・宿泊業、カスタマーセンターなど「謝る機会が多い業種」ほど、言葉の選び方・タイミング・態度の重要性が増す。
(7) クレーム後の対応が消極的
「検討します」「持ち帰ります」で終わり、その後は何の連絡もなし。顧客は「言うだけ無駄だ」と思い、怒りが無力感に変わる。
製造業の修理受付やサブスク型サービス、本国が強い外資系企業のカスタマーセンター、官公庁の苦情窓口など、「改善権限を持たない現場」で頻発するパターンだ。
せっかく顧客が改善のヒントを与えてくれているのに、それがフィードバックされないどころか、ブラックホールに吸い込まれていくような印象を与える。
(8)説明が間違っている(知識不足・誤案内)
一見もっともシンプルだが、実は顧客に最も深刻なダメージを与える。制度改定を把握していない、例外規定を知らない、確認せずに推測で説明してしまう。結果、顧客が不利益を被ったり、手続きをやり直す羽目になったりする。
行政窓口・金融保険・ITサポート・医療・教育など、「高頻度更新×専門性が高い×顧客が質問しにくい」環境で起こりやすい。しかも「一貫して間違った説明」をされると、顧客は組織全体を信用しなくなる。