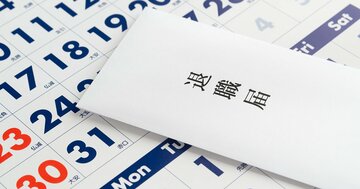写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「課長、僕にも担当をつけてください」――まだ入社1年半の若手社員が、なんと退職届を提出した。理由は「仕事を任せてもらえないから」。働き方改革で残業削減に取り組み、部下を気遣ってきた上司。それが裏目に出て「ホワイトハラスメント」だと指摘されてしまう。優しさが若手を追い詰める?パワハラを恐れるあまり、管理職が陥る新しい落とし穴とは。(社会保険労務士 木村政美)
<甲社概要>
都内にある従業員数300名の貿易会社。
<登場人物>
A:甲社営業課長で38歳。
B:甲社営業課勤務でAの部下。入社2年目の24歳。
C:Bの大学時代の友人で、他社の営業課に勤める24歳。
D:甲社の人事・総務部長(人事担当の責任者)50歳。
E:甲社の顧問社労士でD部長とは昔からの知人。
都内にある従業員数300名の貿易会社。
<登場人物>
A:甲社営業課長で38歳。
B:甲社営業課勤務でAの部下。入社2年目の24歳。
C:Bの大学時代の友人で、他社の営業課に勤める24歳。
D:甲社の人事・総務部長(人事担当の責任者)50歳。
E:甲社の顧問社労士でD部長とは昔からの知人。
友人との再会が招いた、新入社員の焦燥感
甲社では、3年前から働き方改革の一環として、全部署を対象に労働時間と業務内容の見直しを進めてきた。この方針に基づき、A課長が率いる営業課でも、特に新卒入社2年までの社員に対して単独で取引先を担当させるなどの過重な業務を避け、原則残業をさせない体制を徹底することとした。A課長はその方針に忠実に従い、育成にあたっては「無理はさせずじっくり育てる」慎重な姿勢を貫いた。
昨年4月、新入社員のBが営業課に配属された。A課長はBに対して、会社の方針から外れないように先輩社員の取引先への同行、取引先向けの新製品プレゼン資料の作成、社内会議の準備などを指示した。これらは営業課全体から見れば比較的軽い業務であり、本来の勤務時間内で無理なく終えることができた。Bは与えられた業務をそつなくこなしていたが、入社して1年3カ月後、心境の変化が起きた。
それは7月中旬。1年ぶりに上京してきた大学時代の友人Cと再会したときのこと。居酒屋に入り生ビールで乾杯をしたあと、Cがいきなり打ち明けた。