路線は万博会場内の展示地区を取りまくルートで、全長4.27㎞となる単線環状線だ。最急勾配は55‰、最小半径は60m。車内からの展望を良くするため、特別の制限がある区間を除き、全体の6割以上が高架線となっている。また、地平線では線路まわりを高さ1.8mの安全防護柵で覆っていた。
停車場は中央口駅・エキスポランド駅・東口駅・日本庭園駅・北口駅・西口駅・水曜広場駅の7か所。また、北口駅~西口駅間の一部は複線状に200mほどの側線を設け、留置線と兼用する検修線としている。
車両編成は6本用意され、平日は5列車、日曜・祝日は6列車で運用、平日は3分間隔、日曜・祝日は2分30秒間隔の運転となった。各駅の停車時間は40秒で、1周の所要時間は15分、1時間に最大定員約2万5000人の輸送力とした。運行時間は3月15日~4月28日は9時~22時30分、4月29日以降は最終日まで8時30分~23時となっている。
無料のモノレールに「乗ることが目的化」
このモノレールは無料で利用できたこともあり、初っ端から利用者が殺到、1時間平均利用人数は1万人を超える大混雑となった。特に7月は平均で1時間あたり1万4775人もの利用があり、ラッシュ時の通勤電車並みの混みようだった。万博期間中、のべ3351万2314人が利用しており、入場者の52%がモノレールに乗った計算だ。この数字でもモノレール人気のほどが読み取れる。筆者もそうだったが、日本万博協会がめざした会場内輸送機関というより、モノレールに乗ることが目的化していたのである。
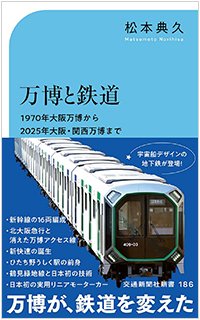 『鉄道と万博』(交通新聞社)
『鉄道と万博』(交通新聞社)
なお、このモノレールは地方鉄道として免許を受け、1968(昭和43)年9月に着工、軌道部分が竣工した1969(昭和44)年8月から試運転を実施している。実はATOによる運転は日本初の事例で、より慎重に試運転を行ったのだ。その後、停車場などの仕上げも進み、1970(昭和45)年3月3~5日に運輸省および大阪陸運局による完工検査を受けた。営業運転は開会式前日の3月13日から行っている。
また、無料の施設ではあるが、地方鉄道として運行されるため、日本万博協会は東京急行電鉄(現・東急電鉄)に管理運営を委託している。同社では運転・保安管理業務・利用者の誘導業務などで115人体制を組んだ。
万博終了後、このモノレールはほかに移設される計画もあったが、残念ながら実現せずに解体されてしまった。
なお、現在の万博記念公園(大阪万博の跡地につくられた公園)などを結ぶ大阪モノレールでは、2020(令和2)年3月から「1970年大阪万博50周年記念」として2000系1編成を当時の万博モノレールに準じた塗色として運行中だ。







