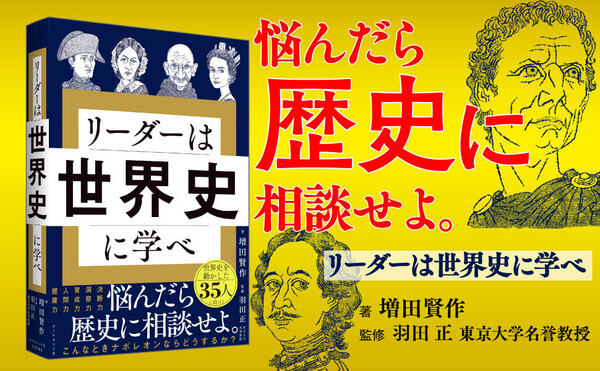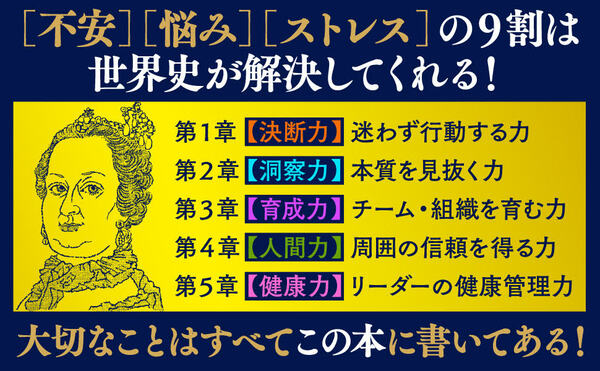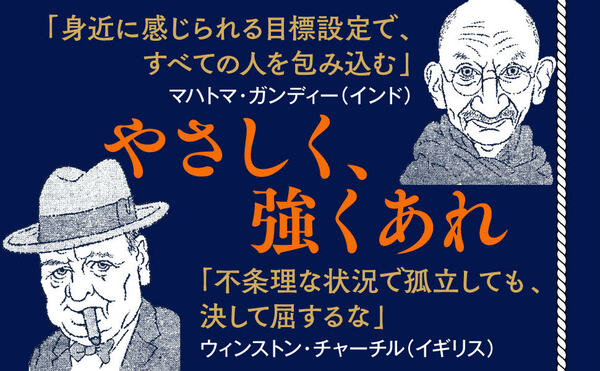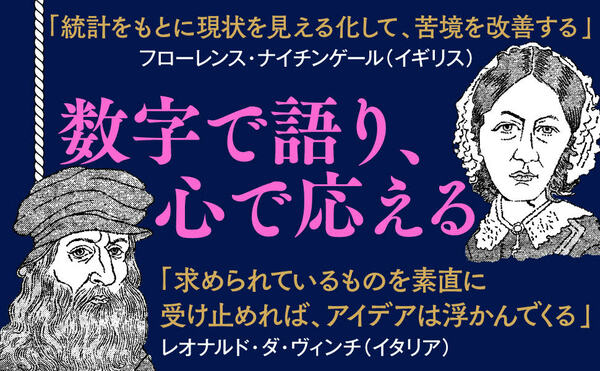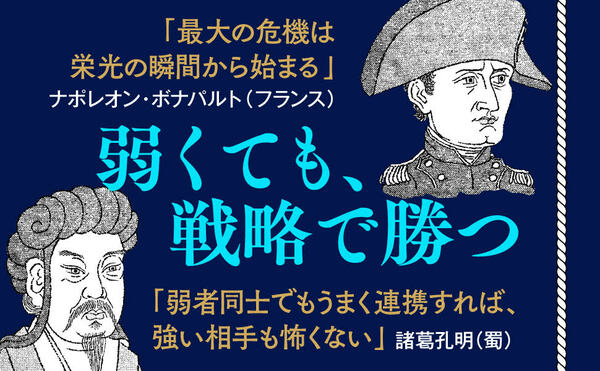「サッチャー政権、命運尽きる」――囁かれた早期退陣
こうした内憂外患のなか、政権発足から3年がたった1982年初頭の段階では、「サッチャー政権は間もなく終わるだろう」という声が政界・メディアを問わず広がっていました。
インフレは収まらず、失業率は高止まりし、国民の間には「改革の痛み」への不満が広がっていたからです。強すぎる改革と、成果の見えにくさ――このギャップが、当初のサッチャー政権をきわめて不安定なものにしていたのです。
逆風を追い風に変えた「鉄の意志」
しかし、サッチャー政権の運命を劇的に変えたのが、1982年のフォークランド紛争でした。アルゼンチンの侵攻に対し、即座に軍を派遣して勝利を収めたことで、彼女の断固たるリーダーシップは国民から熱狂的な支持を集めます。
これを機に経済政策も徐々に成果を上げ始め、政権は長期安定の道を歩むことになったのです。
令和のリーダーに重なるサッチャーの姿
奇しくも、日本初の女性首相になる可能性がある自民党総裁の高市早苗氏は、政治と無縁のサラリーマン家庭で育ち、かねてよりサッチャー氏を信奉してきたことを公言しています。
長期にわたる経済の停滞や社会の閉塞感など、現代日本が置かれた状況は、かつてのイギリスと重なる部分も少なくありません。だからこそ、サッチャー氏のような強いリーダーシップが今、再び注目されているのです。
「鉄の女」から学ぶべきこと
サッチャー氏の評価は今なお賛否両論あります。しかし、私たちが彼女の生き方から学べるのは、国家の未来を信じ、短期的な不人気を恐れずに信念を貫いた「鉄の意志」ではないでしょうか。
それは、政治の世界だけでなく、変化の激しい時代を生きる私たち一人ひとりの仕事や人生においても、困難を乗り越えるための大きなヒントを与えてくれるはずです。
※本稿は『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。