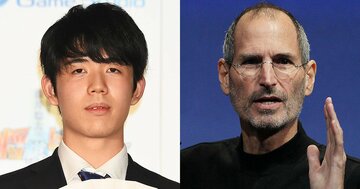AIやインターネットは
対局の記録に便利
また、AIやインターネットとの付き合い方においても、才能をつぶさないための「接し方」が必要です。
AIやインターネットというと、どうしても子どもにとって悪いイメージがあるかもしれませんが、そうとは言えません。
将棋の世界では、「終わった将棋の保存」ができることが大きなメリットといえます。かつて開催していた将棋教室の生徒さんの中には、終わった将棋を思い出せず、忘れてしまうことがありました。
将棋には投了後に「感想戦」といって、一局をビデオテープのように巻き戻し、勝者と敗者がともに「最善手」を振り返る時間があるのですが、忘れてしまえばそれができません。ですので対局中に紙に書き留めながら記録を取っていた子もいました。
でもそれはそれで書き留めることに一生懸命になってしまい、肝心の将棋の内容がおろそかになってしまいます。それが将棋アプリのようなものを使えば記録できますし、第三者に見せる時にも効率がいい。
弟子が自分の将棋を相談する時にも、かつては紙に書いたものを私にファクスしてきましたし、少し前は紙に書いたものを写真に撮ってメールで送ってきました。でも今は将棋アプリに落とし込むことで、受け取る人のほうで再現できるのです。
ですからAIやインターネットは、データの保存、蓄積、再現に非常に便利といえますね。
相手への気遣いが育まれず
考える力を奪うことも
一方でデメリットとしては、将棋の「ゲーム性」だけを取り出したような感じになるので、“相手を気遣う”などの気持ちが育まれません。将棋は「礼に始まり礼に終わる」というような武道の精神のあり方に似ていて、本来対局相手に感謝しなければならないのです。
対局相手がいなければ将棋は成り立ちませんからね。それがインターネットでは「お願いします」ボタンを押して始まり、「負けました」「ありがとうございました」というのもボタンで済みます。インターネットの世界でフリー対局、顔が見えない相手と指して相手が負けた場合、よほど悔しいのか、中にはそれらのボタンを押さずに放置して去る人も……。
人として大事なことが育まれない可能性があると思いますし、さらには自分で考える力、自主性も低下しやすいと感じます。もっと言えば現代社会のあらゆる便利さが、考える必要をなくし、考える力を奪っている面もあるかもしれません。
とはいえ今は生活の中にAIが入り込んできています。現代では好む好まざるに関わらず、インターネットやAIの使用を避けて通ることはできないですよね。たとえ子どもに与えない、禁止したとしても、もう世の中にあるのが当たり前ですから。ですので、どう付き合っていくかが重要でしょう。
才能が伸びる子は
「本当にそうかな?」と思える
例えばテレビやインターネットで棋士の対局シーンが流れると、「評価値」がパーセンテージで表示されます。AIが分析し、ある局面で「どちらが優勢か」というのを示している。子どもが目にすれば「これは何?」と質問するでしょう。この時、AIの評価値であることを説明した上で、子どもがそこで判断や思考を完結してしまわないように注意が必要です。
才能が伸びる子、伸びない子という観点で考えると、評価値を目にしても、「本当にそうかな?」「でもこうやったらどうなるだろう?」と思える子は伸びていくと思います。