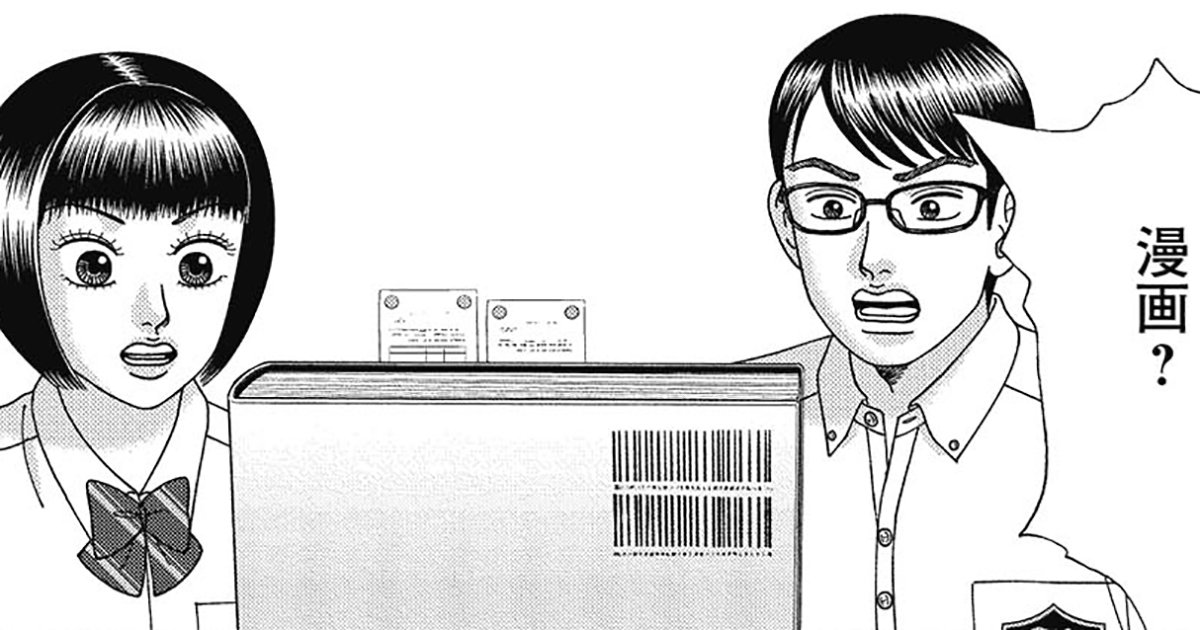 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第95回は、「歴史マンガ」の効能について考える。
東大生が小2で買ってもらったマンガ
東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒の2人は、担任の水野直美に「勉強の気分転換は勉強」と言われ驚愕する。水野は歴史マンガを取り出し、これを息抜きとして使うように2人に勧める。
歴史好きの人の話を聞くと、家にシリーズものの歴史マンガがあった、という人が多い。私も小学2年生ごろに親戚に歴史マンガを買ってもらい、以来歴史は得意科目になった。
日本史だと小学館の『学習まんが 少年少女日本の歴史』や集英社『学習まんが 日本の歴史』、KADOKAWAの『角川まんがシリーズ 日本の歴史』など各出版社が出版している。日本史のみならず、世界史や中国史のシリーズもある。
これらの歴史マンガは、少年マンガのように軽く読めるし、歴史のストーリーがスッと頭に入ってきやすい。専門家による監修の元で作成されており、歴史に興味を持つきっかけとなるうってつけの教材だ。
だが、受験勉強にそのまま使うには少し注意が必要だ。なぜなら、歴史マンガがそのまま小中高のカリキュラムと連動しているとは限らないからだ。
まず、マンガはストーリー性を持たせるためにエピソードが多くなる。源平合戦で那須与一が扇を射った話や、織田信長が桶狭間の戦いで急襲した話など、特に戦闘シーンにおける「かっこいい話」が数多く登場する。
中には伝承としてしか伝わっておらず、史実に確認できない話などが「〜と言われている」などという形で登場することもある。だが、それらの話の重要性は高くない。一昔前の歴史マンガをみてみると、明らかに創作と思われる話が描かれていたこともある。
逆にオススメの「勉強になるマンガ」
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
それに対して、庶民の暮らしや文化史など、ストーリーとして構成しづらい話は分量が少なくなるし、印象に残りづらい。ただ一方で、名もなき庶民の歴史こそ、近年の歴史学で着目すべきとされている点なのだ。
また、近現代史の全体像が掴みづらいという難点もある。古代から近世と違い、近現代は膨大な量の資料が残されており、その分学校で学ぶ量も多い。
山川出版社の高校教科書『詳説日本史』では全体の約40%が近現代だ。一方で、政治史・社会史・経済史・文化史などさまざまに分かれているせいで、マンガとして描くのは難しい。その分、相対的に量が少なくなってしまう。
世界史の歴史マンガでは、登場する地域がヨーロッパと中国に偏ってしまうということもある。
高校で初めて世界史を体系的に学んだ時、イスラーム史やインド史に対する自分の予備知識の少なさに驚いた。同時代に様々な地域でストーリーが展開する世界史だからこそ、何が描かれていないのかに着目できる視点が重要だ。
逆におすすめなのが、古文の作品をマンガで読むことだ。『源氏物語』や『徒然草』などの作品は、子ども向けにマンガ化されている。ストーリーを把握できるだけでなく、絵として記憶がつくため、後々文字だけを読んで勉強することになった時に、頭の中に映像が浮かびやすい。
歴史や古典など、学びの出発点としては、これ以上の教材はない。だがあくまで「出発点」であることを忘れてはいけない。より本格的に歴史を学ぶのであれば、マンガで得られた大まかな流れを元に、教科書や専門書で勉強することが求められる。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







