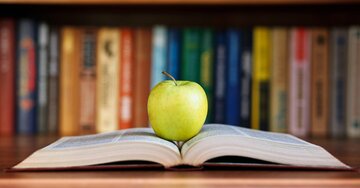秀長を主人公にしてベストセラーとなった小説『豊臣秀長』(堺屋太一著)では、「兄を助ける」ことを、小一郎が仕官した中心的な動機としていますが、幼い頃、別れた兄が突然帰ってきて、そのような心情を本当に抱いたのか、本当のところはよくわかっていません。むしろ、自分も農村の仕事が嫌になっていたかもしれませんし、意外に出世欲にかられてのことかもしれません。というように、兄秀吉の影のように生きた秀長という人物の動機に関しては、よくわからないことが多いのです。
秀長、勇猛果敢の大活躍
それから数年間、20代前半の小一郎の様子も判然とはしていません。おそらくは、農民から武士に転じて、軍事的な技術や武家のしきたりなど、さまざまなことを学んでいたのでしょう。
そして、仕官から5年後、永禄9年(1566)、信長が美濃を本格的に攻めはじめた頃から、秀長は、兄秀吉とともに頭角を表します。以後、豊臣兄弟は合戦に明け暮れることになります。
まず、織田家と美濃の斎藤龍興との戦いでは、秀長は、墨俣城の築城と守備で、かなりの役割を果たしたとみられます。秀吉は美濃勢を陥れるための調略に出向くことが多かったので、兄に代わって、砦の留守居役を務めることが多かったとみられます。
そして、1568年、信長が斎藤龍興を破り、足利義昭を奉じて上洛戦に打って出ると、豊臣兄弟は南近江の攻略戦で活躍します。
その後、1570年の朝倉攻めのさいに、同盟軍の浅井長政に裏切られ、織田軍がピンチに陥ったときは、秀吉は殿(しんがり)をかって出て、秀長はさらにその殿をつとめることを秀吉に命じられます。そして、見事、生き残ります。
兄弟は姉川の戦いに参加。浅井氏の居城の小谷城攻めでは、秀長が中心となって小谷城の郭の要を落とします。その前の比叡山焼き討ちにも、秀長は兄とともに参加したとみられます。
そして、兄秀吉が播磨・但馬攻略をまかされると、秀長はそれに従って、三木城の3年にわたる包囲戦に参加。対毛利の戦いとなった鳥取城攻めや備中高松城の戦いにも加わります。