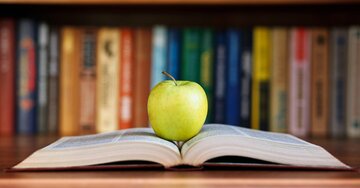その最中、本能寺の変が起きます。その報を受けて、秀吉が毛利と講和を結ぶと、秀長は、中国大返しのさいも、最も危険な任務である殿をつとめました。
明智光秀との戦いとなった山崎の戦いでは、秀長は、おもに天王山の防衛にあたっていたとみられます。
華麗なる戦果で大大名へと大出世
続く、柴田勝家との賤ヶ岳の戦いでは、秀吉が一時近江を離れ、「美濃大返し」を行う間、本陣の大将として全軍を指揮しました。
1584年、秀吉と家康との唯一の直接対決となった小牧・長久手の戦いのさいは、秀長は、家康と連合を組んでいた織田信雄の領地の伊勢へ進軍し、松ケ島城を落としています。
その翌年の紀州征伐では、秀長は、秀吉の副将をつとめ、制圧後、紀伊・和泉64万石を与えられ、大大名となります。その後、家臣の藤堂高虎に命じて、紀伊に和歌山城を築いています。
 和歌山城 Photo:PIXTA
和歌山城 Photo:PIXTA
同年、秀吉が四国に兵を出したさいには、秀長は、秀吉に代わって、総勢11万もの大軍の総司令官をつとめ、長宗我部元親を降伏させました。この四国攻めの功績で、大和国を加増されて、知行高はついに100万石に達したといわれます。また、官位は従二位権大納言に昇進し、以後、「大和大納言」と呼ばれるようになります。
その大和は、寺院の領地が多い難治の国でしたが、秀長は、さまざまな勢力の訴えによく耳を傾け、公正な採決を下したと伝えられます。その一方で、寺社勢力の武装解除につとめました。
続く、1586年からの九州平定戦では、二手に分かれた軍の東ルートを南下する軍の総大将をつとめ、島津軍に勝利します。