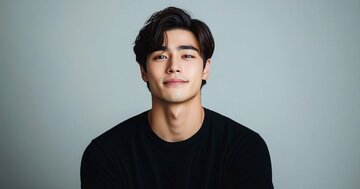AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って“100年後”を予測する「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、イノベーティブなアイデアを生み出したいときにおすすめなのが、技法その56「百年の予測」です。
こちらが、そのプロンプトです。
100年後の〈商品・サービス・行為・概念などを記入〉はどんなものだと思いますか。
アイデアによるイノベーションは、20年、30年と長い時間をかけて徐々に社会や人々に変化をもたらします。
そうしたイノベーティブなアイデアを考えるにあたって、3年や10年先までの予想ではたして充分でしょうか? いっそ、100年ぐらい先まで見通したアイデアを考えてみてはどうでしょうかと、研修の現場ではお伝えしています。
「100年先を考えるなんて、そんなの無理……」
そう感じた方もいるでしょう。でも、そう言わずに。AIの力を借りれば100年先の予測が可能ですから。
そのための手段が、この技法「百年の予測」です。5~10年後の比較的近い未来ではなく、地続きでは発想しにくい100年後をAIに想像してもらいます。未来予測には尻込みしがちなAIですが、100年後という壮大な未来予測に対しては比較的素直に答えてくれます。
「読書」の100年後を洞察してみよう
では、実践してみましょう。
インターネットやSNS、そしてAIなどの登場によって、近年はあらゆる物事が急速に変化しています。これまで何百年も続いていた習慣なども例外ではありません。会社に行かずに働くようになる未来を、はたして30年前の人たちが予想できたでしょうか。
これまでも、これからも、そして100年後も変わらないだろうと思える体験ほど、未来を予測してみると意外な答えが導かれることがあります。たとえばまさに今、この本を手に取ってくれているあなたがしている「読書」。
100年後の〈読書〉はどんなものだと思いますか。
何百年も変わることなく続いてきたこの行為の未来を、AIはどう考えるでしょうか。