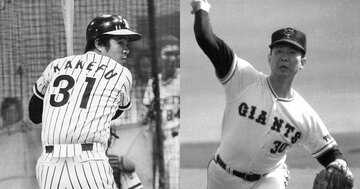南海球団は大阪の街と、勝利のよろこびをわかちあった。そのかがやかしい様子が、よくわかる。プロ野球の球団が、こういう規模で地元の喝采をあびる前例は、ないような気もする。少なくとも、関西圏ではこれが最初であったろう。
4連投4連勝の快挙をなしとげたエースの杉浦も、自伝で御堂筋のパレードにふれている。そのなかで、彼は自分たちの行進を赤穂浪士のそれになぞらえた。「主君の仇・吉良上野介を討ち取って凱旋するシーン」が、脳裏をよぎったという(杉浦忠『僕の愛した野球』1995年)。
1702年に、旧赤穂藩の浪人たちは、亡き主君の仇をうった。宿敵であった吉良の首を、主人の墓がある泉岳寺まで、表通りを歩きながらとどけている。時代劇でもおなじみとなったその行進場面を、杉浦は想像したらしい。
祝祭の絶頂を体験したことで
読売と東京への怨念は薄まった
浪士らの藩主であった浅野内匠頭は吉良に純情をもてあそばれ、切腹を余儀なくされた。そのため、旧赤穂藩の有志たちは復讐へのりだしたのだと、一般的に語られる。そんなストーリーの赤穂浪士に、杉浦は自分たちを見立てている。
どうやら、別所のひきぬきへ走った読売(編集部注/南海のエース・別所昭〔のち毅彦と改命〕が1949年巨人に移籍。「別所引き抜き事件」とされる)を、吉良に擬してもいたようである。
おそらく、御堂筋へあつまった「20万人以上」のファンも、同じように思ったろう。仇討ちの本懐がとげられたという幻想を、南海の選手たちとわかちあったにちがいない。
自伝で杉浦は、こうも書く。「大阪人には東京への対抗意識がありますが、東京の代表チームに完勝した」せいで、「自分らを赤穂浪士になぞらえてしまった」、と(同前)。こちらも、御堂筋の群集は共有したろうか。
私は『阪神タイガースの正体』という本をだしている。そのさいものべたのだが、ここでもくりかえす。