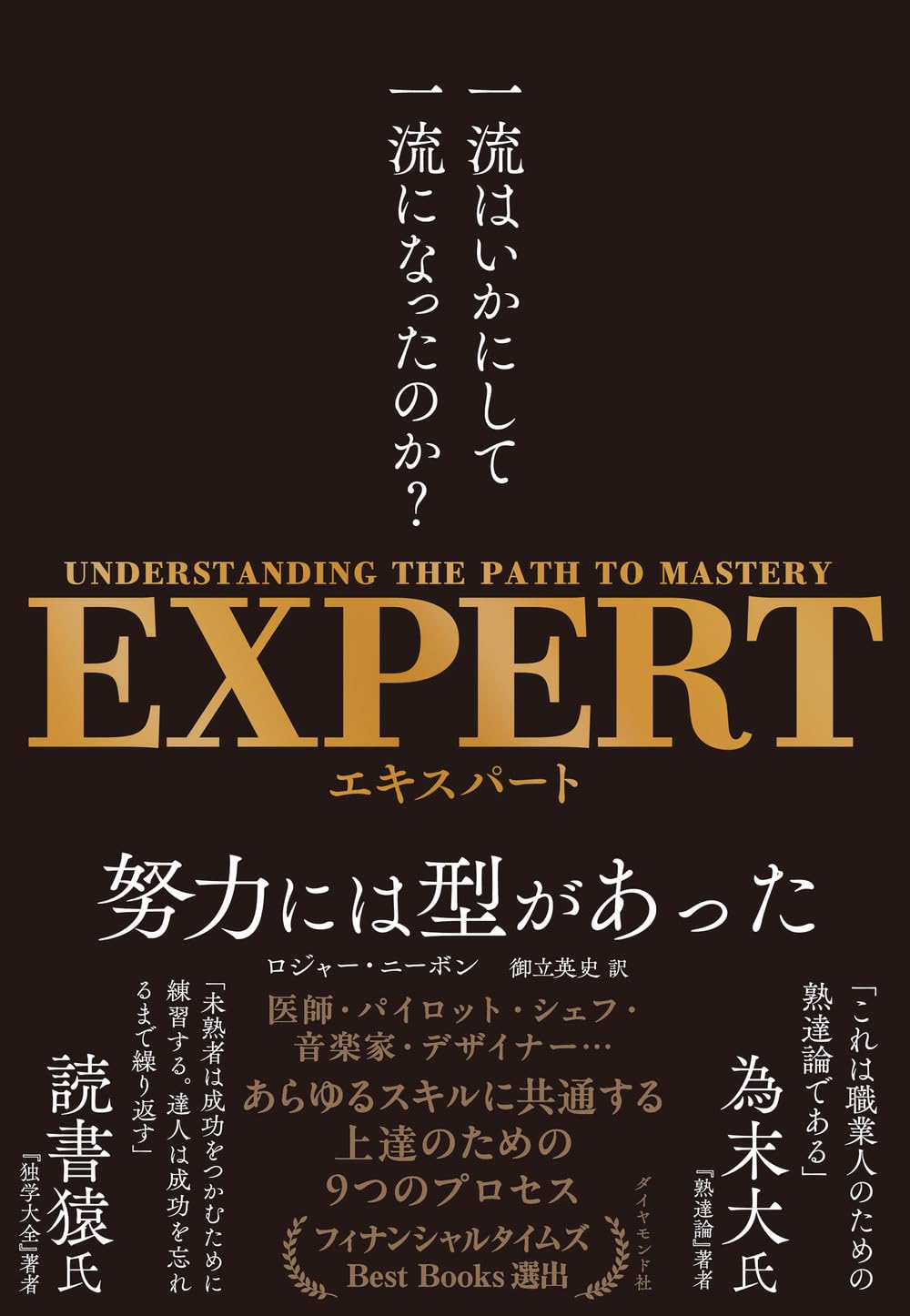新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は部下をダメにする上司のたった一つの特徴を、『EXPERT』を元にしてお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
丁寧に教えているのに部下が成長しない...
上司が力を入れて指導していても、部下が伸びないことがあります。それは一体なぜなのでしょうか。
教育心理学の世界では、「最近接発達領域(ZPD:Zone of Proximal Development)」という考え方があります。旧ソビエトの心理学者レフ・ヴィゴツキーが提唱したもので、「自力ではまだできないが、熟達者の助けがあればできる」範囲を指します。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.373より
上司の役割は、この中間のゾーンを見極めることです。すでにできることを繰り返させても成長はありませんし、逆にまったく歯が立たない難題を与えても挫折しか残りません。
大切なのは、「もう少しで自力でできる」というギリギリの領域に支援を入れることです。そこにこそ、学びの芽が生まれます。
「手を出しすぎる」上司が成長を止める
部下がなかなか育たないチームには、共通する特徴があります。それは、上司がずっとそばにいることです。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.373より
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.373より
足場をいつまでも残したままでは、建物は自立できません。マネジメントも同じです。指導が丁寧すぎる上司は、一見優秀に見えても、実は「部下の自立を遅らせる存在」になっていることがあります。
成長とは「失敗の責任」を取る経験である
ヴィゴツキーの理論が教えてくれるのは、学びの本質が「失敗の中」にあるということです。上司がすべてのリスクを取り除き、正解を先に示してしまえば、部下は考える機会を失ってしまいます。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.374より
本当に人を育てる上司は、あえて部下に失敗の余地を残します。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.374より
「任せる」とは「突き放す」ことではありません。必要なときには支え、そうでないときには距離を取ることが大切です。
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』を元にしたオリジナル記事です。)