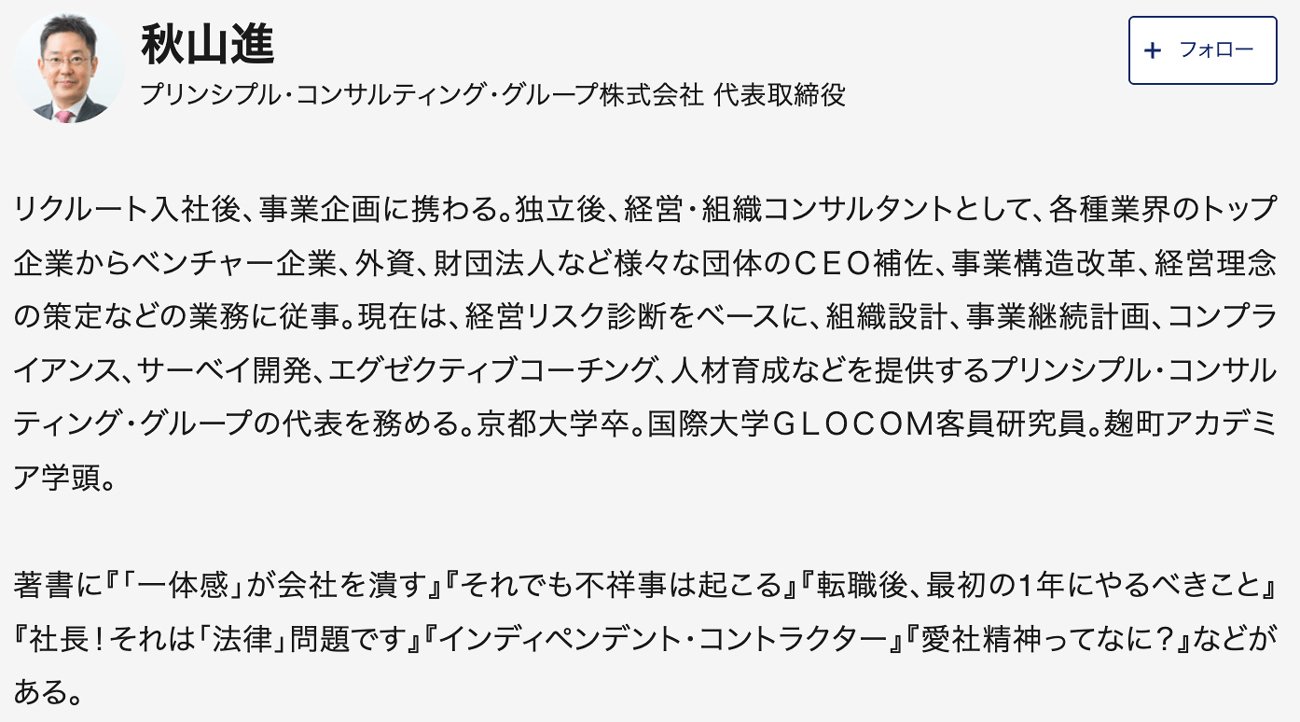「顔の広さ」が可視化されるSNS
知人の話を聞いて以来、私はSNS上のグルメ投稿や写真を、若干疑いの眼差しを込めて見るようになった。
「きっと無償提供だな」「この店はなかなかうまいことやっているな」「ちゃんと“提供”とか“PR”とか入っているかな」……。とはいえ、ほとんどの消費者は深く考えずに投稿を見ているだろうし、お店やインフルエンサーも、問題を指摘されても「違法だなんて知りませんでした」で済ませることになるのだろう。
厳しい「評価経済社会」の一面をのぞき見たような感慨もあったが、この構造は昔から存在した「顔の広さ」や「人脈の力」のデジタル版だともいえる。
かつては「○○さんに頼むと何でもうまくいく」「あの人なら顔が広いから適当な(適切な、の意である、念の為)人を紹介してくれる」という人がビジネスで成功した。いまはそれがSNSという舞台で再生回数やフォロワー数などの数値で可視化され、拡散されるようになっただけなのかもしれない。
現代のビジネスパーソンにとって、無償でサービス提供を受けるという「ただ飯経済」が投げかけるメッセージは明確だ。透明性がないおいしい話ほどリスクがあるという古典的な教訓を、SNS時代にも当てはめることが求められている。
飲食店やインフルエンサーは、ほんの一言「#提供」「#PR」と添えるだけで法的・倫理的リスクを大幅に低減できる。特に小規模店こそ最初から透明性を確保しておくことが、長期的な信頼への投資だろう。
知人の体験は、現代のマーケティング構造をも映し出している。大人数フォロワーだけでなく地域に根ざした少数フォロワーが経済的価値を持つ時代――。そして「ただ飯」という一見些細な行為が、法制度や倫理問題と直結する時代である。
「えらい時代になってきた」と思う一方で、こうした構造を理解し、透明性を確保することこそが、これからのビジネスパーソンに求められる重要なスキルであり、われわれが備えるべき新常識なのだとも思い知った。