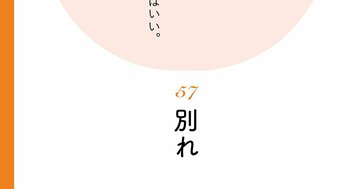なぜ「自分を大きく見せる人」は必ず大問題を起こすのか?
誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医tomyが教える 50代を上手に生きる言葉』(ダイヤモンド社)など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
気をつけたほうがいい人
今日のテーマは「気をつけたほうがいい人」です。世の中には関わる際に気をつけなければいけないタイプがいろいろといますが、今日取り上げるのはその一つ、「自分を大きく見せたい人」です。
これは、かなり要注意かなと私は思います。
「ふかす人」の初期段階
あなたの周りにいないでしょうか? 自分が実際にできることを、少しでも良く見せようと思って「ふかす(話を盛る)人」。まるで自分がもの凄いことをしたかのように言う人です。
こういう人は、最初は些細なことを少し良く言ったり、いわゆる「サバを読む」に近いようなことをしたりする程度です。
レトリックの上達と実態との「乖離」
しかし、この「少しだけ良く言う」ことが、だんだん上手になってきます。レトリック(話術)が上達し、もっと上手に、すごいことをやったかのように見せかけるようになることもあります。
横文字をいっぱい使ったり、長々と話したりしますが、よく聞くと「結局そういうことですよね」という単純な話だったりします。それを、すごく長く、大きく「ふかして話す」傾向があるのです。
そうすると、そのレトリックから受ける印象と、実際の中身(実態)が「乖離」していきます。一つひとつに露骨な誇張や嘘がなかったとしても、トータルとして正直な印象を伝えていないわけですから、これはもう「嘘に等しい」と私は考えます。
やがて本物の「嘘」に変わる
そこまで行くと、本当の嘘が混ざってきます。言っていないこと、やっていないことまで言うようになります。いわゆる「詐称」をする人たちの一部が、これに該当するのかもしれません。
例えば、本当は大学を「中退」したのに、「卒業」したことにしてしまうケースが、少し前にどこかで問題になりました。これも、「ほぼ卒業だよね」というレトリックで、卒業したかのように見せかけるところから始まったのかもしれません。
そこまで来ると、そのレトリックと本当の嘘との差は、ほんのわずかになってきます。そして、「もう面倒くさいから、これは『卒業』ということにしておきましょう」と。これが「嘘」になるわけです。