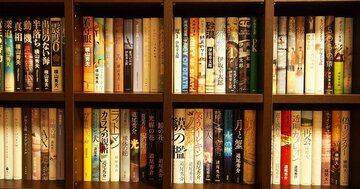「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか?
その名は――ピーター・ドラッカー。
彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。
『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「強みの上に築け」
――吉田さんの著書『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』は、平安時代の人物である光源氏がドラッカーのマネジメントを学ぶという異色の設定ですね。ドラッカーの思想を一言で表すと、どんな言葉になりますか?
吉田麻子(以下、吉田):ドラッカーの著作には、たくさんの名言があります。
「マーケティングの理想は販売を不要にすることである。」
「企業の目的は顧客の創造である。」
これらは経営者であれば誰もが耳にしたことのある言葉でしょう。
けれど、私が最も象徴的だと思うのは「強みの上に築け(Build on strength.)」という言葉です。この考え方は『経営者の条件』(1966年刊)に登場し、多くのマネジャーに“人を生かす”マネジメントの出発点を示しました。
『経営者の条件』の中でドラッカーは、
「成果をあげるには、人の強みを生かさなければならない。弱みからは何も生まれない」と述べています。
この考え方こそ、彼の思想全体を貫く原理だと思います。
組織も個人も、弱点を直そうとするより、強みを生かすことで成果を上げる。
そして、それぞれの人が持つ強みを結集することこそ、「優れた組織の文化は人の卓越性を発揮させる」という言葉に通じるのだと思います。
私自身も、この「Build on strength」という言葉に何度も励まされてきました。
たとえ小さな力であっても、それを発揮できる場所があれば、人は必ず成長できる。個人の強みはやがて他者を助け、組織を育て、社会の力へと変わっていく。「私的な強みは公益となる」。
それが、ドラッカーの思想の根幹にある“人間への信頼”なのだと思います。
没後20年、現代でもドラッカーは通用するのか
――ドラッカーの考え方は、現代の日本社会やビジネスにどう活かせるでしょうか?
働き方や組織の在り方が変化する今、ドラッカーの教えから学べることを具体的に伺いたいです。
吉田:ドラッカーの教えは、いまの日本社会にこそ必要だと感じます。働き方や価値観が多様化し、AIが仕事の一部を担うようになった今、私たちは「正解が一つではない社会」を生きています。
さらに、リーダー像は“指示する人”から“支援する人”へと変わり、副業やパラレルキャリアの広がりによって、
一人ひとりが「自分」をマネジメントする時代になりました。
人材育成やリスキリング(学び直し)もまた、企業の課題ではなく、社会全体のテーマとなっています。
こうした変化のただ中でこそ、ドラッカーの言葉が光ります。
彼は「企業にも企業以外の組織にも、本当の資源は一つしかない。人である」と語りました。どれほどテクノロジーが進んでも、中心にいるのは人間です。AIやデータがどれだけ発達しても、人の意欲や信頼、創造性がなければ、道具である組織は動きません。
ドラッカーが説いた「人の強みを生かす」という考え方は、いまの時代にいっそう重みを増しています。
日本社会には長く「弱みを直す文化」が根づいてきましたが、これからは「強みを伸ばす文化」への転換が求められています。
文化の転換期の中で
吉田:その転換には軋轢もあるかもしれません。
けれど、ドラッカーの原理は、その揺らぎの中に立つ大樹となりえます。人の多様性を尊重し、一人ひとりが持つ力をどう組み合わせるか。
そして、企業が利益を超えて、どんな“社会的価値”を生み出すか。
組織のリーダーも、家庭の中の一人も、それぞれの場で“マネジメント”をしています。
それは単なる経営技術ではなく、「人を生かす方法」を考えること。ひいては、次世代へつなげる、あたたかくいきいきとした社会の実現へとつながること。
ドラッカーの思想は、会社だけでなく、社会や家庭、そして自分自身の生き方にも生かせる学びだと思います。