さらに、地域の総合病院の担当医とかかりつけ医が患者の病気の経過や検査結果、治療の内容などについての診療情報を共有し、役割分担しながら協力して患者を支える「ふたり主治医制」を推奨・導入する動きも各医療機関で広がりつつあります。
頼りになるかかりつけ医
適確に選ぶポイントは?
総合病院の多くは「医療福祉相談窓口」を設置し、退院後に在宅療養になる人や、要介護対象となる人が安心して療養生活を続けられるように、かかりつけ医の候補や地域の介護サービスを紹介する「退院支援」を行っています。退院支援においては、医師や看護師、リハビリスタッフ、医療ソーシャルワーカーなどが、地域のクリニックや介護施設と連携して情報を提供しています。
お勧めしたいのは、親御さんが元気なうちに、近隣の総合病院や入院経験のある総合病院の医療福祉相談窓口に赴いて、どこのクリニックと連携しているのかを確認し、通いやすそうなクリニックを見つけておくことです。その際は、医師やクリニックの雰囲気との相性があるため、候補を複数紹介してもらうとなおよいでしょう。
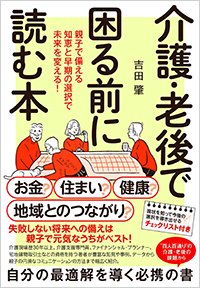 『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』(吉田肇、NHK出版)
『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』(吉田肇、NHK出版)
紹介してもらっても、「選定療養費が数千円余計にかかっても構わないから、やっぱり手術してもらった先生に診てもらいたい」と、大病院に戻ってしまうケースが多くあります。そのときにお子さんが「親がそう言っているのだから……」と流されてしまわないように、医療の仕組みやかかりつけ医を持つことのメリットを早くから親子で共有しておきましょう。
かかりつけ医を選ぶポイントは、「自宅から通院しやすい」「訪問診療や往診を行っている」「病気だけでなく、患者の家族関係や生活全般を理解し、相談にのってくれる」などが挙げられます。今はインターネットでクリニックの口コミ評価を調べたりできるので、お子さんがそうした情報収集を手伝ってあげてもよいかもしれません。医師との相性の良し悪しについては、親御さん本人が確かめるしかないので、風邪を引いたときなどに1度診てもらうとよいでしょう。
早めに行動することで、親世代は、自分に合うかかりつけ医を丁寧に時間をかけて探すことができます。子世代は、親御さんの日々の健康を見ているかかりつけ医をあらかじめ把握しておけば、“もしものとき”の心強い支えとなるはずです。







