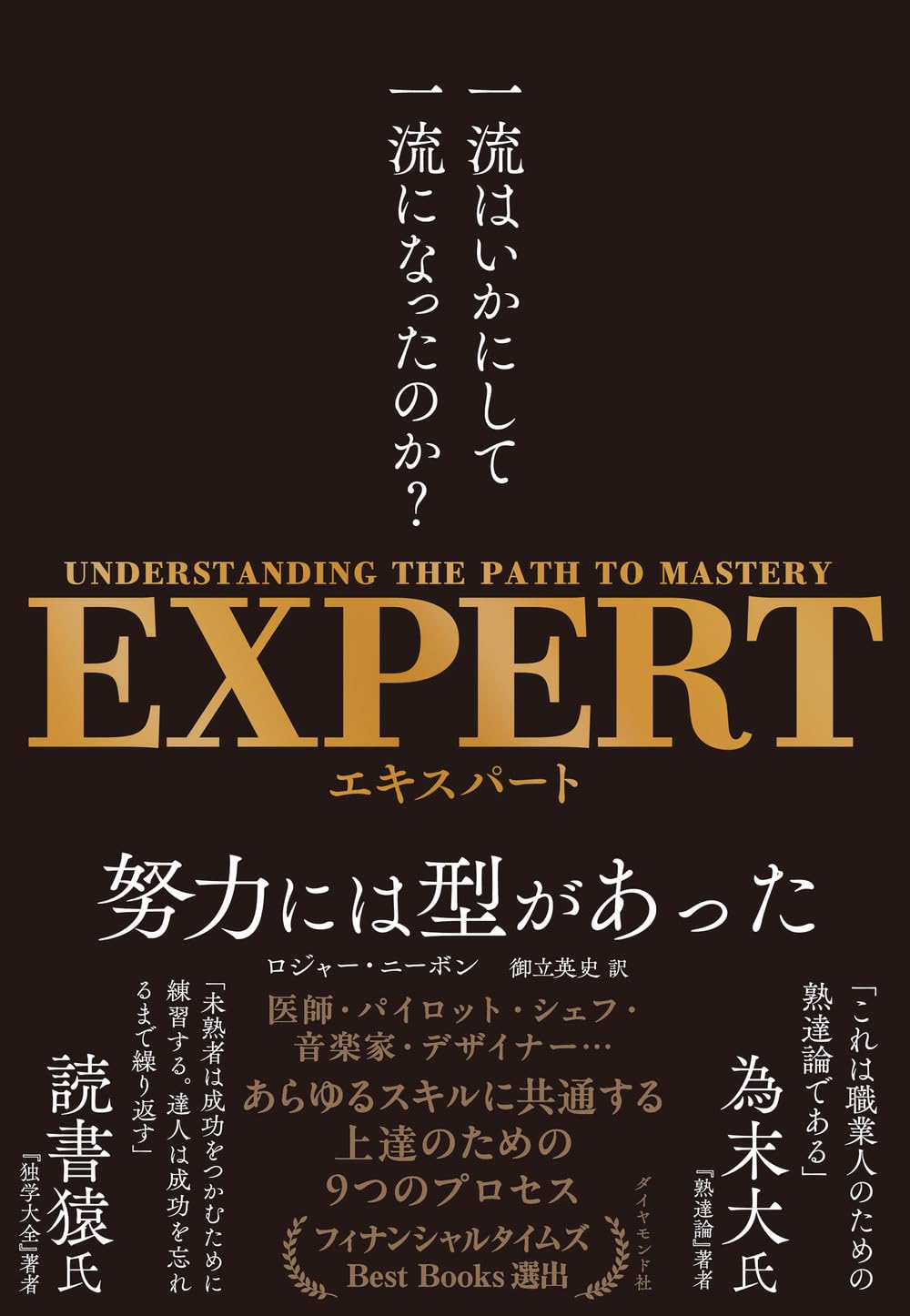新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は「感覚をつかむということ」について『EXPERT』の本文から抜粋してお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
感覚をつかむということ
私たちはどの一瞬を切り取っても、どれか一つの感覚だけを使っているということはない。「アリストテレスの五感」─触覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚─が感覚のすべてというわけでもない。神経科学者や哲学者によれば、人間の感覚はどうやら二五種類もあるらしい。それらは、身体の外から入ってくる情報を認識する「外受容」と、身体の中で発生する情報(バランスや方向の感覚、生理的作用など)を認識する「内受容」に分けられる。
達人になるためには、外の世界と内の世界を統合することが不可欠だ。感覚を働かせることで、視野に入ったものを見、流れ去る音を聴き、触れたものを感じ、匂いを嗅ぎ、口に入れたものを味わうことができる。その際、感覚を通じて得る情報は固定的なものではなく、自分の興奮、疲労、空腹、ストレスといった精神的・身体的状態に影響されることも覚えておく必要がある。
アリストテレスの五感にしても、従来の区分では説明しきれない面がある。共感覚〔ある感覚が刺激されたときに他の感覚も同時に惹起される現象〕などという医学的・神経科学的概念を知らなくても、私たちはある感覚が別の感覚を惹起することを体験的に知っている。私は外科医として、指で“見る”ことを学んだ。患者の腹腔の奥深くに手を差し入れ、見えない部分に触れることで臓器の全容をイメージし、正常と異常を見分けることができる。
これは分野や扱う素材を問わず、熟達した人ならだれでもやっていることだ。シルクとフランネルが違うのは当然だが、同じシルクでも布の一枚一枚に特異性がある。もちろんフランネルも一枚一枚が違う。小説と博士論文も、長さは同じでもまったくの別物だ。
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)