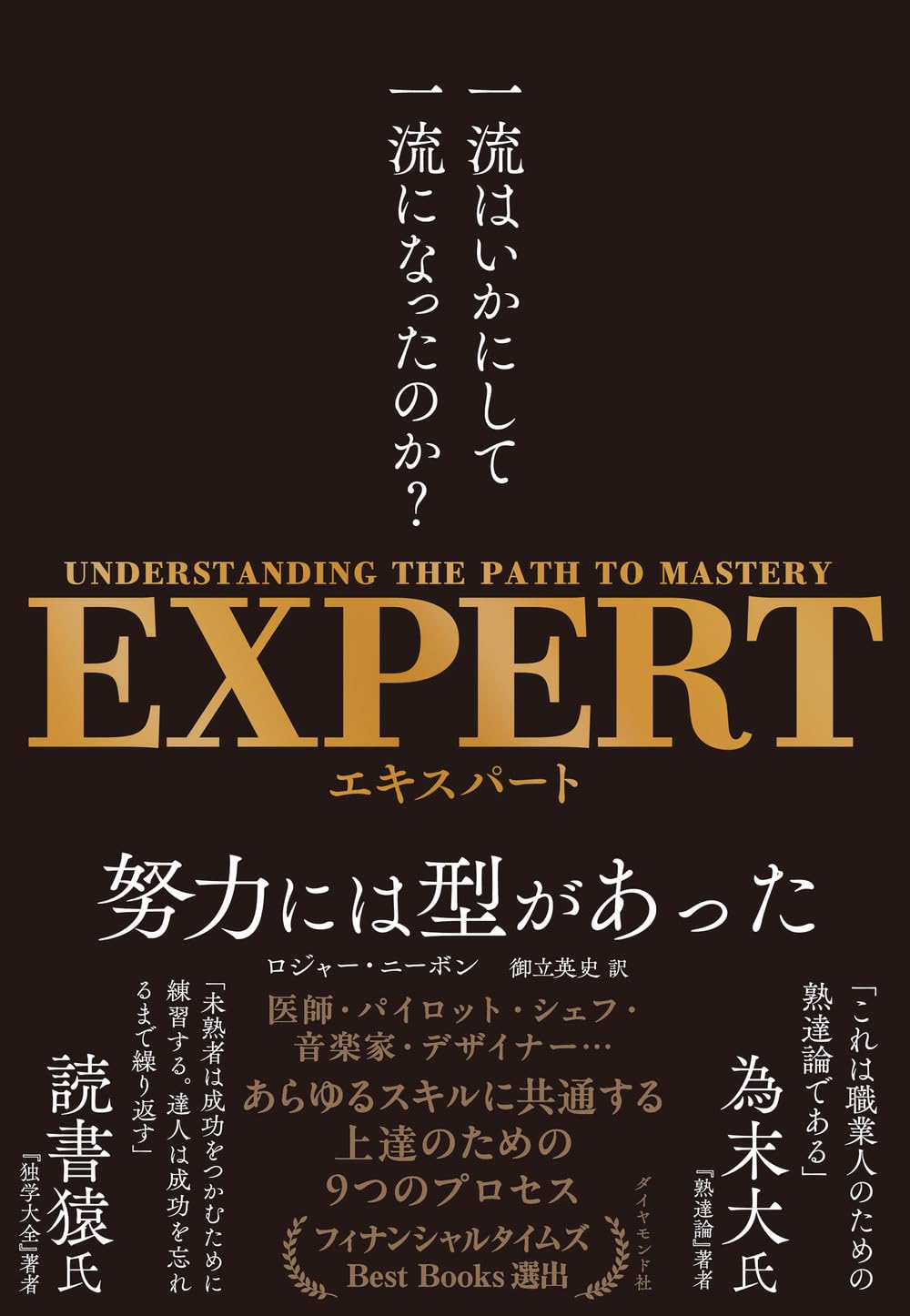新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は一流だけが知っている感覚の正体について『EXPERT』の本文から抜粋してお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
感覚の正体
感覚にも独自の特性がある。たとえば触覚には、視覚や聴覚にはない即時性がある。視覚や聴覚は「遠隔知覚」とも呼ばれる。私がだれかを見ても、相手も私を見るとはかぎらないし、こちらが相手の声や音を聞いていても、相手がこちらの声や音を聞いているとは限らないということだ。視覚や聴覚は一方通行で成り立つことがある感覚だと言える。他方、触覚は即時かつ相互的な「近接知覚」である。私が何かに触れた瞬間に、その何かも私に触れ返す。それは対象が生物でも無生物でも同じで、触覚においてはつねに双方向のフィードバックが生じる。
医療の現場では、触覚のこうした特性が特にはっきりと現れる。意識のある患者を診察するとき、患者は必ず医師に触れられていることを認識する。それを意識させずに診察することはできない。これは医師にかぎらず、人と関わる仕事全般に当てはまる。相手から情報を受け取るとき、自覚していなくても、自分も相手に何らかの情報を発信している。駆け出しの美容師だったころのファブリスも、客の髪を洗いながら、自分自身に関する何らかの情報を客に伝えていたのだ。
自分が扱っている対象に気づくには、感覚を研ぎ澄まさなくてはならない。それには鍛錬が必要だ。私たちは往々にして感覚を眠らせ、情報を遮断してしまう。見えているのに見ておらず、聞こえているのに聴いておらず、触っているのに感じていない、ということは珍しくない。気づくというのは、いま、ここ、を意識して注意を払うことだ。同時に、材料と自分の交差にも注意を向けることだ。
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)