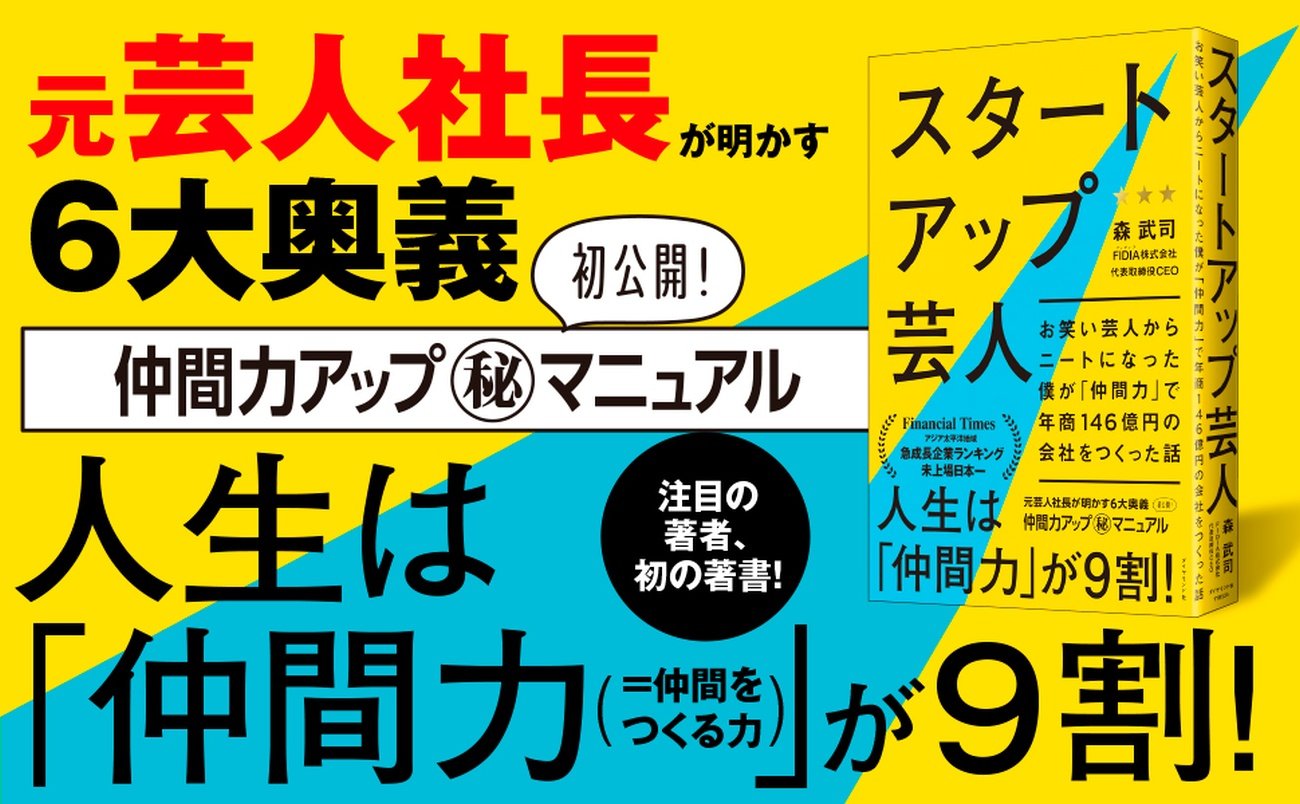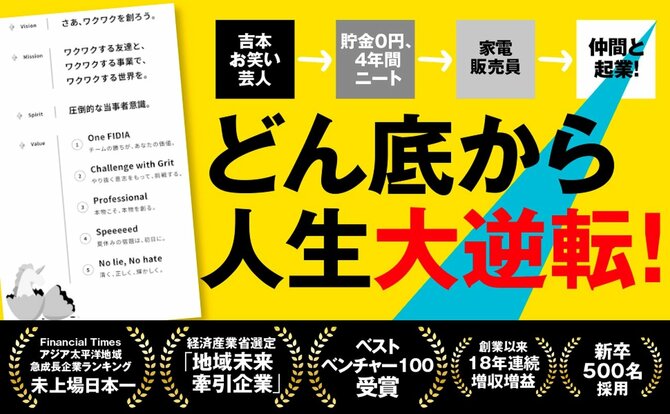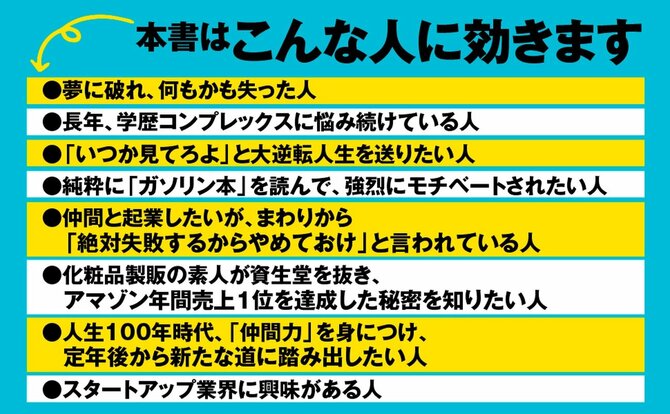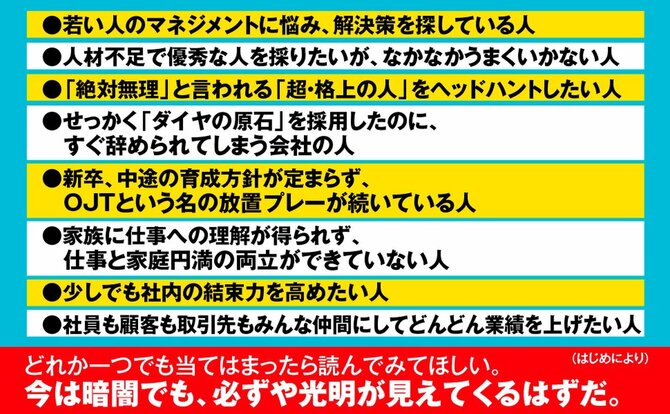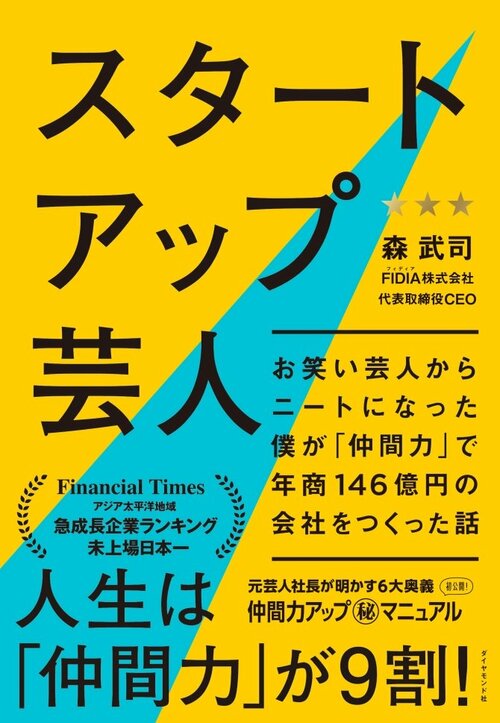「能力も情熱もあった。なのになぜ辞めた?」――そんな疑問を抱いたことはないだろうか。ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり! 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は芸人からニートを経て起業し、仲間と共に会社を育ててきた。その哲学に影響を受けた経営者が、株式会社Stella Point代表・米川凱(よねかわ・がい)氏だ。
優秀な人材を採用したはずが、数ヶ月で離職。その繰り返しに悩んでいた米川氏は、ある「見落とし」に気づいた。採用基準を見直した結果、社内の空気は一変し、離職率も劇的に改善したという。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「能力×情熱×人間性」で仲間を見極める
――仲間を見極めるうえで、大切にしていることを教えてください。
米川凱(以下、米川):『スタートアップ芸人』を読んで、「能力×情熱×人間性」という考え方にビビッときたんです。
能力と情熱で評価することはよくあるけれど、そこに“人間性”を加えるという発想は、この本で初めて意識しました。
実は過去に、能力も情熱もあるのに辞めてしまった人がいたんです。
振り返ると、価値観の根っこがズレていた。どんなにスキルが高くても、人間性が合わないと長くは続かないんだと痛感しました。
それ以来、採用基準に「人間性」を追加しました。ただ、人間性って履歴書ではわからないじゃないですか。だからこそ、まずは一緒に食事をしたり、オフィスで半日過ごしてもらったりして、お互いの温度を確かめる時間を持つようにしています。紹介でつながった方とも、いきなり採用せずに、まずは関係性を育てることを大事にしています。
「目配り・気配り・心配り」がカルチャーの土台
――人間性を重視するようになって、会社にはどんな変化がありましたか?
米川:僕が考える人間性とは、「目配り・気配り・心配り」です。
ゴミが落ちていたら拾う、陰口を言わない――そんな当たり前の行動の積み重ねが、カルチャーの土台になると思っています。
カルチャーの浸透を大切にしているからこそ、人間性が合わないと組織全体の方向性がズレる。
だから採用でも「この人はStella Pointっぽいか?」を常に意識しています。
「陰口を仕組みで防ぐ」コツ
――『スタートアップ芸人』の「悪口・陰口を言わない仕組み」にも共感されたとか。
米川:はい。あの部分はページ数まで覚えているくらい印象的でした。
僕自身、過去に不用意な言葉で人を傷つけてしまい、それがきっかけで辞めた方もいます。悪口って本当に伝染するんですよね。だからこそ、“仕組みで防ぐ”という考え方に共感しました。
実際に、弊社でも評価項目の中に「オフィスのドアをくぐったらネガティブ発言NG」というルールを設けています。わざわざバリューとして掲げるまでもないけれど、毎日の行動基準として意識しています。
そして何より大事なのは、トップが体現すること。僕自身が率先してポジティブな姿勢を見せることで、自然と空気が変わっていくと思っています。
「辞められない会社」にするための仕組みと「余白」
――とはいえ、飲み会などで愚痴が出ることもありますよね。そういう時は?
米川:まずはしっかり“聞く”ようにしています。
フラストレーションをため込まないようにするのも経営者の役目。
ただ、場の雰囲気が悪くなりそうなら「その話はやめよう」「あとで個別に聞くね」とフォローします。
人間関係のトラブルって、放置すると退職につながりやすい。
だから僕は、“辞めずにすむ仕組み”をつくることを意識しています。
たとえば、適性診断を取り入れて相性を見たり、部署異動を柔軟にしたり。
配置転換できる会社であれば、人間関係が合わなくても辞める必要はないですよね。
――最後に、採用に悩んでいる経営者の方にメッセージをお願いします。
米川:能力や情熱だけで人を選んでいると、いつか必ずカルチャーにヒビが入ります。でも、人間性まで見極めた仲間なら、一緒に長く走れる。僕はそう信じています。
「人間性を見極め、受け入れる器を持った会社」――それが、僕の理想のチーム像です。
辞められないほど働きやすい会社をつくりたい。そのためには、採用の段階から“仲間”として迎える意識が必要だと思います。
『スタートアップ芸人』には、そんな“仲間づくり”のヒントがたくさん詰まっています。採用や組織づくりに悩んでいる方には、参考になると思いますよ。
(本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。)