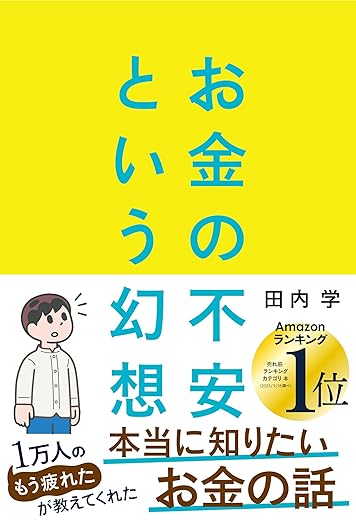「お金の不安」の向かう方向が誤った方にずれてきている
――確かに最近は、「お金の不安」という言葉をあちこちで耳にします。どうして、こんなにも多くの人が不安を感じるようになってしまったのでしょうか。
情報環境の変化が大きいと思います。雑誌や新聞が主な情報源だったころは、そこに一定の編集方針やチェックがあり、極端に偏った情報に触れることは少なかったと思います。「投資しないと損をする」なんてあおられることもほとんどなかったと思います。
ところが今は、SNSやネットニュース、動画サイトなど、オンライン上のメディアが増えるにつれて、「投資しない人は負け組」「今すぐ始めないと手遅れ」といった刺激的な言葉が日常的に流れてきます。理由は単純で、刺激的で不安をあおる見出しほど、人目を引きやすいからです。
そうした情報を繰り返し目にするうちに、「何もしていない自分は遅れているのでは」と感じてしまうのは無理もありません。
不安そのものが悪いわけではありません。それを行動につなげて改善に向かっていけるなら有効な不安と言えますが、今はその不安が焦りの方向にずれてしまっている。ネット上のどこかで見聞きしたのか、たとえば、「港区の幼稚園では株の取引を教えているらしい」「小学生に資産運用を勉強させておいたほうがいいのか」と、真に受けて焦ってしまう親御さんも少なくありません。
「焦り」につけ込むような情報も多く出回っています。
「このメルマガを読んだら、100万円が1億円になりました」といった極端な成功談を目にすることもありますが、そうした発信の裏には必ず意図があります。発信する側にも、利益や目的があるのです。だからこそ情報を見極めるためには、「一歩引いて考える姿勢」が欠かせません。焦りに流されず、自分のペースを守ること。それがこれからの時代を生きるうえで何よりも大切です。
他人の成功に惑わされず、「自分のモノサシ」を持つ
――書籍にあった「不安は、他人のモノサシから生まれる。安心は、自分のモノサシから始まる」という言葉がとても印象に残りました。知らないからこそ不安になるのは当然のことですが、知ったうえで「自分の軸をどこに置くか」を考えることが大切だと感じます。「港区の幼稚園では株の授業をしている」といった話に焦ってしまうのも、自分がよく分からないからこそ「子どもには失敗させたくない」という思いが働くからではないでしょうか。その不安の正体に気づくだけでも、少し前に進めるように思います。
確かに、親世代には「働いても報われにくい時代」を長く生きてきたという背景があります。いわゆるロスジェネ世代、就職氷河期世代と呼ばれる人たちは、努力しても給料が上がらず、就職も安定しないという現実を経験しました。
そうした時代を生きてきた世代にとって、「頑張っても報われない」という感覚は強く残っています。
だからこそ今、「働く」ことと「投資する」ことを比べたときに、投資のほうが「努力が報われるように見える」のだと思います。働いても給料は上がらないけれど、投資は銘柄の選び方次第で結果が変わる。しかも、情報があふれる社会では「勉強すれば稼げるようになるかもしれない」と感じやすい。
実際に大きく稼ぐ人がいるのも事実です。だから『自分も頑張れば』と思うのは自然なことです。
けれど、投資の世界はプロの金融機関も多くの人参入しており、少し勉強したくらいでは勝てるはずがない。むしろ、うまく仕組みを理解している側にカモにされてしまうことも少なくありません。
投資には、経済の成長によって利益が生まれるという健全な側面もあります。たとえば自動車が生まれ、私たちの生活が豊かになれば、その会社の株主にも利益が還元される。それは本来の「経済の循環」です。ただし、経済の成長はせいぜい数%。株価が10%、20%と上がるときには、そこに「先回り買い」などのギャンブル的な要素も含まれています。それをしっかりと理解して、過度な期待を抱かないことが大切です。
不安や焦りの中で「正解」を探そうとするほど、人は見えやすい答えに流されてしまいます。
けれど、人生に絶対正解などありません。だからこそ、自分の軸を持つことが、何よりの安心につながるのだと思います。他人のモノサシではなく、自分のモノサシで生きる――。
そのシンプルなことを忘れないだけで、不安は少しずつ小さくなるのかもしれません。