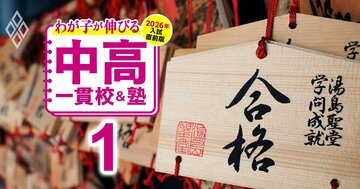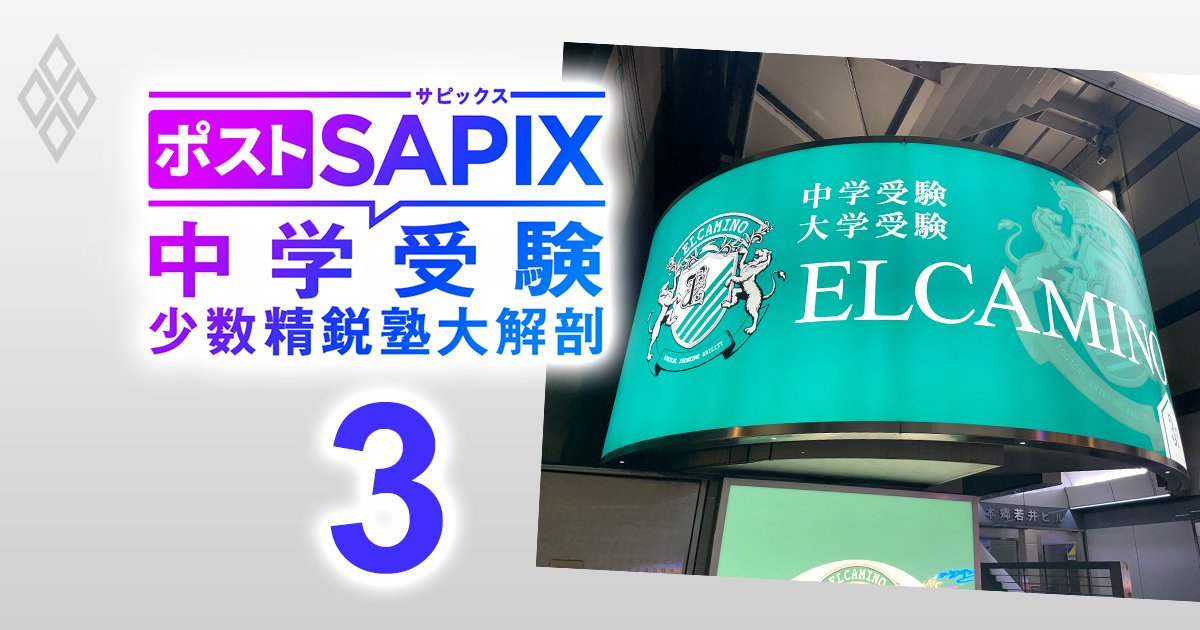 Photo by Toshimasa Ota
Photo by Toshimasa Ota
首都圏における中学受験塾の王者、SAPIX(サピックス)の凋落がささやかれる今、難関校志向を売りとする「少数精鋭型」の中学受験塾の人気が高まっている。知られざる少数精鋭塾の神髄を各塾のキーパーソンへの忖度なしのインタビューで明らかにする連載『ポストSAPIX 中学受験の少数精鋭塾大解剖』#3では、御三家など最難関校への合格率でSAPIXを凌駕すると言われ、ハイレベルの算数教育で高い支持を集める「エルカミノ」の幹部と対談。その前・中・後編のうち前編をお届けする。(教育ジャーナリスト おおたとしまさ)
小3から小4への内部進級テストで
約3分の1の生徒が退塾に
おおたとしまさ この企画は塾カタログではなく、中学受験の過去・現在・未来を各塾の先生方と一緒に読み解くことに軸足を置いています。そこから各塾の思想や特徴も見えてくるのかなとは思っています。まず基本情報として、いつ、どんな経緯でこの塾ができたのでしょうか。
古庄歩エルカミノ副代表・理科総合責任者 設立は2006年です。逆におおたさんはいつぐらいからエルカミノのことを認識されていましたか。
おおた 少なくとも16年に『ルポ塾歴社会』(幻冬舎新書)を書いたときには認識していましたから、10年ちょっと前ぐらいですかね。
古庄 10年前ですと、まだ校舎は8校ですね。
おおた 今は何校舎ですか。
古庄 14校舎です。もともと、代表の村上(綾一氏)は大手学習塾で御三家のコースを担当しており、その後にフリーの講師に転身しました。いわゆる外部講師として算数の指導を各塾で行いながら、メインは教材制作の仕事をしておりました。
おおた フリーランスで?
古庄 そうです。個人事務所を目白に構えて仕事をしていたのですが、空いている時間に近所の子どもたちを見ているうちに、どんどんと口コミが広がり生徒が増え、これはもうちゃんと組織化しないとまずいな、というところでつくったのが06年です。
私も同じ大手塾の講師でした。村上と「いつか一緒に塾をやろう」なんて話していましたが、その後、私は天文関係の仕事など、いろいろなことをやっていました。「じゃあ理数系専門塾ということでやろう」とつくったのが、当初のエルカミノです。
 算数教育の強さで知られるエルカミノの本郷三丁目校 Photo by T.O.
算数教育の強さで知られるエルカミノの本郷三丁目校 Photo by T.O.
おおた 現在の生徒数を学年別にお願いします。高学年だけで結構です。
古庄 4年生が約400人、5年生が約300人、6年生は約200人です。うちは新規校舎をつくっても、開校1年目は1~3年生のみしか受け付けません。練馬とか大井町とか、まだ5年生しかいない校舎もあるので、低学年になるほど生徒数が多くなる構造だというのと、やはりやめてしまう生徒もいます。特に内部進学の生徒(私立小学校から系列の中学に進むことが決まっているが、中学受験組に引けを取らない学力を付けておくために通塾している)は、高学年になると学校が忙しくなり、塾との両立が難しくなります。
おおた 続いて合格実績についてですが、ホームページを拝見すると、パッと目立つところにはないですよね。
古庄 下のほうにあります。
おおた モノクロのワープロで打ったようなPDFがペロンと貼り付けてあるだけで、特定の学校を強調したりはしていない。筑駒(筑波大学附属駒場)、男子御三家(開成、麻布、武蔵)、女子御三家(桜蔭、女子学院、雙葉)、フェリス女学院、駒場東邦、灘、渋幕(渋谷教育学園幕張)、渋渋(渋谷教育学園渋谷)の12校は、上のほうに書かれていますけれど。
古庄 筑駒15人。男子御三家は、開成18人、麻布3人、武蔵8人。女子御三家は、桜蔭が3人、女子学院も3人、雙葉が1人。あと灘が8人ぐらいですかね。
おおた 自塾の合格者としてカウントする線引きは?
古庄 入塾金を納めてくれた正式な塾生で、2月の受験の時までうちで指導している生徒です。講習会は塾生にならなくても受講できますが、そういう生徒は含めていません。
おおた 最後の仕上げをお願いしたいと、6年生の秋以降に滑り込みで入ってくるような生徒さんは?
古庄 そういうパターンはうちにはほとんどいないですね。
おおた なるほど。
古庄 よく『週刊ダイヤモンド』さんみたいな媒体に「3人に1人は最難関校に行く」とか、「4人に1人は御三家に行く」などと書かれます。しかし、今まで私たちは、自ら超難関校や御三家の合格率を発表したことは一度もありません。たぶん今後もしないと思います。
おおた なぜですか。
古庄 小3の秋にエルカミノ内部の進級テストで一定の点数を取らないと小4には上がれません。これは厳格です。それで、3分の1ぐらいの生徒は退塾になってしまいます。
おおた 3分の1も。
古庄 冷たい塾みたいに思われるかもしれませんが、なんとか受かってもらいたいと思って、年内いっぱい補講もやりますし、再テストもやります。なぜそういうことをするのかというと、うちの代名詞になっている小4以降の算数のテキストについていけない可能性が高いお子さんにも、その子らしい中学受験をしてほしいからです。決して「できない子はいらない」と言っているわけではありません。
おおた 情けで入れてしまっても、結局その子がつらい思いをするだけだということですね。ほかの塾でやったほうが結果的にその子にとっては学びやすいかもしれない。それはその通りだと思います。
古庄 そのぶん分母が絞られるので、最終的な合格率が高くなるのは当たり前です。だから割合は打ち出さないようにしています。
おおた 厳しい進級テストを課している代わりに、自ら合格率をアピールはしないという姿勢がセットになるわけですね。このあたりに御塾のスタンスがよく表れているなと思います。あと、合格実績だけを見ると男子校のほうが圧倒的に多い。生徒数も男子のほうが多いですか。
古庄 圧倒的に多いです。女子を増やしていきたいというのが今後の目標の一つです。女子の御三家が全部そろったのは今年が初めてなんですよ。
おおた では、話を本論に進めましょう。過熱気味だった中学受験も、今後は少子化でピークアウトすると言われていますが、そんな流れの中で、中学受験がどうなっていくと予想されるか、あるいはどうあるべきだとお考えか、そのあたりを伺っていきたいのですが。