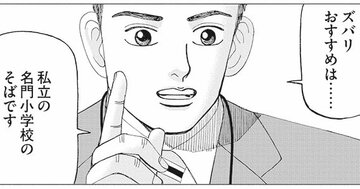いずれはSBI名が取れる日が来るだろう。その予兆のように、SBI証券との取引において「SBIハイブリッド預金(住信SBIネット銀行)」は、前述の「SBIハイパー預金(SBI新生銀行)」と併用できないとされた。
新生銀行のサイトに『住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金」をご利用中のお客さまが、SBI新生銀行の「SBIハイパー預金」をお申し込みする場合には、住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金」を休止していただく必要があります。』と冷たく書かれている。
なお、金利も「SBIハイパー預金」の方が約2倍も高い。SBI証券での取引をメインで行う利用者がどちらを選択するかと言えば、じわじわSBI新生銀行へと移動していくことになるのではないか。
NISAは長期視点
積立資金で銀行は安定運営
このように各銀行が証券口座との連携に力を入れているのは、NISAを意識してのことだろう。SBI新生銀行は、指定した金額を定期的に普通預金からSBIハイパー預金へ振り替える「定額自動振替サービス」も始めた。
NISAで投信積立をしている人は、このサービスを利用すれば自動的に資金を入金できる。NISAでの積立は短期というより長期にわたって続ける想定のため、利用する証券会社をちょくちょく乗り換える人はそう多くはいない。証券口座とつなげることで、積立資金の入り口となる銀行の方も、長期かつ安定的に顧客を囲い込めることになる。
NISA口座といえば、SBI証券と楽天証券の2大ネット証券がそのほとんどを押さえている。当然、楽天証券は楽天銀行と「マネーブリッジ」という口座連携サービスでつながっている。
そうなると、おのずと他の銀行はSBI証券と組もうとするだろう。例えば三井住友銀行の場合、利用者がSBI証券の口座開設をしたうえで三井住友カードでクレカ投資積立をすれば、Vポイントを貯められる。
金利優遇ではないが、ポイント還元の最大は4%だ(ただし、三井住友カードの最上位カードである Visa Infiniteの場合だが)。今後もSBI証券と仲良くしたい金融機関は増えてくるに違いない。