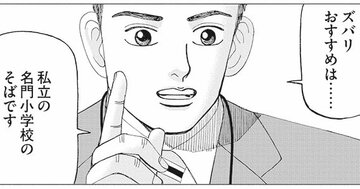ちなみに、楽天銀行でマネーブリッジを設定すると、楽天銀行の普通預金が最大で年0.28%まで優遇になる。金利だけで見ると先のSBIハイパー預金に大きく見劣りするが、楽天証券のお客はいわゆる“楽天経済圏”の住人なので、ポイントプログラムなどを武器に我が道を行くということか。
ポイント経済圏で見る現在地
今後台頭しそうな証券会社は?
ここで視点を変えて、口座連携の現在地をポイント経済圏の側からも見ておこう。
楽天経済圏=楽天銀行×楽天証券
au(Ponta)経済圏=auじぶん銀行×SBI証券
Vポイント経済圏=三井住友銀行×SBI証券
PayPay経済圏=三井住友銀行のVポイントとPayPayポイントの相互交換を予定
ドコモ(dポイント)経済圏=住信SBIネット銀行(d NEOBANK)×SBI証券
これを見れば、SBI証券やSBIグループが、いかに手広いかがわかるというものだ。
しかし、ここに加わるべき証券会社がもう一つある。ドコモグループのマネックス証券だ。同証券では取引口座とdアカウントを連携したり、dカードでクレカ投資積立することでdポイントを貯めたり買付に使ったりができる。
10月に同証券が出したリリースによれば、dアカウントを連携している個人投資家のNISA口座開設率は62%だそうだ(2024年1月以降、2025年9月末現在)。ドコモ経済圏にいる投資未経験層が、ドコモグループ入りをきっかけにマネックス証券に口座開設をしたのだろうとして、シナジー効果があったと分析している。
そして住信SBIネット銀行(d NEOBANK)が加わった今、同銀行にマネックス証券との口座連携預金あるいは連携サービスが生まれるだろうことは想像に難くない。
とはいえ、ドコモとしても難しいところだ。dポイント経済圏を成長させるためには、マネックス証券との連携預金を新設して、それこそ年0.3%以上の魅力的な金利やポイント還元特典を武器に預金者を集めるのが王道だろう。
その一方で、SBIハイブリッド預金の0.21%と大きな金利差をつけて、SBI証券ユーザーのさらなる流出を招くのも得策とは言えない。外野で見ている分には面白いが、悩ましいに違いない。“ドコモ銀行”と“ドコモ証券”の今後に注目したい。
金利は税引き前。11月13日現在。